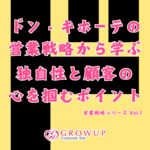Blog
ガソリン暫定税率廃止の先にあるもの|EV時代の新たな税制を考える

ガソリン価格が下がれば、家計は助かる。
「暫定税率が廃止される」と聞けば、誰もが一瞬ほっとするかもしれません。
――しかし、はたして喜んでばかりいられるものか?
老朽化した下水道管が腐食し、道路が陥没。走行中のトラックが落下し、運転手が死亡する事故が起きました。
原因は、硫化水素による下水道管の腐食と、そこから生じた地中空洞。
“見えない老朽化”が、とうとう人の命を奪うかたちで現れたのです。
いま国会では、物価高対策の一環として「ガソリンの暫定税率廃止」が議論されています。
けれども、この流れのままEV化が進めば、私たちは「燃料課税」という財源の柱を失う未来に直面します。
ガソリンが安くなることは短期的な朗報であっても、その先にあるのは、道路も橋も下水道も支えられなくなる日本かもしれません。
――では、その先の社会をどう支えるのか?
距離・重量・デポジット・スマートメーターという新しい仕組みから、“走ることが社会貢献になる”税制のかたちを一緒に考えていきましょう。
与野党6党が年内廃止を視野に協議で一致。暫定税率(25.1円/L上乗せ)は1970年代の道路特定財源起源で、物価高対策として撤廃に向けた実務協議が継続中。
国会討論や党内審議でも「暫定税率の廃止」や減税が論点化。
そもそも暫定税率は“燃料を買うほど税収が増える”仕組み。EVシフトが進むほど税基盤は痩せるため、短中期の家計対策としては効果があっても、中長期の財源設計としては持続しません。
暫定税率を薄める/廃止すると、地方道路関連の収入も逓減。だからこそ代替財源(”誰から・何に対して・どう徴収”)の設計が必須。
海外では燃料課税の縮小に合わせて、走行課金やEV登録追加料に移行する例が増加。
「これはとても飲み込める金額ではありません。税収の減収分をどういう形で埋め合わせていくのか、国においてしっかり検討し考えて頂きたい」
廃止による県財政への影響として「123億円の減収となる可能性」を指摘しています。
道路だけではありません。地方自治体が抱える課題は、
といった「見えない維持コスト」にも広がっています。
特に水道管は、全国で平均法定耐用年数(約40年)を超えた管が4割を超え、2030年代には一斉更新期を迎えると試算されています。
地方自治体にとってガソリン税や地方揮発油税は、これらの基礎インフラ維持の“最後の砦”。
暫定税率の廃止は単なる燃料価格の問題に留まらず、地方インフラの延命戦略そのものに直結します。
EV普及=ガソリン購入量の構造的減少=燃料課税ベースのやせ細り。
「今はガソリン安くしよう」だけでは先送り。
“燃料から走行へ”の課税ベース転換(例:距離課金/重量連動/道路利用課金)が現実解。
「ガソリン税収が減るのは時間の問題です。地方道路の維持費は年々膨らみ、舗装更新や除雪にも影響が出かねません。EV化の波を止めることはできない以上、”EV時代の新たな道路財源モデル”を早急に国と議論すべきです」
「ガソリン車が減れば、当然ながら市に入る地方揮発油税も細ります。市民の移動の質を落とさずにどう財源を確保するか――”走ることへの課税”への移行を真剣に検討すべき時期だと感じています」
現状の日本のEVは、環境性能割や重量税の免除・減免、補助金支給(国+自治体)など、政策的な”後押し”によって普及を進めている段階。
つまり、今はまだ「EVが市場で自立する前夜」であり、税制優遇による普及促進期にある。
そのため、EV優遇の裏でガソリン車を保有する世帯に過度な負担を求めることは、本末転倒です。
ガソリン車を維持するのは、都市部よりも地方の通勤・生活に不可欠な”移動インフラ”を抱える世帯が多く、一律な増税や負担転嫁は、地域間の不公平を拡大させる懸念があります。
EVが普及していない地方においては、ガソリン税・自動車税が引き続き地域交通の生命線。
一方、都市部ではEV化が急速に進み、インフラ整備費の原資がガソリン税収では支えきれなくなる。
この二重構造の狭間にあるのが“いま”の日本であり、国は「EVを優遇しながらも、ガソリン車ユーザーの生活を圧迫しない」公平な過渡期設計を取る必要があります。
→ 高価格帯のEVは優遇縮小、一般世帯向けは継続支援
→ 一律増税ではなく、地域交通事情に応じた段階的負担
→ 「燃料課税 → 走行距離課税」への移行を進めつつ、低所得・地方世帯の免除措置を同時に議論する
世界各国はすでに「燃料課税から走行課金」への移行を本格化しています。
その背景には、EV普及の恩恵を受ける層と、負担を強いられる層の不均衡を是正する目的があります。
これまでEVは自動車税(VED)免除でしたが、2025年登録分から段階的に課税へ。
初年度£10、2年目以降は標準£195。高額車には「Expensive Car Supplement」(追加課税)も課す。
→ “EVも道路を使う以上、応分の負担を”という理念に基づく政策転換。
多くの州がEV登録追加料(50〜250ドル)を導入。
ユタ州では1マイルあたり1.11セントの「Road Usage Charge」制度を試行中。
オレゴンやハワイでは、距離課金を義務化する方向で議論が進行。
→ 燃料課税が機能しなくなる前に、データ連動型の課税インフラを先行整備している。
フランス・ドイツでは、車両重量やCO₂排出量に応じた課税体系を採用。
EVは優遇対象である一方、高価格・大型EVには追加課税を導入。
→ 「環境にやさしい」だけでなく、道路負荷・資源コストの公平性を評価軸に加える方向。
日本のEV政策はまだ「導入初期の税制優遇+補助金」で支えられています。
しかし、次のフェーズではEVユーザーにも“応分のインフラ負担”を求める設計が不可避となります。
EVを買える人だけが恩恵を受け、ガソリン車ユーザーがインフラ維持費を肩代わりする――そんな不公平を残したままでは、社会全体の合意は得られません。
世界各国は「燃料課税→走行課金」へ移行していますが、距離課金だけでは不公平が残ります。
都市部の軽自動車と地方の大型SUV、どちらも同じ距離を走っても、道路への負荷・環境への影響は大きく異なるからです。
「道路使用権デポジット制」
軽EV(1t未満)で年間5,000km走行 → デポジット 15,000円
SUV(2t級EV)で年間5,000km走行 → デポジット 30,000円
※基準単価:1t・1,000kmあたり3,000円相当(試算)
これにより、重量の大きい車がより多くのインフラ維持コストを負担し、環境・道路保全・地域公平の3側面を同時に達成します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 「距離×重量 デポジット型道路使用権制度」 |
| 課金単位 | 年間走行距離(km)× 車両重量(t) |
| 支払方法 | デポジット(前払い)方式(ICチップ・アプリ・車検時登録) |
| 減算方式 | 実走行距離と車重に応じて自動減算 |
| 優遇措置 | 軽量車・短距離利用・地方登録車は割引 |
| 使途明確化 | 道路・橋梁・上下水道・充電インフラなどに目的税化 |
| 余剰処理 | 未使用分は翌年繰越または公共インフラ基金へ寄付選択可 |
制度の要は、計測の正確さと透明性である。
そのために、すべての自動車(EV・HV・ガソリン車を含む)に「デポジット対応スマートメーター」を義務化する。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 走行距離検知 | GPSと車軸センサーによる距離計測(1km単位精度) |
| 重量データ連携 | 車検時の登録重量を自動参照し、課税係数を設定 |
| デポジット残高管理 | 前払い額・残高・使用履歴をリアルタイムで表示 |
| ブロックチェーン認証 | 改ざん防止・地域ごとの課税透明性を担保 |
| オンライン接続 | 自治体・国交省・財務省への匿名データ送信 |
この仕組みを導入することで、「燃料課税に代わる、利用ベースの自動課税」が初めて可能になる。
さらに、税の流れ(徴収→分配→公共インフラ投資)をブロックチェーン上で可視化することで、国民が「どの道路に、どのように税金が使われているか」を把握できる社会へ。