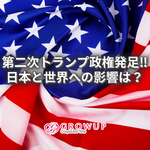Blog
相対的貧困率15.4%の嘘|統計が映さない日本の本当の貧困層

嘘には三つの嘘がある。
人を喜ばせる嘘、人をだます嘘、そして統計だ。
数字ほど人を安心させるものはない。
数字ほど人を欺くものもない。
そして、貧困というテーマほど、統計が現実から乖離しやすい分野はない。
この言葉ほど、現代日本の「貧困報道」を象徴するものはない。
しかし、その数字の根拠をたどれば、そこには「可処分所得の中央値の半分未満」という単純な線引きしか存在しない。
つまり、この数値は“実際に生活が破綻している人”の割合ではない。
貧困の定義が「所得」でしか測れない以上、統計が映すのは人間の生活の影――その輪郭だけであり、体温までは伝えない。
まず注目すべきは、富裕層の「形式的貧困化」である。
株式配当や不動産収入を申告分離課税やNISAで処理すれば、総合課税の所得は簡単にゼロ近くまで抑えられる。
資産を数億円単位で保有しながら、住民税非課税世帯として補助金や給付金を受け取ることも理論上可能だ。
その人の生活は豊かで、子どもは海外留学し、配当で暮らしている。
これが「数字の貧困」と「実態の豊かさ」が逆転する社会の現実である。
次に、家族援助・同居支援が無視されている点だ。
統計上は独居で年収200万円未満の「貧困世帯」であっても、実際には親からの送金、住宅支援、食費の援助で暮らしているケースが多い。
子供からの仕送りで豊かに暮らしている親御さんもまたしかりだ。
こうした非公式の支援は「所得」には計上されず、結果として実際よりも“貧困に見える”人々が増えてしまう。
日本社会は、表面的には個人主義が進んだように見えても、実際には家族というセーフティネットの影響力が依然として大きい。
この構造を無視した「世帯所得ベースの貧困統計」は、現実の安全網を正確に反映できていない。
そして何よりも深刻なのは、統計の外にいる人たちだ。
こうした“非正規・非申告型フリーランス”は、税の網にも、統計の網にも引っかからない。
所得の実態は誰にも分からず、彼らは「労働者」でもなければ「失業者」でもない。
統計の世界では“存在しない人”になってしまう。
だが、現実の街では確かに彼らが働き、消費し、都市の夜を支えるもう一つの経済圏を形成している。
これら三つの歪みを補正して見直せば、
実際に恒常的に生活が困難な層は
5%前後に収まる。
本当の貧困は、数字よりもずっと静かで、深く、そして個別的だ。
それは統計ではなく、物語としての生活史の中にしか見出せない。
統計は、真実を語るための道具であると同時に、真実を覆い隠すためのカーテンにもなる。
数字が語る「平均」や「中央値」の背後には、制度設計者の意図、政治的判断、そして社会の都合が潜んでいる。
私たちは、数字を信じる力ではなく、
数字を疑う勇気を持たなければならない
それこそが――
「7人に1人」という嘘を超えて、”本当の社会”を見抜くための、新しい知性のかたちである。
そして、ここで述べたこともまた、一例にすぎない。
統計が語らない真実は、多くのメディアで繰り返し報道されている。
数字の背後には、まだ誰も語っていない「現実の断片」が眠っているのだ。