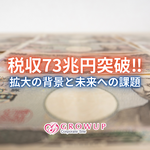Blog
お盆は地域でこんなに違う!意味・歴史・全国の習慣ガイド
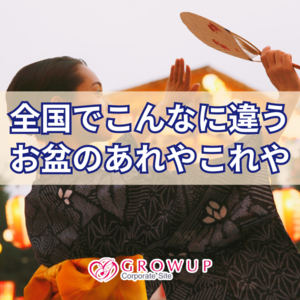
夏の風物詩ともいえる「お盆」。
帰省ラッシュや旅行、家族で過ごす時間など、全国各地でさまざまな光景が広がります。
しかし、本来のお盆の意味や地域ごとの違いについては、意外と知られていないことも多いものです。
今回は、そんな「お盆」にまつわる素朴な疑問から、地域ごとのユニークな習慣まで、「あれやこれや」とご紹介します。
ちょっとした雑学としても楽しめる内容ですので、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
お盆と聞くと現在では、長期休みと連想しがち。そもそも「お盆」とは!?

「お盆」と聞くと、多くの人が“夏の長期休暇”や“帰省ラッシュ”を思い浮かべるのではないでしょうか?
しかし、そもそもお盆とは ご先祖様の霊を迎え、供養するための日本独自の仏教行事です。
正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、仏教経典の一つ『盂蘭盆経』が起源。
亡き人の霊がこの世に戻ってくるとされる期間に、迎え火・送り火を焚き、供物を捧げて感謝と供養の気持ちを表します。
歴史的にみると、江戸・明治・大正・昭和・平成とこんなに変化してきた

お盆の形は時代と共に変化してきました。
お盆の過ごし方が、家族のかたちや社会構造を映す鏡でもあることがわかりますね。
全国のエリアを見渡すと、いろんな違いがある

日本各地で見られるお盆の風習には、意外な地域差があります。
お盆の時期が違う!?
全国の多くの地域(旧盆):8月13日〜16日
沖縄など(旧暦盆):旧暦7月15日前後(年によって変動)
迎え火・送り火の風習
京都では五山の送り火が有名ですね。
精霊馬(しょうりょううま)の文化
西日本では一般的ですが、東北などではあまり見られません。
盆踊りのバリエーション:地域と記憶をつなぐ“夏のリズム”
先祖の霊を慰めるために踊る仏教儀式が由来とされていますが、
今では地域の夏祭りやコミュニティの交流イベントとしても根付いています。
実はこの「盆踊り」、全国に目を向けると驚くほど多様なスタイルがあるのです。
北から南まで、踊りの宝庫!盆踊りの多様な魅力
北海道・江差町の「江差追分盆踊り」
日本三大民謡の一つ「江差追分」をベースにした優雅でしっとりした踊り。北国ならではの静かな情緒が漂います。
徳島の「阿波踊り」
「踊る阿呆に見る阿呆」で有名な熱気あふれる踊り。法被を着た男踊りや浴衣姿の女踊りなど、リズムもステップも躍動感たっぷりです。
岐阜の「郡上おどり」
日本一長い盆踊りで知られ、期間中は夜通し踊る“徹夜踊り”も開催。観光客も飛び入り参加可能で全国から踊り手が集います。
大阪万博で世界記録!「河内音頭」
関西で根強い人気を誇る「河内音頭」。特に大阪府八尾市で代々親しまれ、2025年大阪・関西万博関連イベントで盆踊りのギネス世界記録が樹立されました。
「音頭」「太鼓」「輪になる踊り」の熱気は、日本の夏の象徴です。
筆者のふるさと「防府踊り」:都はるみさんの曲が地域の誇り
山口県防府市の「防府音頭」は地元で親しまれるオリジナル盆踊り。昭和の大スター都はるみさんが歌唱を担当しており、「ちょるちょる やっちょる 踊っちょる」のテーマソングは防府の風土を歌い上げています。
筆者は子どもの頃、この音頭が全国区だと思っていたそう。夜には浴衣姿の子どもや地域の年配者が踊りの輪に加わり、夏の記憶がよみがえります。
盆踊りは、地域の「記憶と風景」
どの地域にも「あの曲」「あのリズム」があり、土地の風土や文化、家族や友人との思い出が刻まれています。故郷を離れても、その音頭を聞くと自然と体が動くのは、盆踊りが持つ不思議な力かもしれません。
あなたが大切にしたお盆の習慣は何ですか?

皆さんは、どんなお盆の記憶がありますか?
- 毎年祖父母の家に帰省し、仏壇に手を合わせた日々
- 兄弟で精霊馬を作っては笑い合った夏の午後
- 浴衣を着て地域の盆踊りに参加した思い出
- あるいは、都会暮らしで迎え火すら焚いたことのない夏……
時代も場所も違えど、「誰かを想う時間」であることには変わりません。
今年のお盆は、ほんの少し立ち止まって、自分にとって大切な習慣や人に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
おまけコーナー|スタッフの思い出一言コメント集
「祖母の手料理が恋しくなる季節。お盆といえば冷やしそうめんと大きなスイカでした」(Y)
「迎え火で使った“おがら”の香りは、今でも夏の原風景です」(M)
「子どもと一緒に初めて精霊馬を作った今年。受け継がれていく文化に感動しました」(T)
今年のお盆も、それぞれの“あれやこれや”を大切に。
皆さまにとって、心温まるひとときとなりますように。