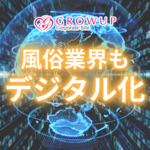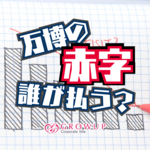Blog
給付付き税額控除とは!?過ちを繰り返すな!

2025年、日本の政治シーンでは「減税か、それとも給付か?」という議論が熱を帯びています。物価高騰や格差拡大が続く中で、国民にどう支援を届けるのが最も公平で効果的なのか――その答えのひとつとして浮上しているのが 給付付き税額控除です。
単なるバラマキでもなく、単なる減税でもない。税制の仕組みを通じて「本当に必要な人」に支援を行き渡らせようとするこの制度は、 2025年の参院選や自民党総裁選の論点にもなりつつあります。
目次
2025参院選挙、自民党総裁選挙でいわれ始めた給付付き税額控除とは!?
2025年の参議院選挙や自民党総裁選挙を前に、ニュースや討論で耳にすることが増えてきたのが 給付付き税額控除です。これは、低所得者や一定の条件に当てはまる人に対して、税額控除だけではなく実際に 給付金として支給される仕組みです。いわば、「税金が少ない人にも恩恵が届く減税+給付制度」といえます。
通常の税額控除は、そもそも支払う税金が少ない人ほど効果が薄くなります。そこで、「給付」という形を組み合わせることで、働いていても収入が少ない人や子育て世帯にもきちんと支援を行き渡らせることが狙いです。
減税と違うの?どんなメリットがあるの?
すでに税金を支払っている人の負担を軽くする仕組みです。しかし、所得が少なく、そもそもあまり税金を払っていない人には効果が限定的です。
「控除しきれなかった分を現金で給付」する仕組みのため、低所得者層にもメリットがしっかり届きます。特に、子育て世帯や非正規労働者など、社会的に支援が必要とされる層にとっては減税よりも実感しやすい制度となります。
給付までの期間や国や地方自治体のコストの比較は?
ただし、実際に給付を行うには手続きが増えるため、国や自治体にとってはコストがかかります。減税ならば、税務署や企業の源泉徴収で自動的に処理できる一方、給付金は申請・審査・振込といった事務作業が発生します。
減税のメリット
税務署や源泉徴収で自動処理が可能。迅速に支援を届けられる。
給付付き税額控除のメリット
申請・審査を通じて「本当に必要な人」に絞った支援が可能。精度が高い。
再分配の機能は減税でも、給付でも、実は同じこと
所得の再分配という観点から見れば、減税も給付も「お金の流れを通じて公平性を高める」という点で大きな違いはありません。
しかし、もっと大事なのは「対象者をどう絞り込むか」です。現在の制度では所得だけで線引きすることが多いですが、資産を多く持っている人も同じ「低所得者」として扱われるケースがあります。本当に支援が必要なのは、収入も資産も少ない人であるはずです。
ここで参考になるのが、経済学者トマ・ピケティの理論です。
ピケティは『21世紀の資本』で、資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回る限り、富は一部の資産家に集中し格差は拡大すると指摘しました。
所得だけを基準に再分配を考えると「資産格差」に対応できず、社会の分断が広がる恐れがあります。今後は「収入+資産」を基準にした仕組みが必要です。
シミュレーション例: 同じ「年収300万円世帯」でも、資産の有無で支援の必要性は大きく異なります。
| 世帯モデル | 年収 | 金融資産 | 税額控除後の課税額 | 給付額 | 実質的な生活余裕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| A世帯:資産ゼロ | 300万円 | 0円 | 10万円 | 10万円 | 生活ギリギリ、給付が実質的支援に |
| B世帯:高資産あり | 300万円 | 5000万円 | 10万円 | 10万円 | 困窮はなく、給付は「余剰」となる |
この比較から分かるように、年収だけで制度を設計すると、真に困っている層と資産を多く保有している層が同じ扱いになってしまう問題が発生します。
ピケティが指摘する「資産格差」の視点を加えることで、より公平で持続可能な再分配の仕組みが見えてくるのです。
給付付き税額控除は、減税の恩恵が届きにくい層にもしっかり支援を届けられる制度です。その設計は「所得」だけでなく「資産」も踏まえるべき段階に来ています。
社会の分断を防ぐためには、ピケティ理論が示す資産格差の是正が不可欠。行政コストや対象者の線引きといった課題もありますが、私たちも「公平で持続可能な再分配」としてどう活かすか考えていくことが大切です。