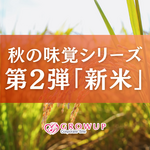Blog
電動キックボードシェア独占の真実|LUUP一強体制の裏側と制度問題

街でよく見かけるようになった「電動キックボード」。
中でもひときわ多く見かけるのが、青と白のロゴを掲げた「Luup」です。
同じ時期に多くのシェア企業が参入したはずなのに、気づけばLuup一社だけが生き残っている──。
これは単なる経営努力の結果でしょうか?
実はその裏側には、制度設計・行政運用・政治スピードが複雑に絡んだ”構造的勝利”があります。
今回はその実態を、わかりやすく解説します。
目次
なぜLuupが”勝者”なのか?
Luupは「市場で勝った」のではなく、“制度の内側で勝った”企業です。
特定小型原付区分(2023年施行)における車両要件──
「最高速度20km/h以下」「重量20kg以下」「歩道モード6km/h切替」「前後独立ブレーキ」など、これらは法改正前からLuupが採用していた仕様とほぼ一致していました。
“法律がLuup仕様に寄せられた”のです。
Luupの戦略的優位性
さらにLuupは2019年から警察庁・経産省・自治体と実証実験を進め、「法制度化のデータ提供者=政策テーブルの内側」にいました。
他社がルールを”守る側”だったのに対し、Luupはルールを”作る側”だったのです。
他社(海外勢・ベンチャー)が撤退した理由
電動キックボード市場には当初、アメリカのLimeやBird、ドイツのWind Mobilityなどが参入していました。
しかし法改正後、次々と撤退しています。
主な理由は3つです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 技術要件が厳しすぎた | 欧州規格(25km/h・25kg)では日本の基準に適合せず、再設計コストが莫大。 |
| 行政手続きが煩雑 | 自治体ごとにポート設置や保険認可が異なり、全国展開が困難。 |
| Luupが先にポートを押さえていた | 公共空間の駐輪ポートが既にLuup協定下にあり、他社が入り込めなかった。 |
ルールを作る者が市場を制す──Luupの制度独占構造、独禁法にひかかるのでは?
Luupは全国主要都市の自治体と包括協定を結び、公共空間(歩道・公園・駅前)にポートを独占的に設置しています。
形式上は「安全確保のための行政協定」ですが、実質的には公共空間を民間企業が占有している状態です。
通常、こうした市場支配は独占禁止法の「不当な取引制限」にあたる可能性がありますが、Luupの場合は”行政の協定下”にあるため、独禁法の対象外(行政独占)というグレーゾーンに位置しています。
問題は、法的にはグレーでも消費者の選択肢が失われていること。
価格競争は起きず、データも1社に集中し、サービス改善のプレッシャーが消えています。
行政は「安全確保」を名目に制度を急ぎましたが、現場レベルでは安全はむしろ悪化しています。
特定小型原付制度により、車両の構造基準は整備されました。
しかし、肝心の「運用ルール」や「安全教育」は追いついていません。
特定小型原付の事故原因の約7割が「交通ルールの未理解・誤認」。
つまり、法整備が利用者理解を追い越した結果、混乱が広がっているのです。
──それが現在の日本のモビリティ市場の姿です。
行政が果たすべき”二つの責任”
この独占構造の最大の責任は、実はLuupではなく自治体側にあります。
-
① 安全保障責任
事故防止・秩序維持(→ Luup協定で実現)
-
② 公正競争責任
複数事業者の参入機会確保(→ 現状、放棄)
地方自治法では、公共施設の利用は「平等」でなければならない(第244条)と定められています。
つまり、公道や公園を特定企業にだけ使わせるのは行政上の怠慢です。
Luupと行政の連携実態
Luupは現在、警察庁・国交省・自治体との連携協定のもとで運営されています。
| 地域 | 連携内容 |
|---|---|
| 東京都 | 官民協働モデル都市事業、電動キックボード社会実験 |
| 大阪市 | 都市再生推進法人との協定(放置車対策・観光連携) |
| 京都市 | 交通混雑地区でのポート優先設置 |
| 名古屋市 | 地方創生モデル実証(環境省助成対象) |
これらはすべて、国交省・環境省・経産省の支援スキーム内で行われています。
つまり、直接の補助金は少なくても、公的インフラ整備に便乗して成長できる仕組みを確保しています。
現状:Luupだけが占有している構造
多くの都市で、ポート(駐輪場所)は公道や公園の一角に設置されています。
これらは本来、市民全体の共有財産(公共物)です。
ところが実際には、
- 契約主体:Luupと自治体の協定のみ
- 使用条件:随意契約(公募なし)
- 期間:更新制で事実上の永続化
となっており、公有地の独占利用状態になっています。
行政は、
- 複数事業者の公募制導入
- ポート共有制度
- 協定の定期見直し
といった仕組みを整えることで、消費者の選択肢を取り戻す責任があります。
ただし、以下の疑問・説明不足の部分もあります。
- 他企業(ベンチャー・海外勢)もこの実証制度を利用可能だったはずですが、なぜLuupだけが”優先的に計画段階から関与”できたのか。
- 自治体・行政が複数事業者を検討・公募するというプロセスではなく、実質的にLuup側と”早期包括協定”を結んでいた構造。
- その選定プロセス(なぜこの企業を選んだか、他社はどう扱われたか)が透明には示されていないという点。
つまり、政策形成・制度設計の段階で “競争的な選定”よりも”先行実績を積んだ一社を使う”という選択がなされた可能性が高いのです。
まとめ:なぜ他社ではなくLuupだったのか──制度の透明性が問われている
Luupが”唯一の生き残り”となった理由には、技術力や運営ノウハウの差だけでは説明できない構造があります。
制度設計の初期段階からLuupが計画に参加していたこと、そして他社が排除されるような技術要件・行政協定が形成されたこと──
これは「偶然」ではなく「制度が特定企業に最適化された結果」と考えるのが自然です。
制度透明性の欠如が、信頼を損なう
行政は「安全性を担保するため」と説明しますが、もし特定企業だけを制度設計に入れ、他の事業者を公募・審査せずに除外したのであれば、それは公正競争原則(地方自治法第244条・独禁法第1条)に反する可能性があります。
とくに公共空間(歩道・公園・駅前など)を使うサービスであれば、誰が使い、誰が排除されるのか──
その判断は、行政の恣意ではなく公開・競争・説明責任の上に立つべきです。
自治体がポート(駐輪・充電ステーション)を借り上げ、「交通モビリティ共用インフラ」として整備。
| フェーズ | 主体 | 役割 |
|---|---|---|
| ① ポート借り上げ | 自治体 | 公道・公園・駅前スペースを整備、設置費用を公費または交付金で賄う |
| ② インフラ開発 | ディベロッパー・電力会社・通信事業者 | 給電・IoT・センサー連携などを整備 |
| ③ 運用管理 | 公設民営方式(PFI/PPP) | 民間複数社(Luup含む)に利用許可 |
| ④ サービス提供 | 各シェア事業者 | ルール統一のもとで運営(課金・保険・走行データ共有) |
その先には以下の都市構想が見えてきます。
- EV充電・Eバイク・シェアカーを統合した”次世代モビリティ拠点”
- 高齢者・観光客・通勤者がアクセスしやすい生活圏内交通の再設計
- 再生可能エネルギーによる脱炭素型都市モデル