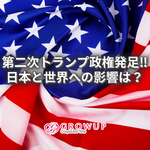Blog
2025年は日本各地で熊が出没、行政の人災では!?

目次
2025年、日本各地で熊の出没が社会問題に
これまで山奥で暮らしていたはずの熊が住宅街や通学路に現れ、時に人を襲う痛ましい事件が相次いでいます。背景には気候変動やエサ不足などの環境要因だけでなく、行政の対応遅れという“人災”の側面も指摘されています。
本記事で問い直すポイント
- なぜここまで問題が深刻化したのか?
- 行政や地域はどこまで責任を果たしているのか?
本稿では、被害事例の実情、制度や現場のすれ違い、駆除と保護の価値対立、そしてテクノロジーや地域施策による共存策まで、多角的に見つめ直します。現地の生活を第一に考える視点で、実務的な解決策を探ります。
日本各地で熊による痛ましい事件が・・・
2025年、日本各地で熊が人里に出没し、怪我や命を落とす事故が相次いでいます。
これまで山間部にとどまっていた熊が、エサ不足や環境変化によって町へ降りてくるケースが増加。人々にとって身近な「危険動物」としての存在感が急激に高まりました。
ハンター協会は、自治体の要請に答えないその理由は!
かつて熊の駆除や捕獲は地元ハンターに頼るのが常識でした。しかし現在では自治体の要請に対し、ハンター協会が積極的に応じられない状況があります。その背景には、単なる担い手不足だけではなく、制度と現場の乖離があります。
- 高齢化と人材不足:ハンター人口は高齢化が進み、危険な熊の駆除に出られる人材は年々減少。地域の要請に応じられる人員が限られています。
- 報酬体系の不公平:命がけの仕事であるにもかかわらず、自治体からの報酬は低く、危険と責任に見合っていません。
- 銃所持をめぐる“萎縮効果”:発砲許可が認められたにも関わらず、後に公安委員会が銃所持許可を取り消した事件が発生。正当な判断をしても処分される恐れから、全国のハンターに不信感が広がりました。
こうした背景のもと、ハンター協会全体が自治体の要請に二の足を踏むようになっています。根底にあるのは──
・ハンターにリスクだけを背負わせる制度設計
この構造的な不信こそが、2025年の熊出没問題を「自然災害」ではなく「人災」へと変えてしまっているのです。
2024法改正と自治体権限
過去の行政判断が生んだ深い不信
ある事件では、現場の警察が「正当な発砲」と判断し許可を出したにもかかわらず、後に公安委員会が銃所持許可を取り消しました。
命がけの行為を後になって処罰される――この出来事は全国のハンターに衝撃を与えました。
2024年の法改正
この反省から、2024年には「自治体の要請と警察承認があれば発砲可能」とする法改正が行われました。
あの事件に見られた曖昧な判断を防ぎ、住民の安全を優先できる制度が整えられたのです。
しかし不信は解けない
一度失った信頼は簡単には戻りません。
「法を守っても処分されるかもしれない」「また同じように後から責任を負わされるのでは」――
そんな不安が根強く残り、自治体の要請に二の足を踏む要因となっています。
当時の世論・マスコミの反応
事件は北海道砂川市(2018年)での発砲をめぐるものでした。
地裁は2021年に「取り消しは著しく妥当性を欠く」と違法判断しましたが、2024年10月の札幌高裁で逆転敗訴。
この経緯に現場ハンターから「これでは誰も撃てない」と萎縮と反発の声が噴出。
メディアは“発砲恐怖症”“萎縮”といった言葉で伝えました。
しかしその決定に、誰も責任を取りませんでした。
熊を駆除すると動物愛護の観点から非難の声も
動物愛護の声と人命優先の現実
「共存の道を探すべきだ」
──動物愛護の立場からは、必ずこうした声が上がります。
確かにその主張も理解できます。しかし現実には、人命を最優先にしなければならない場面があります。
この価値観の対立が、行政の判断をさらに遅らせているのです。
報道機関は、地域外での報道を自粛すべきではないでしょうか。
人里に降りてくるアーバンベア対策はあるのか?
「アーバンベア」という新しい脅威
近年では、住宅街や市街地にまで熊が出没する現象を指して「アーバンベア」という言葉まで生まれました。もはや山奥だけの問題ではなく、私たちの日常生活に直結するリスクとなっています。
考えられる主な対策
- ごみステーションの管理強化
- 人里近くの山林整備(放置竹林や果樹の処理)
- ドローンやAIを使った出没監視システム
- 学校や地域での避難訓練・啓発活動
こうした取り組みは一部自治体で試みられていますが、全国的な仕組みにはまだ十分に広がっていません。
熊と人の共存へ ― 人も熊も守るという視点
熊出没問題は“自然災害”だけではない
行政対応の遅れが被害を拡大させた“人災”でもあります。対立ではなく「熊を山に留め、人命を最優先に守る」現実的な共存策が求められています。
熊が山から下りないようにする取り組み
- 森林整備・生態系回復: 放置竹林や果樹を処理し、山のエサ資源を確保
- 人間側の予防策: ごみステーションや畑の管理を徹底し、匂いで熊を誘わない
- テクノロジーの活用: AIやドローンによる監視で早期察知・対応
基盤は「熊を人里に近づけない」仕組みづくりです。
人里に出たら速やかに駆除
現れた熊をためらえば、被害は拡大し「熊も人も守れない」結果に。迷いをなくす仕組みが必要です。
- 自治体・警察・ハンターの即応体制
- 発砲ルールの明確化と後追い処分の禁止
- 地域住民への迅速な避難・警報システム
熊も人も守るという考え方
無条件な駆除ではなく、「山で生きられる環境を守る」+「人里に出た個体は速やかに処理」という二段構え。これこそが熊の種全体と人命を守る現実的な共存策です。
判断の主体は誰か
熊と隣り合わせで暮らすのは現地住民です。
都市部からの抽象的な「動物愛護」論ではなく、日常の命と生活を守る視点を最優先に置く必要があります。