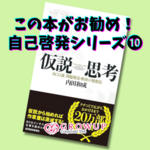Blog
評価に納得できず転職を考えるとき、まず知っておきたいこと|相対評価と自己認識のズレとは?

目次
「なんでこんな評価なんだ?」— そのモヤモヤの正体
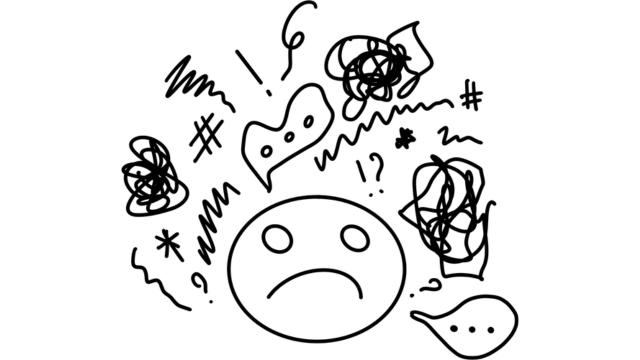
「頑張って成果を出したのに、なぜ評価されなかったのか?」
「同僚よりも仕事をこなしていたのに、なぜ自分の方が低評価なのか?」
そんな悔しい思いを抱え、前職を離れた方も多いでしょう。
人事評価には「相対評価」と「絶対評価」という2つの基準があり、それが原因で不公平に感じることが多々あります。
本記事では、その違いを解説し、納得感のある評価を受けるための考え方を共有します。
相対評価と絶対評価—— あなたの評価はどっちだった?

相対評価とは、周囲との比較で評価が決まる方法です。
例えば、営業部門では売上成績をランキングし、上位○%を高評価とすることが一般的です。
一方、絶対評価は、個人の達成度を基準とする評価です。
目標として設定されたKPIや成果物のクオリティを元に評価されます。
例を挙げましょう。
相対評価の場合:どれだけ頑張っても、他の人がより良い成果を出せば、あなたの評価は下がります。
絶対評価の場合:事前に設定された基準を達成できれば評価は上がります。周囲の成績は関係ありません。
あなたが前職で感じた理不尽な評価は、この相対評価の仕組みによるものかもしれません。
部下の不満と上司の評価基準のズレ

上司は、部下の「役割」を基準に評価しがちです。
「この仕事を遂行するのがこのポジションなのだから、これくらいは当然」という考え方です。
しかし、部下の立場では「自分がどれだけ頑張ったか」を評価してほしいもの。
このギャップが、評価に対する不満を生み出します。
「こんなに頑張ったのに、なぜ評価されないのか?」—— その疑問は、上司とあなたの評価基準のズレが原因かもしれません。
同僚評価や360度評価の落とし穴

「公平な評価制度」として導入されることが増えている同僚評価や360度評価。
しかし、これらも完璧なものではありません。
同僚評価の問題点:人間関係の影響を受けやすく、好き嫌いが評価に影響を及ぼすことも。
360度評価の問題点:多角的な評価が得られるものの、評価者自身の評価能力にばらつきがあり、必ずしも正しいとは限りません。
これらの評価制度も、人間関係や組織文化の影響を受けることを理解しておく必要があります。
納得感のある評価を受けるために——自己評価の重要性

会社の評価に不満を感じる人ほど、「自分のビジョン」と「評価基準のズレ」を認識することが大切です。
・自分が目指すキャリアの方向性を明確にする
・そのために必要なスキルや経験を洗い出す
・実際の業務を振り返り、目標とのズレを認識する
これができれば、会社の評価に振り回されず、自分自身の成長を正しく評価できるようになります。
まとめ
「なぜ自分は正当に評価されなかったのか?」—— そう感じたことがあるなら、相対評価と絶対評価の違いを理解することが第一歩です。
そして、会社の評価基準と自分の価値観のズレを見つめ直し、自己評価の精度を高めることで、納得感のあるキャリアを歩むことができるでしょう。