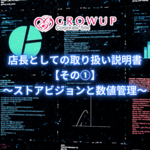Blog
構造化する“人”の力は未来の経営を支えるか? ― 複雑な時代に価値を生み出す“構造人材”の正体 ―
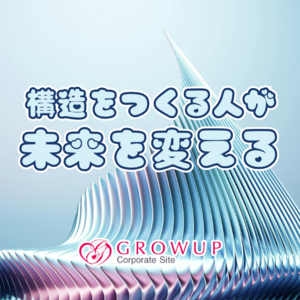
目次
はじめに|「属人的な力」から「構造化する力」へ

かつて「優秀さ」とは、経験・知識・判断力など、“個人の属人的な能力”によって測られていました。けれども今、求められる人材像は明らかに変化しています。
とくに不確実性が高く、変化のスピードが早い現代においては、「知見や成功体験を再現可能な“仕組み”に変換する力」=“構造化する力”が、組織の持続的成長を支える源泉となっています。
構造化する人とは?

“構造化する人”とは、「価値の再現性を生み出せる人材」です。
以下のような力を持ち、属人化からの脱却と仕組み化をリードできる存在です。
・抽象と具体を行き来し、本質を捉える
課題の核心を見極め、意味ある行動に落とし込める
・一度きりの成功を“型化”できる
成功の再現性を高め、ナレッジを共有可能な形式へ変換
・組織やプロジェクトの構造を設計できる
役割・目的・情報の流れ・意思決定の仕組みを意図的にデザイン
・属人的な業務を“仕組み”で回せるようにする
「できる人がやる」状態から、「誰でも再現できる構造」へ
なぜ今、“構造化する人”が求められるのか?

1. 変化が速すぎて、マニュアルがすぐに陳腐化する
→ 環境に応じて“型”を柔軟にアップデートできる人材が必要
2. 情報や業務が“複雑化・多様化”している
→ 複雑な情報を整理し、構造として可視化・共有できるスキルが求められている
3. 組織が“共創型”にシフトしている
→ 「一人で成果を出す」よりも「チームの再現モデルをつくる」人材が重要
構造化する力が活きる4つの実践場面
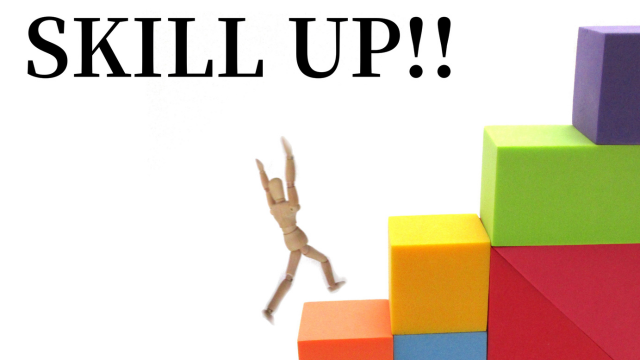
① プロジェクト設計
ゴール、役割分担、進捗管理、意思決定ルールを体系化し、プロジェクトの“骨組み”をつくる。
② ナレッジマネジメント
成功・失敗のプロセスを言語化・整理し、誰でも使える形で蓄積・共有する。
③ 育成とOJT
個人のノウハウを“教えられる形”に変換し、他者に伝承できる状態にする。
④ 新規事業・仕組みづくり
カオスな立ち上げ期において、必要な要素を構造的に組み立てる。
「構造人材」を育てるためのポイント

環境設計
「やり方を教える」のではなく、「仕組みを考える機会を与える」こと。
設計タスクの経験が、構造的思考を鍛える。
評価軸の見直し
成果そのものよりも、「仕組みにどう貢献したか」を評価対象に含める。
再現性と持続性を評価する視点が必要。
言語化・図解の訓練
フレームワークや図式を活用し、「見えない構造」を言語化・視覚化するトレーニング機会を設ける。
結論|構造化する人が未来の経営を支える

人的資本経営とは、単に“優秀な個人”を集めることでは成り立ちません。
本当に必要なのは、再現性 × 自律性 × 共創性 を構造化できる人材です。
属人的な力ではなく、誰もが活用できる価値を生み出せる仕組み。
それをデザインできる人が、未来の経営の中核を担う存在となっていくのです。
次回予告|“人的資本”を組織戦略に落とし込む方法
次回は、「人的資本をどう経営と連動させるか?」をテーマに、実務レベルでの組織戦略設計について掘り下げていきます。
たとえば──
・人的資本レポートを経営にどう活かす?
・スキル構造と事業構造の接続とは?
人事部門だけでなく、現場リーダーや経営層にも役立つ視点をお届けする予定です。