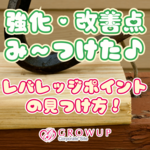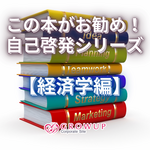Blog
歴史に学ぶリーダーシップ【第15回】渋沢栄一

本シリーズ「歴史に学ぶリーダーシップ(日本ver)」では、日本史に名を残すリーダーたちの人生・思想・行動を振り返りながら、現代のビジネスや組織運営に活かせる教訓を探っています。
前回の立見尚文編に続き、今回第15回では、「日本の資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一(しぶさわ えいいち)を取り上げます。
1万円札の新しい顔としても話題になった渋沢栄一――彼の功績やリーダーシップを紐解くことで、現代にも通じる経営・組織運営の要諦を学んでいきましょう。
目次
渋沢栄一とは?――“日本資本主義の父”の誕生
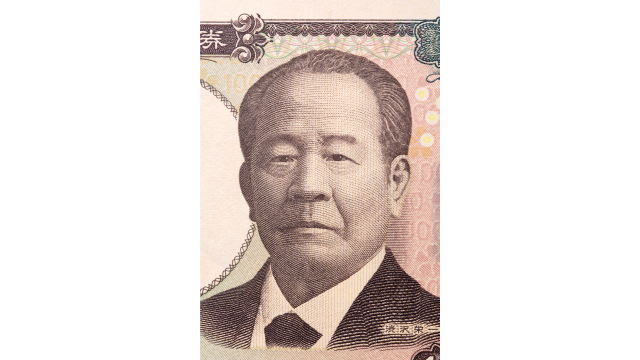
1. 農村出身から幕臣、そして明治政府へ
深谷の豪農の家に生まれる
渋沢栄一(1840年~1931年)は、武蔵国血洗島(現在の埼玉県深谷市)で農家の長男として生まれました。
幼少期から算術や経営感覚に秀で、若くして父の商売を手伝う一方、儒学や兵学を学びながら意欲的に頭角を現していきます。
幕末動乱期を駆け抜ける
幕末の動乱期、栄一は尊王攘夷の志士として活動しますが、一転して一橋慶喜(のちの徳川慶喜)に仕える立場となり、パリ万博への渡欧にも同行。
のちに明治政府で大蔵官僚として働くという、多彩なキャリアを積み重ねました。
2. 実業界への転身と数多の企業創設
官吏から実業家への転身
明治政府での官僚経験を経て、栄一は「国の富強には民間の経済発展が不可欠」との信念から、官を辞して実業界に飛び込みます。
約500の企業創立に関与
第一国立銀行(現・みずほ銀行の前身)や東京瓦斯(東京ガス)、東京株式取引所(東京証券取引所)など、500近くの企業・銀行・団体の設立や運営に関わり、「日本資本主義の父」と称される偉業を成し遂げました。
渋沢栄一の理念――“道徳経済合一説”とは?

1. 利益だけでなく“道徳”を重視
儒教的モラルとビジネスの融合
渋沢栄一は「道徳と経済は本来相反するものではなく、両立すべきである」という“道徳経済合一説”を唱えました。
正直・誠実・勤勉といったモラルを企業活動の根底に据え、単なる利潤追求でなく、社会の発展と調和を目指す姿勢を強調したのです。
“士魂商才”という在り方
自らの経営観を「士の魂(士魂)と商人の才覚(商才)の融合」と表現し、近代日本の資本主義は、武士道的な誠実さと責任感をビジネスに持ち込むことで健全に発展できる、と説きました。
2. 合本主義と社会貢献
“合本主義”による共同経営
渋沢栄一は株式会社制度を活かした“合本主義”を推進。
多くの人から資金を募り、共同で事業を進めることでリスクを分散し、広く国民に恩恵が及ぶ体制を構築しました。
公益と事業の両立
企業経営だけでなく、教育・福祉・医療などの公益事業、さらには慈善団体の設立や支援にも力を注ぎました。
こうした“経済活動と社会貢献の一体化”は、現代のCSR(企業の社会的責任)に通じる先進的な思想と言えます。
渋沢栄一のリーダーシップのポイント

ビジョンと実行力の両立
幕末から明治への大転換期において、具体的な企業・組織を次々と創設・運営した行動力は突出しています。
大きな理想(ビジョン)を掲げるだけでなく、それを形にする実行力を伴わせることがリーダーに求められる、という好例です。
多様なネットワークを築き上げる力
幕府や明治政府の官僚経験から得た人脈、欧州への渡航時に得た国際感覚など、多彩な人々とのネットワークをフル活用して事業を進めました。
現代のリーダーも、組織の垣根を越えたコラボレーションや利害調整において、広い人脈と交渉力が必須であることを学べます。
公正な財務と透明性
第一国立銀行をはじめ、銀行制度・金融制度の確立に大きく関わった栄一は、“資金の流れを公明正大に運営する”ことを何よりも重視しました。
組織においても、財務の健全性や透明性を担保する体制こそが、ステークホルダーからの信頼を得る土台となります。
“社会を良くする”理念とビジネスの融合
“道徳経済合一説”は、利益追求と社会貢献の両立を明確に唱えた先駆的な考え方です。
現代でもSDGsやESG投資など、企業には社会的責任が問われる時代。
栄一のように、経済活動と公共の利益が一致するビジネスモデルを追求するリーダーが注目されています。
現代に活かす“渋沢式”マネジメント

道徳と経済の両立――CSR・ESGの先駆者
渋沢栄一が掲げた「士魂商才」や「道徳経済合一説」は、企業の社会的責任や持続可能性が叫ばれる今こそ、再評価すべき考え方といえます。
利益を生むだけでなく、社会・環境への貢献を同時に考えるマネジメントは、長期的な企業価値向上に直結します。
多分野への挑戦とリスク管理
栄一は数多くの銀行・保険・鉄道・製造・貿易会社など、さまざまな業種に関わりました。
その際、合本主義による資本分散でリスクを最小化しながら新産業を育成。
一極集中ではなく、分散投資・複数事業の展開でリスクとリターンのバランスをとる考え方は、企業戦略にも活きるでしょう。
人的ネットワークとリーダーの役割
政財界を横断する人脈を生かし、同士を募りながら事業を起こし、公共事業にも参画するスタイルは、まさに“巻き込むリーダーシップ”の見本。
組織やプロジェクトで「多様なステークホルダーを巻き込みながら成果を創出できるリーダー」は時代に求められています。
柔軟性と持続性を両立する経営哲学
経済環境の変化に応じ、事業形態や経営方針を柔軟に変えつつも、常に「社会に役立つ」「道徳にかなう」という基軸を失わなかった点が栄一の強みでした。
現代のグローバル化・デジタル化の時代でも、この“変化対応力+不変の軸”はリーダーにとって欠かせない要素です。
まとめ
渋沢栄一は、幕末から明治・大正期にかけて、日本の経済・産業を牽引した“実業家の祖”とも呼ばれる人物です。
武士道的な誠実さと商人の才覚を融合させた「士魂商才」
利潤追求と社会貢献を両立させる「道徳経済合一説」
複数の企業設立や銀行制度の確立、教育・福祉への尽力
広大なネットワークと行動力で数多くのプロジェクトを成功へ導くリーダーシップ
これらは、企業の持続的成長や社会課題の解決が切り離せなくなった現在のビジネス環境において、改めて学ぶべき教訓と言えます。
“世の中を良くする”という高い志と、実務的な経営手法を両立させる――
渋沢栄一が長きにわたり貫いた姿勢は、あらゆるリーダーにとって時代を超えたインスピレーションを与えてくれるはずです。
次回以降も、歴史に学ぶリーダーシップのエッセンスをシリーズを通じて探り続けます。
どうぞお楽しみに!