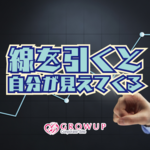Blog
AIエージェントで業務改善をする手順について

人手不足やコスト削減、働き方改革への対応が求められる今、AIエージェントの活用は大きな鍵となります。
しかし、「何から始めればよいかわからない」という声も多く聞かれます。
本記事では、AIエージェントを活用して業務改善を進めるための基本的な手順を、現場目線で分かりやすく解説します。
目次
AIエージェントで、どうやって業務改善するのか?
AIエージェントとは、単なるチャットボットや自動化ツールではなく、「人の代わりに業務をこなす知的労働のパートナー」です。
業務改善の第一歩は、「AIに任せられる業務」を正しく見極め、AIと人が最適に役割分担できる状態をつくることです。
そのためには、まず 業務の可視化と分解 が必要です。
業務フローやオペレーションの洗い出しから始めよう
現場で行われている業務を、一つひとつ丁寧に書き出してみましょう。
ToDoリストではなく、「業務の流れ」や「各工程の意思決定・判断基準」までを含めた プロセスマップ を作成することがポイントです。
これにより、どこにボトルネックがあるのか、どこが自動化に適しているかが見えてきます。
| 項目 | 記入例 | 補足 |
|---|---|---|
| 業務名 | 顧客からの問い合わせ対応 | 業務単位で記載(例:請求処理、日報作成など) |
| 実施頻度 | 毎日(10〜15件) | 数が多いものほど自動化メリットが大きい |
| 実施者 | 主に事務スタッフ(2名) | 誰が担当しているか(属人化の有無) |
| 所要時間 | 1件あたり約10分 | 合計の工数を算出しやすくなる |
| 使用ツール | メール/Excel/社内チャット | 利用中ツールと手動かどうか |
| 手順(概要) | ①メール確認 → ②内容を確認 → ③回答テンプレ作成 → ④送信 | ステップごとに分解する |
| 判断が必要か | 一部あり(対応の優先順位) | AIに任せられるかの判断基準になる |
| トラブル頻度 | 月1〜2件(送信ミスや重複対応) | エラーが多い箇所は改善余地あり |
| ナレッジ有無 | 回答テンプレはあるが個人フォルダに保存 | 共通化・整備の余地を探る |
人の手順はその人の思考プロセスも分解すること
「Aさんじゃないとできない仕事」には、必ず 思考や判断のクセ・基準 が潜んでいます。
単なる手順ではなく、どう考えてその判断に至ったか という「暗黙知」を言語化し、AIが再現できるように整理することが重要です。
ここを疎かにすると、「AIがうまく動かない」原因になります。
ある店舗では、「クレームの初動対応」は店長だけが行っており、アルバイトや新人スタッフは判断できない状態でした。
店長の対応はマニュアル化されていなかったため、AI化するには「どのクレームにどの対応を選ぶか」の思考パターンの見える化が必要でした。
- 判断基準1:相手が感情的か理性的か
- 判断基準2:事実誤認か、要求が妥当か
- 対応パターン:謝罪+説明/謝罪+代替案提示/責任者引き継ぎ など
この思考プロセスをフロー図とQ&A形式で整理し、AIチャットボットに組み込むことで、新人でも適切な対応方針を瞬時に選べるようになりました。
このように、「やり方」だけでなく「考え方」までAIに伝えることで、再現性のある仕組みが構築できます。
労働リソースが多い、反復され、何度繰り返されるポイントを見つけよう
AIエージェントは、繰り返し・定型的な業務に強みを発揮します。
特に、次のような業務は自動化の優先順位が高い領域です:
- 問い合わせ対応
- データ入力・転記作業
- 定型レポート作成
- 日次や週次のルーティン業務 など
事例:予約受付の自動化
ある美容サロンでは、電話での予約対応に1日あたり2〜3時間のスタッフ工数がかかっていました。
予約内容はパターンが決まっており、質問も「空き時間は?」「担当者の変更は可能?」など定型的なものが多く、AIエージェントによるチャット対応を導入。
その結果:
- 予約受付の80%以上がAIで完結
- スタッフの手間が月40時間以上削減
- ミスやダブルブッキングもゼロに
これにより、スタッフは接客やサービス品質向上など
本来の価値を生む業務に集中できるようになりました。
このように、「よくある質問」「単純な入力」「繰り返しの確認作業」などは、AIに置き換えることで大幅な時短と品質向上が見込めます。
属人性があり、取得に時間がかかるものをナレッジ化しよう
業務の中には、「教えるのが難しい」「引き継ぎに時間がかかる」といった 属人化 した領域があります。
これらをAIに学習させるためには、まず人の頭の中のノウハウを
形式知化(ナレッジ化)する必要があります。
動画、FAQ、業務マニュアル、Q&A集などを整備し、AIが参照できる情報源を育てましょう。
事例:新人教育のマニュアル動画+Q&A自動応答化
ある営業チームでは、「ベテラン社員による新人育成」が完全に属人化しており、教える人によって内容にばらつきが出ていました。
そこで、トップセールスの商談ロールプレイ動画+AIナレッジベースを作成し、次の施策を導入しました:
ナレッジ構築
- 商談トーク例・想定Q&A・競合比較表を整理
- 動画・文書・FAQを一元化してAIに読み込ませる
活用フェーズ
- 新人が疑問をAIに即質問できるチャットボットを導入
- 商談トレーニングでAIが想定質問を出すシミュレーション機能を提供
- 立ち上がり期間が従来の半分に短縮
アップデートフェーズ(改善ループ)
- 「この質問はAIが誤答した」「新しい競合製品情報を追加してほしい」など現場からフィードバックを収集
- 月次でAIナレッジを更新・再学習し、常に最新情報にブラッシュアップ
- 改訂履歴を管理し、ナレッジの陳腐化防止サイクルを構築
ポイント
ナレッジは「作って終わり」ではなく、現場の声を吸い上げてアップデートし続けることで進化します。
AIエージェントを「使われるだけの存在」から「成長するパートナー」に育てるためにも、
- 定期的なフィードバック会議
- ナレッジ更新の担当者(オーナー)設置
成長する構造を作り出すことが求められる
AIエージェント導入のゴールは「置き換え」ではなく、「進化する仕組みの構築」にあります。
ナレッジを与えられたAIが、現場のフィードバックによって日々アップデートされ、精度と応用力を高めていく構造が求められます。
「AIが仕事をする → フィードバック → 改善 → 再学習」という 成長サイクル を組み込むことが、真の業務改善につながります。
社内でPDCAを回せる仕組みや、AIエージェントの 「育成担当者」 を置くことで、日々進化する業務体制が構築されます。
たとえば、営業ナレッジを動画やQ&AでAIに学習させただけでは、いずれ 内容が古くなり、現場にフィットしなくなる という課題に直面します。
解決策:「自己成長ループ」の導入
現場の フィードバック → ナレッジ更新 → 再学習 というサイクルを設けたことで、次の効果が得られました:
- 時代や商品に合わせて 常に情報が進化
- 利用者の声が反映され、納得度の高いAI支援を実現
- 教える人が変わっても 質が落ちない
| 項目 | 従来の自動化 | 一般的なDX | AIエージェント活用による進化型DX |
|---|---|---|---|
| 対象 | 単純作業・定型処理 | 業務プロセスの可視化・効率化 | 思考や判断・学習を伴う知的業務 |
| 運用 | 一度作れば終わり | システムは変えるが人は変わらない | 人とAIが共に学び、変化に適応し続ける |
| 成果 | 作業スピード向上 | 業務全体の最適化 | 組織知の蓄積と人材育成効果を同時実現 |
| 本質 | 業務の“省力化” | プロセスの“再構成” | “進化する仕組み”の構築と内製化文化 |
ポイント
成長するAIエージェントとは、
- 知識を蓄積するだけでなく、
- 現場で活用され、
- フィードバックで改善され、
- 再び現場に戻ってくる
これが 共進化サイクル(Co-Evolution Loop) を備えた存在です。
これにより、業務改善が「単なる効率化」から「組織学習と成長のドライバー」へと進化します。
おわりに
AIエージェント導入は「テクノロジーの導入」ではなく、「組織と人の働き方を変えるプロジェクト」です。
最初から完璧を目指さず、小さく始めて、試して、学んで育てていくことが成功のカギです。
これからも当社では、現場に根ざしたAI活用を推進してまいります。