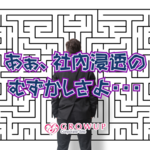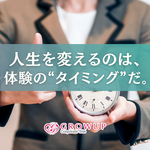Blog
【最新版】マーケティングXとは?コトラーのマーケティング3.0〜5.0進化解説

マーケティングという言葉は、私たちの仕事や日常にあまりにも自然に溶け込んでいますが、その定義は決して普遍的なものではありません。
むしろ、社会構造やテクノロジー、そして人間の価値観の変化に応じて、その意味を柔軟に変容させてきた概念です。
中でも、現代マーケティングの体系化に大きな貢献を果たしてきたのが、フィリップ・コトラーです。
彼は「マーケティング3.0」「4.0」「5.0」といった進化モデルを通して、マーケティングが「モノを売る技術」から「人間理解と共創のプロセス」へと脱皮していく軌跡を明確に描き出しました。
そして今、私たちはその延長線上に、“マーケティングX”という新たな可能性を見出しつつあります。
本稿では、コトラーの理論的枠組みをたどりながら、マーケティングの定義がどのように変化してきたのか、そしてこれからのマーケティングがどこへ向かおうとしているのかを、私たちの実務的視点とあわせて考察していきます。
目次
マーケティングの定義は、時代ごとに進化・パラダイムシフトしてきた

マーケティングは静的な手法ではなく、社会構造やテクノロジーの進展とともに動的に進化する概念です。
その定義は、産業社会から情報社会、そして感性・意味の時代へと進む中で、幾度もパラダイムシフトを経験してきました。
| 年代 | 定義 | 時代背景・補足 |
|---|---|---|
| 1935年 | マーケティングとは、商品やサービスが生産者から消費者へ流通する経済的活動である。 |
物流・販売主導の時代 モノを“どう流すか”が中心 フォード型大量生産・大量販売 |
| 1960年 | マーケティングとは、製品やサービスの流れを計画し、価格を設定し、プロモーションや流通を通じて個人および組織の目標を満たすプロセスである。 |
4P(Product, Price, Place, Promotion)登場 計画と管理の視点が導入され、マネジメントの一環へ |
| 1985年 | マーケティングとは、ターゲット市場における顧客のニーズを満たすために、製品、価格、プロモーション、流通を通じて交換を実現するプロセスである。 |
STP(Segmentation, Targeting, Positioning)の時代 交換価値(Exchange Value)に焦点 顧客志向が強調されはじめる |
| 2004年 | マーケティングとは、顧客との関係性を創造し、維持し、強化するための組織機能および一連のプロセスである。 |
関係性マーケティング(Relationship Marketing) CRMやLTV重視へ 企業と顧客の継続的関係の重要性が前面に |
| 2007年 | マーケティングとは、顧客、クライアント、パートナー、社会全体に対して価値を創造・伝達・提供・交換する活動であり、それらの関係性を管理するプロセスである。 |
ステークホルダー全体を含む定義へ拡張 CSR、社会的責任との結合 マーケティングの社会的役割が強調される |
| 2020年 | マーケティングとは、顧客、クライアント、パートナー、そして社会全体にとって価値ある提案を、創造し、伝達し、提供し、交換するための活動・組織・プロセスの総体である。 |
一方的な提供ではなく、価値の交換と共創を志向 活動(activity)、組織体(institutions)、プロセス(processes)の3階層で構成 |
フィリップ・コトラーは、マーケティングを「価値創造と交換のマネジメント」と定義した上で、環境変化に適応するかたちでマーケティング3.0・4.0・5.0を体系化しました。
この体系は、マーケティングの対象が「製品→消費者→人間」へと変化し、価値の中身が機能的価値から意味的価値へと深化していった過程を理論的に捉えたものです。
ものを売る活動から顧客やステークホルダーとの関係性を重視

従来のマーケティングは、製品やサービスの販売促進に重点を置いた「取引志向型マーケティング」が主流でした。
しかし21世紀以降は、顧客の自律性・情報接触機会の増加に伴い、企業と顧客の関係性は「一方通行」から「双方向・循環型」へと変化しました。
この流れを受けて、マーケティングの主眼は単なる販売から、顧客やステークホルダーとの関係性(Relationship)と共創(Co-creation)に移行しています。
顧客はもはや受け身の存在ではなく、ブランド構築・価値形成に能動的に関与するパートナーとして位置づけられつつあります。
この変化は、サービス・ドミナント・ロジック(S-D Logic)やナラティブマーケティングの台頭にも通底しており、マーケティングが意味生成と経験設計を伴う社会的機能へと変容していることを示しています。
コトラーは近年、テクノロジーの進化とともにマーケティング3.0・4.0・5.0を立て続けに発表

フィリップ・コトラーは、2007年以降、現代のマーケティング環境の劇的な変化に対応するために以下の三段階の理論的進化を発表しました。
| フェーズ | 中核的定義 | 顧客の捉え方 | 主なキーワード |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 人間中心のマーケティング | 価値観をもつ全人的存在 | ミッション・共感・CSR |
| 4.0 | オン・オフ統合の接続型マーケティング | デジタルでつながる共同体の一員 | SNS・カスタマージャーニー・共感拡散 |
| 5.0 | テクノロジー×人間性の融合 | 感情・目的をもつ主体的存在 | AI・ビッグデータ・倫理・パーソナライゼーション |
マーケティング3.0とは、企業が消費者を“単なる購買者”ではなく、“価値観を共有する全人的な存在”として捉え、文化・価値・精神性に訴えるマーケティングである。
「人々は、物を買うだけでなく、意味を買う。」
— Philip Kotler
マーケティング4.0とは、オンラインとオフラインを統合し、デジタル時代における顧客の購買行動を理解・支援するマーケティング。
(出典:『マーケティング4.0』2017年 コトラーほか)
マーケティング5.0とは、AIやデータテクノロジーを活用して、人間の価値観や感情に寄り添ったマーケティングを実現すること。
(出典:『マーケティング5.0』2021年 コトラーほか)
この進化は、社会的価値志向 → デジタル接続性 → テクノロジー主導の人間理解という構造的な連続性を持っています。
コトラーの提唱する5.0は、AIやIoTなどの先端技術を活用しながら、あくまで人間中心の価値創造を指向している点が特徴です。
マーケティングXは個人と企業の共創的進化を構築すること
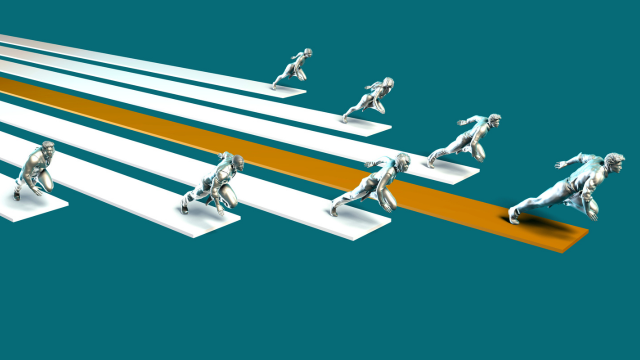
マーケティング5.0が「テクノロジーによる人間理解と最適化」を志向したのに対し、マーケティングXはその先の構造的可能性を見据えたアプローチです。
マーケティングXとは、個人が自らの体験・感情・価値観を通じて自己理解を深め、企業とともに価値共創と進化を行う双方向適応のシステムである。
この概念では、顧客は単なる“受け手”ではなく、「知的進化エージェント」として自らの感情ログ・体験ナラティブを記録し、意味を構築しながら企業と交わる存在です。
マーケティングXは、以下のような理論的背景と接続しています。
個人と組織が相互に変化し続ける関係性
意味・感情・記憶の連関
個人が自らのデータを管理・活用する権利
このようにマーケティングXは、マーケティングを経済活動における知的・感情的進化の共創インフラへと昇華させる概念であり、経営・経済・倫理・心理・AIといった複数の学問領域を横断する次世代マーケティング理論といえるでしょう。
| フェーズ | キーワード | 顧客理解の焦点 | 技術活用 | PDRMとの関係 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 価値観・精神性・共感 | 人間としての全体理解 | 弱い | PDRMはこの先の発展形 |
| 4.0 | オンラインとオフラインの統合 | デジタル接点での顧客理解 | SNS・モバイル | 部分的に重なる(データ収集手段) |
| 5.0 | AI・テクノロジーによる人間中心設計 | 高度なパーソナライズと予測 | AI・IoT・ビッグデータ | もっとも近い。ただし限界あり |
| マーケティングXPDRM | 感情・ナラティブ・共進化UX | 顧客による自己理解と共進化 | AI・対話・体験ログ | 5.0の先を目指す「共進化マーケティング」 |
おわりに|わたしたちの挑戦

私たちも今まさに、マーケティングXの実装現場に立っています。
一人ひとりの体験や感情ログを起点に、企業と顧客が共に進化していく。
そんなマーケティングの未来を、一緒につくっていきたいと思っています。
本質的な違い:マーケティングの「主語」が変わる
従来のマーケティング(コトラーを含む)は、「企業がどのように顧客に価値を届けるか」を中心に設計された 企業主語の理論 でした。
一方、PDRMはこの主語を反転させます。
「個人が、自分自身を理解し、進化させるプロセスの中で、企業との関係を選び、活用する」
―― 顧客主語のマーケティング
顧客は、自らの感情・体験・履歴をもとに意思決定を組み立てます。
企業はそのプロセスに、「伴走者」として参加する――。
そこに初めて、共進化UXという新しい経済圏が立ち上がります。
ここで生まれる構造は、単なる「顧客中心」ではありません。
それは、個人が“経済活動の設計主体”になるという構造であり、
顧客が中核となる「インフラ設計」の視点
これからのマーケティングは、企業が個人を導くのではなく、個人とともに進化するものへと変わっていきます。
「誰に届けるか」ではなく、「誰と未来をつくるか」を問い直す時代が、すでに始まっているのです。