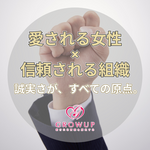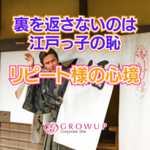Blog
構造化する“人”の力(第5回)“感情デザイン”としての経営
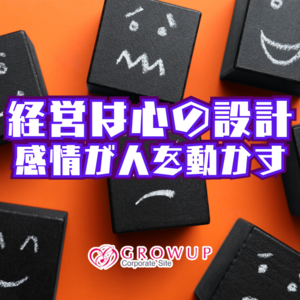
目次
「感情」は、人の行動を決める“見えないインフラ”

ビジョンを掲げ、仕組みを整え、評価制度まで整備しても──
それでも人が動かない組織があります。
一方で、制度はゆるくても、自律的に動き続ける組織もある。
その差を生むのが、“感情の設計”です。
人は論理ではなく、「感情」によって動きます。
ただし、それは単なる直感や一時的な気分ではありません。
過去の体験を通して蓄積された“感情の履歴”──
それこそが、その人の行動や選択を形づくっていくのです。
感情は“構造”として設計できる
感情を「気まぐれなもの」や「個人差のあるもの」として片づけるのは、もう古い考え方です。
いまの経営には、感情も“設計の対象”であるという視点が欠かせません。
感情は、偶然に生まれるのではなく、体験の積み重ねによって必然的に形づくられていきます。
たとえば──
- ▪ フィードバックの受け取り方
- ▪ 会議での扱われ方
- ▪ チャットでのひとこと
- ▪ 評価のときの表情や声のトーン
こうした日々の何気ない瞬間が、組織の“感情設計”をかたちづくっているのです。
それらが積み重なり、信頼・安心・やる気・誇りといった感情の“資本”となって、人の行動を支える“見えないインフラ”になっていきます。
感情アルゴリズムという発想

私はこの構造をかたちにするために、「体験ごとの感情蓄積によってレコメンドを変化させるシステム」の特許を取得しました。
これは、単なる行動データだけでなく、そのときにどんな感情が生まれたのかまで記録・活用する技術です。
なぜなら、同じ行動でも──
「楽しかった」「怖かった」「バカにされた」など、そのときの感情が違えば、次にとる行動や選択はまったく異なるからです。
この発想は、ビジネスや組織運営にも応用できます。
考えるべきポイント
- どんな体験が「やる気」や「安心」につながっているか?
- 誰が、どんな言葉で、どんな関わり方をしたときに、感情が動いたか?
- 感情の履歴をどう設計すれば、人は前向きな行動をとるのか?
こうした問いに向き合いながら、“感情の履歴”を設計していくこと──
それが、新しい人的資本経営への入り口になっていきます。
感情を軽視する組織は、選択の質を下げる

人は、まず感情で判断し、あとからその判断を論理で正当化するものです。
つまり、「感情こそが、選択の起点」なのです。
そんな感情を置き去りにした経営は、人の選択肢を狭め、
エンゲージメントを静かに奪っていきます。
人的資本とは、単なるスキルや知識だけでなく、“感情ごと投資されている時間とエネルギー”でもあります。
その感情がすり減り、奪われたとき──
どれだけ優秀に見える人材でも、“働いているようで、働いていない”状態に陥ってしまいます。
経営とは、感情の流れを設計することである
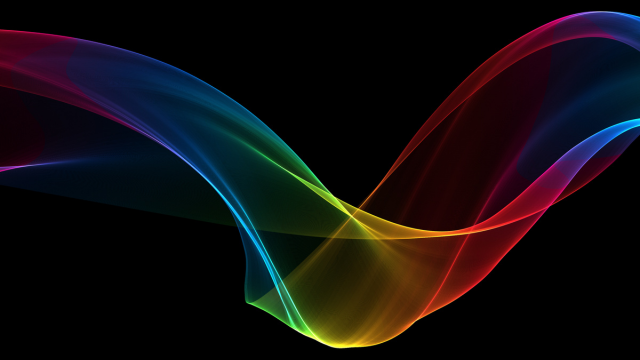
未来に期待できる。
今に安心できる。
過去に誇りを持てる。
この3つの感情がつながるとき、人は初めて──
「今ここで本気を出そう」と思えるようになります。
それを支えるのは、制度や戦略だけではありません。
日常の言葉、習慣、ふるまい、関係性といった“感情の構造”です。
経営とは、人の選択と行動を支える「感情のインフラ」を設計すること。
それこそが、感情デザインとしての人的資本経営なのです。
次回予告
次回はさらに内面に踏み込み、人が自らを「見つめ、修正し、選びなおす力」──
メタ認知をキーワードに、人を育てる組織設計を考えます。