Blog
日本経済の30年は「失われた」のか?デフレでもインフレでもない「同じ価値経済」という新しい豊かさ
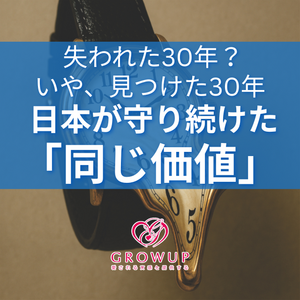
高市早苗新総裁が掲げる経済政策の柱は、「物価安定と賃金上昇の両立」。急激な成長よりも、持続的で安心できる生活を重視する姿勢が明確です。
この方針は、単なる景気対策にとどまらず——長年デフレと向き合い、インフレにも慎重に対応してきた日本の歩みの延長線上にあります。
バブル崩壊から30年。日本は世界のどの国よりも「安定」を守り抜いてきました。デフレでもインフレでもない「同じ価値」を保ち続けたこの30年こそ、「失われた」ではなく、「見つけた」時代だったのかもしれません。
目次
デフレーションとインフレーションとは
物価が下がり続ける現象
お金の価値が強くなる
物価が上がり続ける現象
お金の価値が弱くなる
どちらに偏っても、企業も個人も不安定になり、社会全体のバランスが崩れます。極端なデフレは経済活動を停滞させ、極端なインフレは生活を困窮させる。この両極端を避けることが、健全な経済の基本です。
日本は失われた30年を経て、デフレからインフレへ変化した
バブル崩壊後、日本は長い間デフレと向き合ってきました
物価が下がり続ける中でも、治安や社会秩序は安定し、生活の基盤は揺るがなかった
世界的なインフレの波の中で日本でも物価が上昇傾向に
「賃金が追いつく穏やかなインフレ」=安心できる循環です。急激な物価上昇ではなく、所得の向上とバランスの取れた持続可能な成長を重視しています。
デフレでもインフレでもない状態を目指すべきではないのか
貨幣の価値が一定である社会こそ、
人々に最も安心をもたらす経済構造ではないでしょうか。
変化を恐れるのではなく、安定を選び取る勇気。それが今の日本の成熟を象徴しています。
物価が安定していれば、将来の計画が立てやすい
貯蓄の価値が守られ、老後の不安が軽減される
価格設定や投資計画が立てやすく、長期戦略が可能に
安定した貨幣は、世界中から求められる「有事の円」
世界が混乱するたびに、投資家は円を買います。それは「日本円が安全だから」ではなく、「日本が一貫して安定を体現してきたから」です。
上昇と下降の波に飲み込まれず、静かに時間を刻む通貨――この「中庸の力」が、世界に安心感を与えています。地政学リスクや金融危機が発生するたびに、円が買われるのは、日本経済の底堅さへの信頼の証なのです。
💡 有事の円が示すもの
リーマンショック、コロナショック、地政学リスク——世界的な危機のたびに円が買われてきました。これは日本経済の「変わらない強さ」が世界から評価されている証拠です。
同じ価値を維持し続ける経済状況を示す言葉はない
デフレでもなく、インフレでもない。この中間を保ち続ける状態には、まだ正式な経済用語がありません。
もし名付けるならば、「同じ価値経済」
価格でもGDPでもなく、「感じ方の安定」が続く社会。それは、貨幣と感情の調和がもたらす新しい経済形です。
従来の経済学では捉えられない概念
経済学は成長か停滞か、インフレかデフレかという二項対立で語られがちです。しかし、日本が実現してきたのは、その中間にある「安定的な均衡」。これは従来の経済理論では十分に評価されてこなかった、新しい経済の在り方なのです。
学術的に説明できないことを30年間、日本経済は行ってきた
経済学の理論では説明しきれない——それが日本のこの30年です。
GDP成長率は低かったが…
生活コストは安定していた
世界最高水準の安全性を維持
社会保障と秩序が機能し続けた
「変わらないことこそが、最大の価値だった」
日本は「スピード」ではなく「信頼」で進む国。そして今、高市政権が掲げる「安定と賃金上昇の両立」こそ、この「同じ価値経済」を次の段階へ進化させる挑戦なのです。
数字の豊かさと心の豊かさ
世界が不安定さの中で揺れるとき、日本は「変わらない安心」で世界を惹きつける国になる。それは、スピードではなく、秩序と静けさを誇る成長です。
「平均年収がいくらか」ではなく、「その年収でどんな暮らしができるか」という「実感としての豊かさ」です。
アメリカの平均年収は日本より高い。でも、格差・犯罪・家賃・医療費の現実を見ると、「数字の豊かさ」が「心の豊かさ」と一致していないことに気づきます。
日本は大きく変わらなかった。けれど、安心して暮らせる社会を守り抜いてきた。それは世界のどの国も真似できない「静かな強さ」であり、「同じ価値を保つ国」という新しい幸福の形なのです。
それが、これからの日本が世界に示す新しい豊かさの形です。




