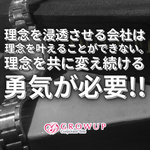Blog
構造化する“人”の力(第4回)人が動きたくなる“ナッジ経営”という設計力

目次
組織を動かすのは「指示」ではなく「設計」である
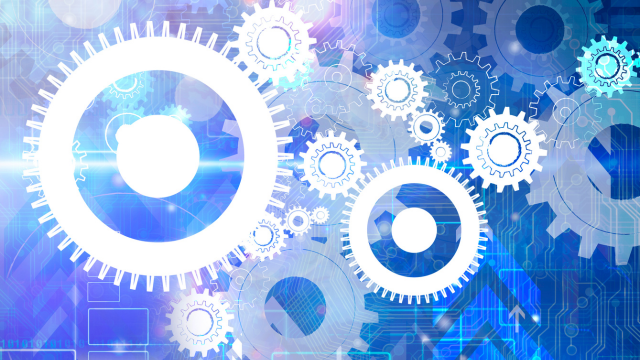
優れた組織は、人を“動かそう”としない。
では、どうして自然と人が動くのか?
それは、行動したくなる“場”が設計されているからです。
人が行動を起こす背景には、「命令」や「目標」よりも、“選びやすさ” “迷わなさ” “安心感”といった環境要因が強く影響しています。
つまり、経営とは単に“動機づけ”することではなく、人が自然と動き出したくなる“構造”をつくることなのです。
ナッジ理論とは何か?

ここで重要な概念が、ナッジ理論(Nudge Theory)です。
ナッジとは、「そっと背中を押す」という意味。
つまり、人に強制せず、あくまで自発的に“望ましい選択”へ導く行動設計のこと。
ナッジを活用した仕掛けの例
- ✔️ 健康志向の社食で、サラダを最初に並べる
- ✔️ 会議室予約に「目的入力欄」を追加し、無駄な会議を抑制
- ✔️ 社内表彰で“理念に基づいた行動”を見える化
- ✔️ 初期設定(デフォルト)を工夫して選択の質を向上
ナッジは、“人の意志”を前提にしながら、行動をデザインする経営の道具となります。
「人が動く空気」は設計できる

組織には、「この会社ではこういう行動が歓迎される」という空気があります。
この“空気”こそが、ナッジによってつくられています。
たとえば:
- ✔️ Slackの反応スタンプ文化が、心理的承認を生む
- ✔️ 1on1の習慣が、“話していい空気”を醸成する
- ✔️ 会議での「問いの出し方」が、主体性の有無を決める
つまり、文化や雰囲気もまた、ナッジの集積によってつくられる「構造」なのである。
行動設計は「人的資本の活性装置」である
人的資本とは、人が持つ能力や経験の“ストック”ではありません。
その資本が、行動として発揮されてはじめて意味を持ちます。
だからこそ、人が自然と動ける環境=ナッジ設計は、人的資本経営の“実行装置”として極めて重要です。
行動が組織を動かす3ステップ
- 行動が引き出される(自然に動きたくなる環境)
- 行動が強化される(評価・フィードバックが循環)
- 行動が共有される(周囲に波及し、文化になる)
この流れが機能して初めて、組織に“力が流れる”。
ナッジは「意志への敬意」から生まれる

最後に大切なことをひとつ。
ナッジとは、「人の自由意思を前提に設計する技術」です。
指示や命令ではなく、
選択を尊重しながら、よりよい未来へ導くやさしい力学。
経営とは、「人の意志に敬意を払いながら、行動を設計すること」。
人を動かそうとするのではなく、
人が“動きたくなる構造”をつくる。
それが、これからの人的資本経営の中核である。
次回予告
次回は、行動のさらに深層へ──
人が動く前に必ず存在する、“感情”というレイヤーに注目します。
第5回|“感情デザイン”としての経営
感情を読み、積み重ね、行動につなげる構造とは何か?