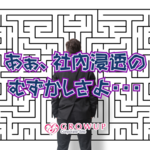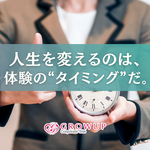Blog
ビジネスをあるべき姿へする前に!現状認識概念図と概念データモデル作成のすすめ

目次
概念データモデルとは? その目的と意義
ビジネス要件に即した高レベルな視点で、業務の主要概念(エンティティ)とそれらの関係を図式化するための設計段階です。
この段階では技術要素(データ型やDBMS)には依存せず、純粋に業務理解に焦点を置くことが重要になります。
概念データモデルは、ステークホルダー間の共通理解基盤として機能し、プロジェクトに関わる全ての人が「本当に必要なデータは何か」「それらはどのようにつながるのか」を整理する際の共通言語となります。
技術的な詳細に踏み込む前に、まずはビジネスの本質を捉えることで、後の設計段階での認識のズレを防ぐことができるのです。
設計ステップ:基本的な流れ
ステップ①
業務の核心を把握し、ユースケースを整理
まずは業務の中心となるユースケースやビジネスプロセスを明確にし、どのような情報を記録・管理したいかを洗い出します
ステップ②
主要なエンティティを特定
ビジネス的重要性に基づいて定義します
例:顧客/注文/商品/支払いなど
ステップ③
エンティティ間の関係性(リレーション)を定義
実世界の関係を明確化します
「顧客が注文を行う」「注文には複数の商品が含まれる」など
ステップ④
基本的な属性を簡易的に定義
IDや識別子など、必須の情報を簡潔に記述し、必要以上の技術要素(データ型や制約など)は避けます
ステップ⑤
ER図などで図示し、ステークホルダーとレビュー
図式化することで共有が容易になり、認識ズレの早期発見につながります
ステップ⑥
反復と共創
利害関係者と何度かレビューや改訂を進め、設計内容が業務要件と整合していることを確認します
概念→論理→物理の3段階モデルを5段階モデルで分かりやすく
概念モデル
何を扱うか(エンティティと関係)の高レベル抽象
論理モデル
どのように構造化するか(属性、正規化、キー設定など)
物理モデル
どのように実装するか(テーブル定義、インデックス、DBMS固有設計)
→5段階モデルへ
従来の3段階モデルでは捉えきれない現代ビジネスの複雑さに対応するため、より包括的で実践的な5段階モデルを採用します。このモデルでは、事業戦略から組織連携まで、業務設計に必要な全ての観点を体系化できます。
| モデル種別 | 主な構成要素 | 活用場面・連携イメージ |
|---|---|---|
|
事業領域と使命モデル
Business Domain & Mission Model
|
ドメインエンティティ、使命、価値提案 | 全社戦略やドメイン設計の上位レイヤーとして整理 |
|
静的モデル
Static Model
|
エンティティ、属性、リレーション | 概念モデルやデータ設計、業務対象の整理に活用 |
|
動的モデル
Dynamic Model
|
アクティビティ、イベント、状態遷移 | 業務フロー設計、ユースケース設計、プロセス自動化に適用 |
|
組織間連携モデル
Organizational / Inter-organizational Collaboration Model
|
組織/役割、部門連携、インタフェース | 部門間・外部連携の可視化と責任分担、ガバナンス検討 |
|
機能モデル
Function Model
|
機能単位の入力・出力・制御・構成要素 | 業務機能の階層設計、コスト評価、業務改善の分析基盤として利用 |
事業領域と使命モデル(Mission Model)|事業の方向性を示す「使命」を中心に据えた全体像モデル

企業や事業の「使命(Mission)」を中心に、戦略、価値観、方針、目的などを配置し、全体の方向性をひと目で把握できる図です。
静的モデルと動的モデル
路線図と時刻表で理解する業務の構造とプロセス
路線図と時刻表で理解する業務の構造とプロセス
🚉 静的モデル(路線図)
中津駅
梅田駅
淀屋橋駅
構造・関係性
を表現・駅の位置関係
・路線の接続
・距離や配置
・時間に依存しない
⏰ 動的モデル(時刻表)
時間・プロセス
を表現・電車の動き
・停車時刻
・運行順序
・時間軸がある
↓
ビジネスシステムでも同じ考え方:
📊 静的モデル
・組織図、データ構造
・「誰が」「何を」持っているか
・エンティティの関係性
・組織図、データ構造
・「誰が」「何を」持っているか
・エンティティの関係性
🔄 動的モデル
・業務フロー、処理手順
・「いつ」「どう」動くか
・プロセスの時系列
・業務フロー、処理手順
・「いつ」「どう」動くか
・プロセスの時系列
組織間連携モデル(Organizational Collaboration Model)|部門・組織のつながりと役割分担を描く連携図
組織間連携モデル
病院の診療連携で理解する部門間協働の仕組み
病院の診療連携で理解する部門間協働の仕組み
🏥 受付
患者登録・予約管理
保険証確認
保険証確認
↓
患者基本情報
👨⚕️ 診察室
診断・治療方針決定
処方箋・検査指示
処方箋・検査指示
↓
診断結果・指示
🔬 検査室
血液検査・画像診断
検査結果報告
検査結果報告
↓
検査データ
💊 薬局
調剤・服薬指導
薬歴管理
薬歴管理
💰 会計
診療費計算
保険請求・支払い
保険請求・支払い
📋 情報管理・サポート部門
医事課・電子カルテ
全部門の情報統合・カルテ管理・データ連携
患者接点部門
診療部門
検査部門
薬剤部門
会計部門
情報管理部門
組織間連携モデルの特徴:
・各部門の役割と責任を明確化
・部門間の情報の流れと連携ポイントを可視化
・患者体験の背後にある組織協働の仕組みを理解
・業務改善や責任分担の見直し、システム設計に活用
・各部門の役割と責任を明確化
・部門間の情報の流れと連携ポイントを可視化
・患者体験の背後にある組織協働の仕組みを理解
・業務改善や責任分担の見直し、システム設計に活用
機能モデル(Function Model)|業務機能の構成と入出力を整理する機能構造図
例:コンビニエンスストアの業務機能を機能モデルで整理
機能モデルとは
業務プロセスを機能単位に分解し、各機能の入力(インプット)と出力(アウトプット)を明確にした構造図です。ここでは身近なコンビニエンスストアを例に、お客様への価値提供プロセスを機能別に整理しています。
📥 インプット(入力)
• お客様(来店者)
• 商品・サービス
• スタッフ
• 設備・システム
• 運営資金
📤 アウトプット(出力)
• 満足したお客様
• 売上・利益
• ブランド価値
• 地域サービス
• 雇用創出
⬇
来店受付
商品選択支援
決済処理
サービス提供
退店案内
在庫管理
POS運用
金銭管理
品質管理
供給管理
人員管理
設備管理
経営管理
凡例
主要プロセス(顧客接点)
支援プロセス(運営支援)
管理プロセス(経営基盤)
インプット
アウトプット
機能モデルの読み方
上段(青色):お客様と直接接触する主要な業務機能。顧客価値を直接創出する。
中段(オレンジ色):主要プロセスを支える運営支援機能。効率性と品質を担保する。
下段(紫色):全体を統制する管理機能。戦略的意思決定と基盤整備を行う。
活用場面:業務分析、システム設計、組織設計、業務改善、品質管理などで使用される。
まとめ
概念データモデル設計は、業務要件をデータの形で可視化し、合意形成を支える共通言語です。
業務構造の漏れを防ぎつつ、後続の設計フェーズへスムーズに展開するための基盤設計として極めて重要です。
ステークホルダーとの共同作業を通じて、認識齟齬を早期に修正・防止でき、開発の信頼性と効率性を高めます。