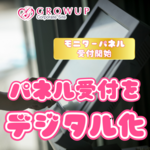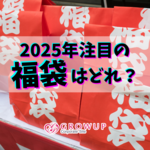Blog
最低賃金、全国で1000円突破!その影響は??
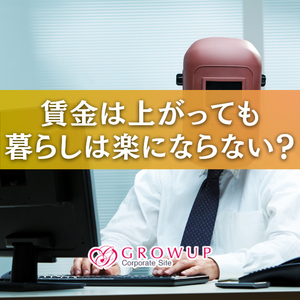
日本の最低賃金がついに全国で時給1,000円を突破しました。家計には追い風、採用では魅力的な材料となる一方で、粗利率の低い現場では“時給の1円”が経営を直撃します。
一部地方の審議会では使用者側が退席する事態も発生。この記事では、過去10年・20年の推移を踏まえつつ、地域ごとの“無理”の出方、価格転嫁の現実性、撤退回避の具体策を整理します。インフレ時代における賃金と価格のリアルをわかりやすく読み解きます。
目次
2025年、全国でついに「1000円」突破!10年前・20年前と比較

2025年度の最低賃金は、47都道府県すべてで時給1000円超に到達しました。
最高は東京 1,226円、最も低い県でも1,023円です。全国加重平均の目安は1,118円(+63円)となっています。
発効は例年どおり10月以降ですが、都道府県によっては2026年初頭まで順次実施されます。発効日一覧は最新のまとめで確認してください。
※ 県ごとの発効時期は賃金体系の見直し等で遅れる場合があります。
- 10年前(2015年)の全国加重平均:798円
- 20年前(2005年)の全国加重平均:668円
→ 2015→2025は約+40%、2005→2025は約+67%の伸びです。
20年前から比べると+300円、10年前からは+200円の上昇。月収換算では約+50,000円、年収では約+600,000円の増加に相当します。
結構、無理をした地域もある?
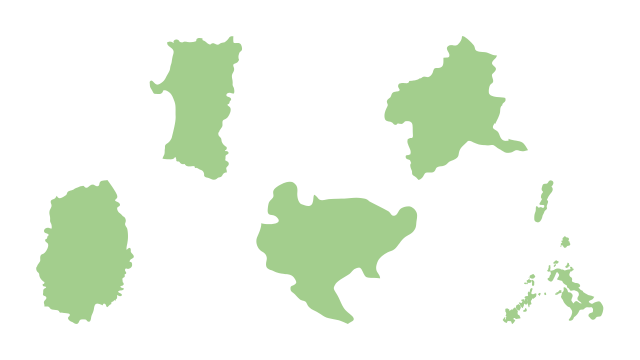
今年は39道府県が国の目安額を上回る「上乗せ改定」を実施しました。人材確保競争と格差是正の流れが背景です。
その結果、発効時期が例年の10月から遅れる県も出ています。たとえば秋田は2026/3/31、群馬は2026/3/1を予定しています(賃金体系の見直しに時間を要するため)。
使用者側の“全員退席”が相次ぐ
各地の地方最低賃金審議会では、使用者(企業)側の委員が全員退席する事例が複数報じられています。代表的なケースを挙げます。
- 岩手県(8/28):時給を1031円(+79円)にする答申を採決する際、使用者側委員は全員退席。その後、賛成多数で可決されました。退席理由は「引き上げ額の根拠に納得できない」などの強い反発です。
- 佐賀県(8/26):1030円への引き上げを使用者側退席のまま採決。発効日も11/21と例年より遅れる異例の決着となりました。
- 長崎県(9/2):1031円(+78円)の答申が出され、採決前に使用者側が退席したと報道されています。
いずれも「中央最低賃金審議会の目安に上乗せする」ことを巡る緊張が背景にあり、現場の負担感が表面化したかたちです。
企業への影響──インフレ時代に価格転嫁できるのか?
価格転嫁の現状と政策の動き
直近の調査では、コスト上昇の価格転嫁率は39.4%と低水準にとどまっています。特に人件費の上昇分は転嫁しづらく、企業の吸収負担が大きくなっているのが実情です。
政府は「価格交渉促進月間」などで取引慣行の是正を後押ししており、取引先との交渉実施割合は改善傾向にあります。
日銀は、賃金と価格設定行動の“積極化”を指摘していますが、賃金上昇が物価上昇に結びつき、好循環が維持できるかどうかは最終的に企業の価格決定行動に委ねられると分析しています。
賃上げに耐えきれない企業は撤退を余儀なくされる?
倒産・撤退リスクと公的支援
足元では「人手不足」関連倒産が過去最多ペースで発生しています。賃上げや待遇改善が遅れた企業ほど人材流出が進み、資金繰り悪化につながる傾向が明確です。
人件費高騰が要因の倒産増も指摘されており、2025年8月には「人件費高騰」が要因とされた倒産件数が2.7倍増との報告があります。
さらに、最低賃金が政府の目標ペース(+7.3%)で上昇した場合、「廃業・休業などを検討」15.9%という中小企業調査の結果も示されています。地方・小規模事業者への影響は特に深刻です。
とはいえ、業務改善助成金などの公的支援を活用すれば、生産性向上とセットの賃上げを後押しできます。設備投資や教育訓練費の一部が助成対象となる制度もありますので、計画的な申請と投資の検討がカギです。
短期的な送料削減や値上げだけでなく、助成金を活用した省人化・生産性投資で中長期的に耐える体力をつけることが重要です。
まとめ(要点だけ)
最低賃金改定の要点まとめ
- 全国1000円超えは歴史的節目。平均1118円へ、地域最安でも1023円。
- 上乗せ改定が多数で、一部県は発効を遅延(2026年春まで)=現場負担の大きさを示す。
- 価格転嫁は依然難航(転嫁率39.4%)。取引慣行の是正と交渉の定着がカギ。
- 淘汰圧力は強まる一方、助成金や省人化投資で持ちこたえる道も。
- 最低賃金上昇により、税収・社会保険料は増加=財政健全化へ寄与。
現場で今日からできること(実務チェックリスト)
- メニュー・価格設計の再点検:原価と作業時間を秒単位で可視化 → 粗利/人時でABCD分類。
- シフト設計×需要予測:曜日・時間帯別の来客/作業負荷ヒートマップで人時最適化。
- 省人化投資の優先順位付け:注文・会計の自動化、下ごしらえ機器、RPA等。助成金要件に沿った計画化。
- 取引先との価格交渉を定例化:賃上げ率や外部指数を根拠に、四半期ごとの見直しルールを合意。
- 採用・定着の総コストで比較:時給だけでなく離職率・教育コスト・多能工化で人件費/売上の中期目標を設計。
参考(主要発表・統計)
- 全都道府県で1000円超(2025年度改定まとめ)
- 琉球新報デジタル
- 10年前・20年前の平均(798円/668円) – JIL労働法研究所
- 経団連
- 発効が翌年にずれ込む県あり(秋田・群馬など)
- 価格転嫁の実態(転嫁率39.4%)と交渉促進状況
- 中小の廃業・撤退懸念調査、倒産動向
- 業務改善助成金(厚労省)