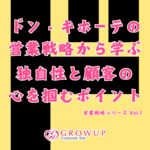Blog
トランプ政権の非公式リスト、貿易赤字の是正のための【ダーティ15】の国家を大胆予測!
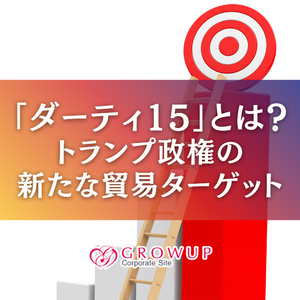
目次
ダーティ15とは何か?

「ダーティー15(Dirty 15)」という言葉は、2025年3月18日にアメリカのベッセント財務長官(財務次官補)が言及したとされる言葉で、関税・非関税障壁が目立つ15か国を指す非公式なリストです。
ダーティ15の概要
名称の意味:「dirty(汚い)」という表現は、アメリカから見て「不公正な貿易慣行」や「不透明な関税・非関税障壁」を持つ国々に対する批判的なラベルです。
発言者:ベッセント財務長官(Assistant Secretary for Economic Policy, U.S. Treasury)
日付:2025年3月18日
文脈:トランプ氏の「相互関税(reciprocal tariffs)」政策の流れの中で言及された。
内容の背景
「ダーティー15」という用語は公式な政策文書ではなく、政治的なレトリックと考えられます。
ただし、以下のような共通点を持つ国々が含まれると推測されています。
・アメリカに対して継続的な貿易黒字を抱える国
・自国市場に対して高い関税や非関税障壁(技術基準、検査制度、補助金など)を設けている
・知的財産権の保護や透明性に欠けるとされる国
・為替操作や国家主導の産業政策などがある国
なぜ重要なのか?
トランプ政権の再登場が現実味を帯びる中、彼の「アメリカ・ファースト」政策において、この「ダーティー15」リストが制裁・関税引き上げ・FTA再交渉の対象になる可能性があるという警戒感が市場や国際社会に広まっています。
トランプ大統領の過去の発言から15の国を大胆予測!
トランプ大統領の過去の発言・ツイート・政策文脈をもとにして、「ダーティー15」に該当しそうな国を大胆に予測してみましょう。
| 順位 | 国 | トランプの主な発言 | 批判ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 (CN) | 「アメリカを何十年も利用してきた」 「関税は武器」 | 貿易黒字、知財、国家補助金、不公正な市場慣行 |
| 2位 | ドイツ (DE) | 「自動車は米国を壊す」 「NATOにも金を払わない」 | 自動車産業、NATO負担、EU最大の対米黒字国 |
| 3位 | 日本 (JP) | 「車は全部日本から」 「米市場は開放、日本市場は閉鎖的」 | 自動車・農業の市場閉鎖性、貿易赤字問題 |
| 4位 | メキシコ (MX) | 「雇用を奪っている」 「国境の壁を建てる」 | NAFTA見直し、製造業の移転先としての問題視 |
| 5位 | カナダ (CA) | 「乳製品の関税が異常」 「トルドーは裏切り者」 | 鉄鋼・乳製品分野で対立、NAFTA交渉の不公平感 |
| 6位 | 韓国 (KR) | 「防衛費を払っていない」 「FTAが不公平」 | FTA再交渉、貿易摩擦(自動車・鉄鋼) |
| 7位 | インド (IN) | 「タリフ(関税)王」 「アメリカ企業への扱いがひどい」 | 高関税政策、米企業への不利な取り扱い |
| 8位 | ベトナム (VN) | 「世界一悪質な貿易操作国」 | 対米黒字急増、中国の関税回避ルートとして批判 |
| 9位 | フランス (FR) | 「デジタル課税は米企業への戦争」 | GAFA(米IT企業)へのデジタル課税 |
| 10位 | ブラジル (BR) | 「鋼鉄とアルミで我々を攻撃している」 | 鉄鋼・農産物の高関税、一時制裁対象に |
| 11位 | トルコ (TR) | 「通貨危機は自業自得」 「リーダーは独裁的」 | 鉄鋼関税の対象、政治的緊張も影響 |
| 12位 | タイ (TH) | (名指しは少ない) | 製造業シフトによる黒字拡大、関税の透明性の問題 |
| 13位 | イタリア (IT) | 「EUは中国より悪い」発言の代表格 | EU内での対米黒字が大きい、非関税障壁の指摘 |
| 14位 | マレーシア (MY) | (名指しは少ない) | 関税逃れの「迂回先」として問題視 |
| 15位 | スイス (CH) | 「為替操作の疑いがある」 | 財務省報告書で批判対象、金融・医薬品分野 |
※ロシアは経済制裁中なので除外
選定のポイント
・発言の頻度・トーン:ツイートや演説での直接批判の強さ
・トランプ流の「不公平感」
評価:米国にとって「損してる」と感じた国、関税対象・制裁対象になったか
こんな発言が根拠です(一部紹介)
日本「我々は日本を守ってやっているのに、日本車でアメリカは溢れている。フェアじゃない!」(2019年)
ドイツ「彼らは素晴らしいベンツを作るが、私たちはアメリカ車を売ることができない」(2018年)
ベトナム「ある意味、中国よりも悪いかもしれない」(2019年6月・FOX Business)
トランプ大統領が狙っているのは関税だけではない?国際ルールのグレーな部分へ手を入れる

トランプ氏が狙っているのは「関税」だけじゃないんです。彼の過去の動きを分析すると、「国際ルールのグレーゾーン」「不均衡な制度設計そのもの」に手を入れようとする姿勢が見えます。
~国際ルールのグレーな部分へ手を入れる狙いとは?~
「WTOルール」そのものに対する攻撃
トランプ政権時代、WTO(世界貿易機関)を「時代遅れ」「アメリカを損させている」と批判。
上級委員会の人事を拒否して機能不全に陥らせた。
特に問題視したのが、中国などの「発展途上国」扱い。→「優遇されすぎている」と批判。
中国やベトナムのように制度の抜け穴を突いてくる国に対しては、ルールそのものを組み替えようという意図が見えます。
「為替操作」や「補助金制度」への踏み込み
通常の関税ルールでは対応できないような、為替誘導・国家補助金への対応を強化。
例)中国の人民元切り下げ、ドイツのユーロ安誘導疑惑、スイス・日本の為替介入も対象に。
通貨安=輸出優遇策という構図に「新たな関税」を上乗せする発想も。
金融政策のグレーゾーンも、貿易戦争のフィールドに引き込もうとしていたのが印象的です。
デジタル・環境・労働といった「非関税領域」も標的に
デジタル課税(GAFAなど米企業対象)を導入した国に対し、「報復関税」を表明。
環境基準・労働基準も「非関税障壁」として批判。
例:EUのカーボンボーダー調整措置(CBAM)に強く反発。
“環境”や“人権”を建前にしつつ、実際は保護主義なんじゃないかという視点も、攻撃のベースにあったと思います。
付加価値税(VAT)・消費税を巡る不公平の是正
トランプ氏は過去に、他国の「付加価値税(VAT)」制度がアメリカ製品に不利だと発言。
例えば日本やEU諸国では、国内製品にはVATを還付、輸入品には課税が行われており、「輸出支援」になっている。
一方、アメリカは付加価値税を採用しておらず、これが“制度的関税”として不公正だと批判。
関税だけでなく、間接税を含む各国の税制そのものを“不平等の構造”として再定義し、制度改正を迫る姿勢もありました。
「制度の歪みを力でねじ伏せる」リアルポリティクス
トランプ氏は、関税という “表の武器” だけでなく、
・WTOルールの盲点
・通貨政策・金融操作
・環境・デジタル・労働の隠れた関税化
・付加価値税などの税制不均衡
といった「制度のグレーゾーン」すらターゲットにしようとする動きを見せており、これは「制度破壊型」の貿易戦略といえます。
ケインズ経済学でも結論がでなかった貿易不均衡“赤字輸出”の解決方法は?

ケインズが提案していた“幻の世界貿易制度”
第二次世界大戦後、ケインズは貿易黒字国にも責任を負わせる国際通貨制度を提案(=バンコール構想)。
しかし、アメリカ(当時の超・黒字国)が拒否。結果、現行のIMF-ドル体制に。
根本の問題として、今の国際制度は“黒字国に罰はなく、赤字国だけが調整役に回らされる”構造なんですよね。
貿易不均衡とは、貨幣の流出と労働の空洞化のトレードオフ
輸入過多 → 自国産業空洞化 → 失業増加 → 財政悪化 → 通貨下落…
という「赤字スパイラル」が発生。
ケインズは「赤字国だけが苦しむのは不健全」と指摘するも、現実の貿易システムは、“黒字国優遇型”に固定化されてしまった。
トランプ流のアプローチは“逆ケインズ”型?
トランプ氏の「相互関税」「赤字国の自衛権」的な発想は、ある意味でケインズ的でもある。
違うのは、協調的制度改革ではなく、力による再交渉(ディール)で問題を解決しようとしている点。
制度で解決できないなら、もう直接叩くしかない——そんな発想が透けて見えます。
赤字輸出=“ダンピングされる側”の苦悩
・黒字国は「製品を安く輸出」して利益を得るが、赤字国はそれに雇用・企業・文化を奪われる。
・かといって赤字国が保護主義に走れば、「世界経済の分断」になる。
📌 現在も結論が出ていないジレンマ
→ グローバル市場に参加するほど赤字国は損をしやすくなる。
→ 引きこもると成長のチャンスを失う。
解決の方向性は“国際制度+国内改革”のハイブリッド?
赤字国がやるべきこと
・自国の競争力強化(技術、教育、インフラ)
・為替政策の柔軟化
・付加価値税などの間接税改革(輸出戻し税導入)
国際社会がやるべきこと
・黒字国へのインセンティブ付き調整圧力
・多国間協調的な不均衡是正ルールの再構築(新・ケインズ的枠組み)
「貿易赤字はその国の無能さ」ではない。
構造的にそうなりやすい制度と立場があります。
ケインズが夢見たように、「赤字国にだけ痛みを押しつけない」世界ルールが必要ですが、現実はむしろ逆行しており、トランプのような“力の政治”に傾くリスクにさらされています。
現状ではトランプ大統領が用意したテーブルに座り、ディールを繰り返していくことが善策でしょう。国際貿易間の構造的な問題を解決し、より公平はルールの再構築をめざしていきましょう。