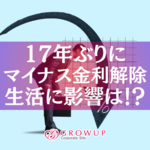Blog
推し活×哲学|第5話:存在としての推し活──“好きでいること”が自分を映すとき
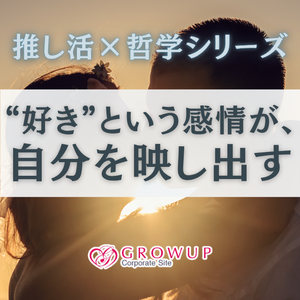
目次
「なぜこの人を推してしまうのか?」という問い

顔が好き
歌がうまい
演技に惹かれる
歌がうまい
演技に惹かれる
──理由はいくつもあるけれど、最終的に私たちはこう言います。
「なんでか分からないけど、好き」
「理由なんて、ない」
「理由なんて、ない」
この“説明不能な好意”こそが、推し活の深淵。
そしてその奥には、「なぜ私はこの人を好きになる存在なのか?」という、自己の存在への問いが潜んでいます。
好きになるとは、“存在にYESを言う”ことである

哲学者マルティン・ブーバーはこう語りました。
「人は『我―それ』ではなく、『我―汝』という関係の中で世界とつながる」
これは、「対象」として誰かを見るのではなく、“あなた”として存在を肯定し合う関係が本質だということ。
推しを好きになるとは、その人の存在に対して「YES」と言うこと。
つまり“あなたはそこにいていい”と、誰かの存在そのものを祝福することなのです。
“推し”は関係性のなかに生まれる存在

重要なのは、「推し」は最初からそこに“いる”存在ではないということ。
私たちが見つけ、注目し、好きになることで、“推し”という存在が立ち上がるのです。
これは言い換えれば、「推し」というのは“私とその人との関係性のなかで立ち上がる人格”だということ。
他の誰かにとってはただの芸能人でも、自分にとっては人生の支えとなるのは、“出会い方”が生んだ存在の意味構造が違うから。
推し活は“存在の引力”を自覚する行為

推し活とは、誰かの生き方・言葉・存在が、自分の内面と響き合い、“引き寄せられる感覚”を形にしていく行為です。
それは「この人が好き」ではなく、
「私はこの人を“好きになってしまうような存在”だったのだ」
という、自己理解のプロセスでもあります。
だから推し活は、ときに苦しく、ときに尊く、そして深く“自分自身の存在”と向き合う儀式となるのです。
まとめ──誰かを好きでいることは、自分の存在を問い直すこと
推しとは「存在を肯定する行為」であり、「自分という存在の再定義」でもある。
誰かを好きになるということは、自己の在り方を映し出す鏡。
推し活の深層には、「私は誰か?」「何に心を動かされる存在なのか?」という問いがある。
推し活とは、あなたが“自分にとっての真実”を探す旅。
誰かを好きになるということは、自己の在り方を映し出す鏡。
推し活の深層には、「私は誰か?」「何に心を動かされる存在なのか?」という問いがある。
推し活とは、あなたが“自分にとっての真実”を探す旅。
それは自己肯定の始まりであり、人生の深度を測るコンパスでもあるのです。
このシリーズ「推し活×哲学」は、全5話で“推し活”という営みの奥深さをさまざまな角度から掘り下げてきました。
各回の詳細は、以下のボタンからまとめてご覧いただけます。
- 儀式性:なぜ通うのか
- 記憶とアイデンティティ:なぜ覚えているのか
- 自己変容:なぜ変わってしまうのか
- 共同体性:なぜ語り合いたくなるのか
- 存在論:なぜ好きでいられるのか
各回の詳細は、以下のボタンからまとめてご覧いただけます。