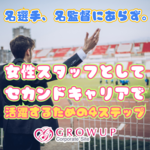Blog
推し活×哲学|第4話:共同体としての推し活──“私たち”であることが人を救う
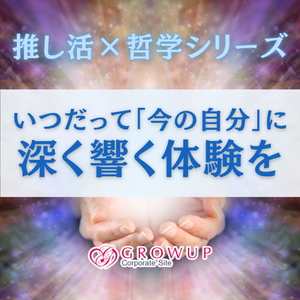
目次
なぜ“誰かと語りたい”と思うのか?

ライブが終わったあと、ふと感じる。
「この気持ち、誰かと分かち合いたい」
「あの演出、あの表情、あのセトリ……語り合いたい」
その衝動は、ただのテンションではありません。
それは“感情を誰かと重ね合わせる”ことで、体験を定着させたいという本能的欲求です。
「共在性」とは、“同じ場にいる”という感覚
哲学者ジャン=リュック・ナンシーは、「存在は常に“共にある(être-avec)”」と言いました。
つまり、人間の存在は最初から“他者との共在性”を前提としているのです。
推し活では、この“共にある”感覚が特に強く生まれます:
そして「一人じゃない」という小さな救いです。
- 現場で隣にいた人と目を合わせて泣く
- SNSで同じ熱量の感想を見つけてうなずく
- 「#○○最高かよ」で感情を共有する
そして「一人じゃない」という小さな救いです。
孤独な時代に、推し活が果たす“共同体的役割”
現代は、社会的には「つながっている」のに、心理的には「誰ともつながれていない」と感じやすい時代です。
そんな中で、推し活は感情を共有できる“仮想の村”のような役割を果たします。
- 同じ想いを持つ他者がいる
- 遠くても、同じ時間に同じ熱量で心を動かしている人がいる
- その存在に支えられて、「好きでいていい」と思える
これは、旧来の地域共同体に代わる“新しい所属感の場”です。
「私たち」があるから、“推しを好きでいられる”

推し活は個人的な行為であると同時に、集団的な営みでもあります。
そして、ときにこんなことすら起こります。
「一人だったら、こんなに長く応援できなかった」
「仲間がいたから、踏ん張れた」
「“あの頃の私たち”があって、今の私がある」
ここで重要なのは、“推しの存在”だけではなく、“推しを通じて出会えた他者の存在”もまた、人生を構成する要素になっているという点です。
まとめ──感情を共有できる場所が、人を生かしている

人は、意味のある体験を誰かと分かち合うことで、少しずつ心を落ち着けていきます。
推し活には、そんな共感と連帯の感情があふれる空間があります。
「ここにいていい」と思える場所。
「好きでいていい」と思えるつながり。
「好きでいていい」と思えるつながり。
ただ推しがいるだけでは、人は救われません。
その推しについて、一緒に語れる誰かがいること。
それが、私たちの心を支えてくれるのだと思います。