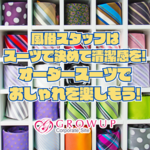Blog
11月23日は勤労感謝の日!”働く”をもう一度見つめ直す日

11月23日は「勤労感謝の日」。
カレンダーに当たり前のように載っている祝日ですが、実は”働くことの本質”を考える、とても深い意味を持つ日でもあります。
かつては当たり前のように言われたこの言葉も、価値観が多様化した今、別の受け止め方をされることも増えました。
働くとは何か。誰に感謝するのか。そもそも、なぜ「勤労に感謝する日」が祝日として存在するのか。
そんな素朴で大切な問いを、今日は一緒に掘り下げてみましょう。
目次
勤労感謝の日ってなんぞ?その制定の意味や目的は?
勤労感謝の日は 1948年(昭和23年)7月20日に公布・施行された祝日法によって制定 されました。
祝日として表記されるのは「11月23日」。これはルーツである「新嘗祭(にいなめさい)」の日付を引き継いだものです。
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」
もともとは五穀豊穣を祝う日でしたが、戦後の祝日法によって、次のような意味を持つ”国民全体で感謝し合う日”に形を変えました。
- 働くことの尊さ
- 社会を支える生産活動
- 多くの人の働きによって生活が成り立つこと
「おかげさまで忙しくさせてもらっています。」はもう死語?
昭和から平成にかけて、ビジネスの場でよく聞かれたフレーズ。
しかし現代では、忙しさ=美徳、長時間労働=立派という価値観は薄れつつあります。
とはいえ、この言葉が持つ本来の意味は“お客様や仲間のおかげで仕事があることへの感謝”。実はとても美しい価値観です。
言葉としては古くても、精神としては今こそ大切にしたい感謝の姿勢なのかもしれません。
働けることに感謝するのか?働いている人に感謝するのか?
結論から言えば、両方です。
● 働けることに感謝
健康で、能力を活かし、社会とつながれるという”環境”があること。これは当たり前ではなく、ありがたいこと。
● 働いている人に感謝
社会は誰かの労働の積み重ねで動いています。
- 電気・水・病院・物流・食品・教育・エンタメ
日常の当たり前は、すべて「誰かの仕事」の上に成り立っています。
だからこそ、勤労感謝の日は
“働けることへの感謝”と”働く人への感謝”が同時に存在する日なのです。
働くことは端を楽にさせること、世の中はほかの誰かの仕事でできている
つまり、働く=誰かを楽にする行為。
自分の仕事が誰かの役に立ち、誰かの仕事が自分を支えている。この連鎖で社会は動いています。
勤労感謝の日は、そんなことをふと立ち止まって考えられる、大切な節目の日です。
- 今の仕事が誰の役に立っているのか
- 自分の生活を支えてくれている人は誰なのか
- 社会はどれだけ多くの”はたらく”でできているか
まとめ
勤労感謝の日は「働く人をねぎらう日」以上の意味を持ちます。
- 働けることに感謝
- 働く人に感謝
- 社会を支える無数の”はたらく”に感謝
そんな ありがとうが交差する日。
私たちの暮らしは、見えない無数の仕事によって支えられています。