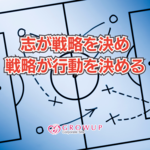Blog
RAG実践フェーズ【後編】Dify×n8nで実現する感情AIと体験の再構築

前編では、RAGの基本構造と「理念を実装するAI設計」について解説しました。
本後編では、その思想を「どのように現場で動かすか」という実装フェーズに移します。
Difyの高精度RAGエンジンがAIの「思考」を担い、n8nの自動化ワークフローが「行動」を担うことで、AIはもはや“答える存在”ではなく、”共に動く仲間”へと進化します。
RAGは、検索と生成の技術ではなく、“理念を現実化するための知的インフラ”。
この後編では、RAGの進化形である「Agentic RAG」「感情RAG」、そして“理念が学習するAI”の実現方法を明らかにします。
AIが企業の裏方から、ついに「ブランドの顔」へ。
その変化を支えるのが、Difyの高品質RAG機能とn8nの自動化ワークフローです。
この連携によって、顧客は「人ではなく理念と会話している」ような体験を得る。
それこそが、AIによる共進化体験マーケティング(CEEM)の到達点です。
この連携により、AIは単なる”回答者”ではなく、理念を実行する自律型社員として機能します。
これまでの顧客対応AIは、「効率化」のための装置でした。
しかし、Agentic RAGを組み込んだAIは違います。
理念・Vision・文化を理解した上で回答を生成するため、“人間的な誠実さ”や”ブランドらしさ”を保ちながら応答できます。
顧客接点AI = 「理念を伝える接客者」
この視点に立つと、AIは単なる自動応答ツールではなく、ブランド体験の担い手となります。
AIを”動かす”のはDify、AIを”つなぐ”のはn8n。
両者を組み合わせることで、理念を中心に据えた自律型ブランドコミュニケーションが可能になります。
FAQ対応ではなく、“理念対応”
顧客の感情や状況に合わせた語り口(例:「共感」「信頼」「挑戦」など)
顧客が“ブランドの人格”を感じるUX
「企業が何を信じているか」を、日々の対応で伝える。
つまり、理念を“接客言語”に変換するRAG。
感情や文脈を含む“生きたデータ”が自動で蓄積
体験をRAGのナレッジベースに反映し、「学習するブランド」へ
顧客体験そのものを次の体験価値として再利用する。
CDE(Collaborative Data Enhancement)の実装例。
AIが“自己修正”を行う
顧客体験の差分をRAGへ還元する“Feedback Loop RAG”
人間の教育PDCAを、AIが自動実行
理念×データによる「成長するブランド」。
失敗も学びに変え、共進化のループを完成させる。
ここで重要なのは、「AIが理念を語る」のではなく、AIが理念を”体験として再現する”ということ。
たとえば──
▸ “挑戦を讃える”理念を持つ企業なら、AIが顧客の挑戦を承認する言葉を返す。
▸ “体験で幸せを届ける”企業なら、AIが感情を共鳴させるストーリーを紡ぐ。
▸ “誠実な関係”を掲げる企業なら、AIは曖昧な回答を避け、確かな根拠を示す。
それぞれの瞬間に、顧客は「この会社らしさ」を感じる。
つまりAIは、理念を表現する最前線の媒体になるのです。
AIが文章を生成するだけでなく、「体験」を再現する時代が来ています。
いま求められているのは、”正しい答え”を返すAIではなく、“感じさせ、考えさせるAI”です。
「疑似体験」とは、AIが文章や映像を通じて、ユーザーに“体験の感覚”を与えるプロセスです。
たとえば、Difyが生成した説明文をもとに、SORAやRunwayなどの生成AIが映像を作成し、ユーザーはそれを「体験前のリハーサル」として視聴します。
この疑似体験は、顧客の「期待」を明確化させると同時に、理念に基づく“理想の体験像”を共有する手段になります。
このフェーズでは、顧客の行動がループ構造になります。
Difyが理念ベースRAGで文章・ナラティブを生成。
→ n8nが映像生成AIに接続し、視覚化。
→ 顧客が体験を”予測”できる。
顧客が実際にサービスを体験。
→ 感情・満足度・期待との差分をデータ化。
差分データを再びRAGナレッジベースに格納。
→ AIが次回の疑似体験生成に反映。
このループにより、AIは「理念 → 体験 → 学習 → 再設計」という自律進化のサイクルを実現します。
この循環の中核は、「理念を評価軸にするAI」です。
通常のRAGは”正確性”を評価しますが、理念駆動型RAGは“理念との一致度”で学習します。
たとえば、理念が「挑戦を称える」であれば:
これにより、AIは理念を「読み取る」のではなく、「評価軸として使う」ようになります。
| フェーズ | 担当 | 機能 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 疑似体験生成 | Dify | RAG+プロンプト生成 | 文章・構成案 |
| 映像化 | n8n | 映像AIへの接続・制御 | 疑似体験映像 |
| 体験評価 | n8n+フォーム/LINE | 感情・満足度収集 | 体験データ |
| 学習更新 | Dify | ナレッジベース更新 | 改善済みRAGモデル |
このプロセスを回すことで、AIは自動的に「理念とのズレを修正」し続けます。
つまり、理念を体現する自己改善型RAGです。
理念には、「言葉にできない部分」があります。
それを可視化するのが映像生成AIの役割です。
映像によって理念は“理解”ではなく”共感”として届きます。
このときAIは、単なる生成エンジンではなく、理念を演出する存在になります。
疑似体験と実体験の間に生まれるのは、「感情の差分データ」。
この差分を分析することで、AIは”何が期待を超え、何が届かなかったか”を学習します。
ここで登場するのが、感情RAG(Emotional RAG)です。
RAGに感情タグ(喜・楽・哀・驚・納得・違和感など)を紐づけ、回答生成時に「感情の構造」を参照させます。
これにより、AIは”正しい答え”ではなく、“感情的に響く答え”を生成できるようになります。
理念を映像・感情・行動に変換することで、企業は自ら進化するブランドへと変わります。
それが、フィードバックループRAG=「感情で成長するAI」の本質です。
企業が理念をAIに教え、AIが体験を顧客に届け、顧客が感じたことを再びAIに返す――。
この循環は、単なる技術ではなく、“共進化する哲学体系”です。
RAGはここで、人とAI、企業と顧客が共に成長する生態系を完成させます。
企業にとって、RAGとはもはや知識管理の仕組みではありません。
それは「理念を進化させるための思考装置」です。
AIが理念を学び、理念がAIを育てる。
その往復運動の中で、ブランドは“生きる存在”へと変わる。
RAG(検索拡張生成)は、もはや「AIの性能を上げる技術」ではありません。
それは、企業が自らの理念を進化させるための思考装置です。
AIが理念を学び、理念がAIを導き、そのAIが生み出す体験が、再び理念を磨く。
この循環こそが、“共進化するブランド”の本質です。
この三位一体の構造によって、AIは「知る存在」から「感じ、動き、学ぶ存在」へと変わります。
企業も顧客もAIも、それぞれの体験を共有し、感情を交換し、知を高め合う。
まさに、”人とAIが共に進化する社会”がここから始まります。
理念がAIに宿り、AIが理念を育てる。
その往復の中で、ブランドは生き続ける。