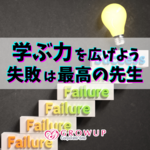Blog
RAG(検索拡張生成)とは?Dify×n8nで実現するプライベートAI【前編】
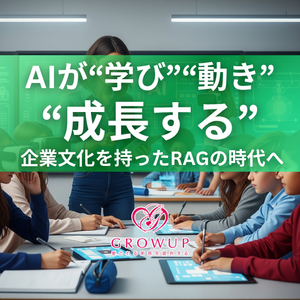
AIが私たちの仕事や生活に深く入り込み始めた今、単なる「便利なツール」から「共に考え、行動する存在」へと進化しつつあります。
その中核を担うのが、RAG(検索拡張生成:Retrieval-Augmented Generation)という技術です。
本記事では、このRAGの基本構造と、AI開発プラットフォームDify、自動化プラットフォームn8nを掛け合わせた次世代ワークフローについて解説します。
AIが「学び」「動き」「成長する」――そんな未来の業務プロセスが、すでに現実のものとなりつつあります。
AIが急速に進化する中で、次に求められているのは「大規模なAI」ではなく、“自分専用のAI”=プライベートAIです。
それは、誰かが教えてくれるAIではなく、自分の経験・知識・思考を学習し、共に進化する存在。
このプライベートAIを実現する上で、欠かせない仕組みがRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)です。
従来の生成AIは、膨大な一般知識をもとに文章を作り出しますが、その知識は「他人のデータ」です。
一方、RAGは自分自身のデータ(個人のメモ、議事録、文章、体験記録など)をもとに検索・生成を行うため、AIが「あなたを理解した上で答える」世界が実現します。
つまり、RAGは単なる技術ではなく、“自分の思考を拡張し、知識を私有化するための基盤”なのです。
たとえば、過去に書いた日報・議事録・ブログ・メールの内容をAIが参照し、「あなたが以前どう考えていたか」「どんな意図で判断したか」を踏まえた上で回答してくれる。
これが、プライベートAIとしてのRAGの真価です。
Difyはその中核として、個人の知識やドキュメントを安全に扱い、n8nはそれを日常の行動や業務に自動的に接続していく――。
この組み合わせこそが、プライベートAIの時代を切り開くRAGの最適解です。
RAG(検索拡張生成)は、一見すると単純な「検索+生成」の仕組みに見えます。
しかし、その実態は非常に奥深く、どこをどう設計・調整するかによって“AIの人格”が変わるほどの影響力を持っています。
AIが参照するドキュメント、会話ログ、社内マニュアル、議事録などを選定します。これがAIの「知の素材」となります。
文章を意味単位で分割し、検索の精度を高めます。この段階で、「どこで区切るか」「どの程度の粒度にするか」によって、AIの理解の深さが変わります。
チャンクを数値化して”意味空間”にマッピングします。同義語・文脈理解などの性能は、ここで使用するEmbeddingモデルの選定に依存します。
質問と最も関連性の高いチャンクを検索します。単なるスコアリングではなく、「社内データ優先」「最新情報優先」などの検索ロジックの調整が独自性を左右します。
検索で得た情報をもとに、LLMが自然文で回答を生成します。この段階でプロンプト設計を最適化すれば、回答のトーン・専門性・一貫性を自社仕様にできます。
RAGを単なる汎用AIにしないためには、以下の3点を自社文脈に合わせて設計・調整することが重要です。
多くの企業では、”1ページ=1データ”のように大雑把に分割してしまい、AIの理解が浅くなりがちです。
一方、独自性を出したい企業は、「業務の思考単位」でチャンクを切ります。
このように「現場思考」でチャンクを切ると、AIが自社文化や判断基準を理解するAIに変わります。
RAGの精度を高める最大の要は、データの取捨選択と分類設計です。
単なるFAQやマニュアルではなく、
これらをナレッジに加えると、AIが「形式知」だけでなく「暗黙知」まで扱えるようになります。
人間らしい共感や判断を出せるRAGは、ここで生まれます。
RAGの最終段階は”生成”です。ここで重要なのは、自社の言語文化を反映するプロンプト設計。
といった文体ルールをプロンプト化し、生成AIに埋め込むことで、AIのアウトプットが「その会社らしい声」になります。
RAGはオープンソースでも作れますが、独自性は”技術”ではなく”思想”に宿ります
RAGの本質は「どの情報を信じるか」という選択の技術です。
ハイブリッド検索(=Web検索+社内ナレッジベース検索)は、この”選択の質”を高めるための構造であり、企業の思想と市場戦略を反映させる要所です。
ハイブリッド検索は、AIが回答を生成する際に、外部情報(Web)と内部情報(自社データ)を統合的に参照する仕組みです。
たとえば、
この「統合のバランスこそが独自性」であり、AIの解答の方向性=自社の思想と言っても過言ではありません。
ハイブリッド検索で”どんなAIになるか”を決めるのは、この3つの軸です。
AIが「外部情報」と「自社情報」をどの比率で参照するか。
この比率こそ、企業の立ち位置と信頼戦略を象徴します。
| 優先度設計 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外部情報優先(70:30) | トレンド先導型 | 最新動向・スピード重視。スタートアップ的AI。 |
| バランス型(50:50) | 思想調和型 | 社内知識と外部知見のバランス。学習型組織。 |
| 内部情報優先(30:70) | 信頼・文化重視型 | 社内ノウハウ・理念を守る”文化AI”。 |
たとえば「業界標準をリードしたい企業」は外部寄り、「ブランドの世界観を守りたい企業」は内部寄りにチューニングします。
ハイブリッド検索では、AIが見つけた情報をスコアリングして評価します。
このスコアリングロジックに「自社の価値観」を反映させることが、独自性の源泉です。
つまり、“何を良いとするか”を明確に定義することが、AIの人格と自社の差別化を決定づけます。
Web情報は”世界の文脈”を、社内ナレッジは”自社の文脈”を表します。
ハイブリッド検索では、この2つの文脈を統合する設計が重要です。
→ 「市場動向を理念に照らしてどう解釈するか」
→ 「流行を追うのではなく、ブランドらしく答える」
この文脈の掛け合わせを制御できるAIこそ、市場における「思想的ポジション」を持ったAIです。
ハイブリッド検索の設計によって、企業は次のようなAI像を戦略的に選択できます。
| ポジション | 概要 | 向いている企業像 |
|---|---|---|
| 革新型RAG | Web情報を積極的に取り込み、新潮流を先導する。 | 新規事業・スタートアップ・研究開発系 |
| 文化型RAG | 社内理念と行動指針を核に、回答を一貫させる。 | 老舗・ブランド重視企業・教育業界 |
| 共創型RAG | 内外情報を融合し、顧客やコミュニティと共に知識を育てる。 | コミュニティ型ビジネス・CDE路線企業 |
ハイブリッド検索は、AIを「正確にする技術」ではなく、“一貫した哲学を持たせる技術”です。
そしてその哲学を作るのは、企業の理念・Vision・行動基準。
つまり、
「AIが参照する情報源」=「企業が信じる世界」
「AIが生成する回答」=「企業の未来の語り方」
Difyとn8nの連携により、DifyがAIの”価値判断”を構築し、n8nが”実際の業務行動”へ接続する。
この二層構造を持たせることで、「理念が実装されるRAG」、すなわち「哲学をもったAI」を実現できます。
RAGが知識を検索して答える時代から、AIが“自社の価値観”を理解し、自ら判断して行動する時代へ。
それが「Agentic RAG(エージェンティックRAG)」のフェーズです。
従来のRAGは「質問→検索→回答」で完結する”受動型AI”でした。
しかし、次世代のRAGは「何を調べるべきか」「どの情報を優先すべきか」を自律的に判断します。
つまり、AIが単に”知っている”存在ではなく、“考え、決め、動く”存在へと進化するのです。
これにより、RAGはもはや情報システムではなく、組織の意思決定プロセスを共に担う存在となります。
Agentic RAGは、以下の3層で構成されます。
| 層 | 役割 | 具体的な処理 |
|---|---|---|
| ① 意図層(Intent Layer) | 「何をすべきか」を判断する層 | 問題の本質を分析し、タスクを自律生成する |
| ② 知識層(Knowledge Layer) | 「どう考えるか」を定義する層 | RAG検索により、理念・ナレッジを参照 |
| ③ 行動層(Action Layer) | 「どう実行するか」を制御する層 | n8n等を通じ、外部システムと連携し実行 |
AIが本当に「自社らしい判断」をするためには、理念を”文言”ではなく“行動ロジック”に変換する必要があります。
その方法が、理念の「条件化」です。
| 理念 | 行動ロジックへの翻訳例 |
|---|---|
| 「体験で人を幸せにする」 | → 「顧客体験に関する質問では、感情語を優先検索」 |
| 「挑戦を称える文化をつくる」 | → 「新しい概念や未知の用語を排除せず提案に含める」 |
| 「誠実な関係を築く」 | → 「曖昧な回答は避け、情報源を明示する」 |
自社の狙うポジションに応じて、Agentic RAGの判断方向も変わります。
| タイプ | 判断の特徴 | 向いている企業像 |
|---|---|---|
| 分析型RAG | データや論理をもとに冷静に判断 | B2B/金融/コンサル系 |
| 共感型RAG | 感情・体験価値を重視し、文脈で判断 | サービス業/体験提供企業 |
| 探究型RAG | 未知領域に踏み込み、新しい構造を見つける | 研究開発/イノベーション志向企業 |
当社の目指すべきは「共感型×探究型」RAGです。
つまり、AIが人の感情や体験を理解し、未知の知を共創していく――それが”人とAIの共進化”のかたちです。
Agentic RAGを設計するプロセスとは、企業自身の価値観や判断軸を可視化し、再定義する作業です。
AIが理念に基づいて判断するよう設計することは、同時に「私たちは何を信じて判断しているのか」を問い直すことでもあります。
すなわちAgentic RAGとは、“AIの自律性”を通して、企業が自分の思考を深める装置”なのです。
Agentic RAGとは、「理念をAIが自分で解釈し、判断し、行動する」構造。
それはつまり、企業文化そのものをデジタル化する行為です。
この循環こそが、”人とAIの共進化”となります。