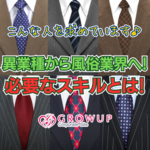Blog
歴史に学ぶリーダーシップ【第6回】足利直義
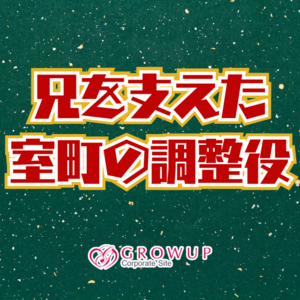
本シリーズ「歴史に学ぶリーダーシップ(日本ver)」では、日本の歴史に大きな足跡を残したリーダーたちの人生と、そのリーダーシップの特徴を探りながら、現代に活かせる学びをお伝えしています。
前回第5回(北条泰時編)では、鎌倉幕府の執権として “ 法 ” による統治を確立したリーダーシップを取り上げました。
今回は時代を下り、鎌倉幕府が滅びた後の南北朝期、足利直義(あしかが ただよし)に焦点を当てます。
兄・足利尊氏とともに室町幕府の創設期を支え、武家社会の新たな形を模索した彼の足跡から、どんなリーダーシップのヒントが得られるのでしょうか。
足利直義とは?――室町幕府の“陰の立役者”

幕府創設期のキーパーソン|足利直義(1306年~1352年)
室町幕府を開いた初代征夷大将軍・足利尊氏(あしかが たかうじ)の同母弟とされる人物です。
尊氏の盟友・腹心として活躍し、初期の室町幕府政権では実質的に行政面を司りました。
後醍醐天皇の建武政権に始まり…
元弘の乱(1331~1333年)以降、鎌倉幕府が滅亡し、後醍醐天皇による建武の新政が開始されると、兄・尊氏と直義はその軍功で大きな存在感を発揮します。
しかし、建武の新政の混乱に失望した武士層が尊氏に集まり、やがて尊氏は後醍醐天皇に反旗を翻し、独自の武家政権を樹立していくことに。
室町幕府成立と直義の役割
1336年頃から尊氏が“征夷大将軍”として武家政権(室町幕府)を築く過程で、直義は主に政治・行政を担当します。
“ 兄が総大将 ” として軍事・武家の統率を担う一方、“ 直義は政務官 ” のような立ち位置で幕政全般を支えたのです。
政務の才覚と公正さ――“良識派”としての直義

建武式目と法整備への関心|武家社会の秩序づくり
足利直義は、武士の社会秩序を整えるための法整備を重視した人物として知られます。
建武政権から室町幕府の黎明期にかけて、複雑に絡む所領問題や新旧武士の待遇問題など、根深い対立が絶えませんでした。
公正な裁定を求める姿勢
直義は、乱世だからこそ “ 武力一辺倒 ” ではなく、“ 公正・公平 ” な裁判・行政ルールを確立する必要があると考えていたようです。
鎌倉幕府でいえば御成敗式目的な武家法の整備にも関心を寄せ、建武式目(後醍醐天皇の方針を取り入れた法令)や室町幕府独自の“先例重視”の姿勢を尊重するなど、法による秩序を模索しました。
幕府内部での評価|“誠実な行政官”のイメージ
実際、同時代の武家や公家の一部から、直義は「誠実で信頼に足る人物」と評価されることが多かったようです。
兄の尊氏が豪胆で武力に秀でた “ カリスマ将軍 ” だとすれば、直義は穏健かつ法理を重んじる “ 文官タイプ ” でした。
大義名分を重んじる
南北朝の動乱期において、各地の武士は実利(所領安堵など)を求めて尊氏側に味方したケースが多いですが、直義は朝廷の権威や武家社会の伝統も無視しない、いわばバランス感覚を持った官僚肌のリーダーでした。
“観応の擾乱”――兄弟間の衝突と直義の失脚
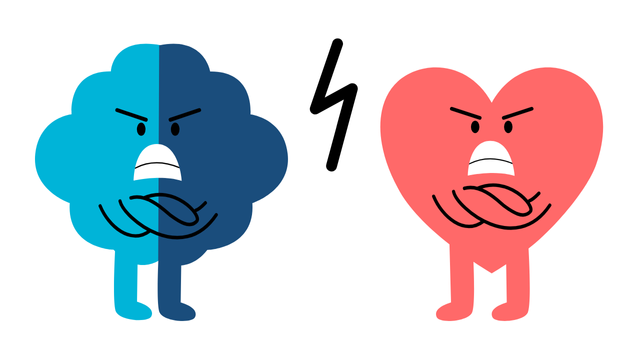
高師直との対立|室町幕府草創期の主導権争い
尊氏の有力家臣であった高師直(こう の もろなお)は、抜群の軍功と強烈なリーダーシップで幕政の実権を握ろうとします。
対して直義は、師直の急激な専横ぶりや強硬姿勢を警戒し、衝突を深めていきました。
二人の不和が幕府を揺るがす
幕府内部の権力闘争は “ 観応の擾乱(かんのうのじょうらん)” と呼ばれ(1350~1352年頃)、ついに直義と高師直は互いに武力行使の段階へ突入。
尊氏自身もどちらを支持するのか揺れ動き、室町幕府は深刻な分裂状態となります。
兄・尊氏との対立、そして直義の死|対立の行き着く先
当初は兄弟で協力関係にあった尊氏と直義ですが、幕府内の路線対立や利権問題、さらに周囲の勢力に翻弄される形で仲違いが決定的に。
やがて尊氏派が優勢になると、直義はやむなく出家して政治の舞台から退きます。
不審な最期
1352年、直義は急死します。
病死とされていますが、一説には尊氏もしくはその周辺が “ 毒殺 ” を図ったとも言われ、真相は定かではありません。
結果的に、室町幕府創設を支えた直義は、権力闘争の渦中で悲劇的な幕引きを迎えました。
足利直義のリーダーシップポイント

公正な法と秩序を重視
戦乱の時代であっても、“法や道理に基づく裁き”を目指し、乱世における武家政権の統治基盤を築こうとした。
現代でも、混乱期こそルールに基づく公正な体制構築が組織運営を安定させる大きな鍵になります。
調整型のリーダーシップ
強権的に進めるのではなく、大義名分や先例、関係者の意見を重んじる“調整型”のリーダー像。
大胆さに欠けるという批判も受けやすい一方で、多様な利害が交錯する状況では、秩序を保ちやすい方法ともいえます。
兄弟・部下とのパワーバランス管理の難しさ
兄・尊氏という “ カリスマ ” と、有力家臣・高師直の“専横”の狭間でバランスを取ることが求められた直義。
結果的には内部対立を制御できず、自身が追い込まれてしまったところに、組織内部の権力バランスを見誤った面がうかがえます。
人望と政治手腕のジレンマ
直義は誠実さや公正さで多くの支持を集めた一方、強烈なカリスマや圧倒的武力を持つわけではなく、最後は内紛に飲み込まれる形に。
リーダーが掲げる理想や正義があっても、周囲とのパワーバランスや実行力が備わっていないと、改革の継続は難しいことを示す例ともいえます。
現代に活かす足利直義の教訓

混乱期だからこそ “ 法 ” や “ 秩序 ” が重要
企業や組織の急速な成長期・変革期では、どうしてもトップダウンや実力者の独裁が進みがち。
しかし、長期安定を考えるなら、直義が目指したような公正なルールと手続きの整備が欠かせません。
調整型リーダーの強みと弱み
強硬路線に走らず、公平性を優先し、周囲の声を丁寧に聞く――それは大きな美点であり、多くの人からの信頼を得られます。
しかし一方、利害対立が激化した際に迅速な決断や強制力が働きにくい面も。
組織トップとしては、状況に応じた “ 決定力 ” も不可欠です。
周囲のパワーバランスに敏感であること
たとえ自身の考えが公正であっても、強い権力をもつカリスマ(尊氏)や有力、有力家臣(師直)の動き次第で、一気に情勢が変わってしまいます。
適切なブレーンとの連携や権限の最適化を怠れば、上意下達が機能せず内紛に陥る危険もあります。
まとめ
足利直義は、室町幕府が揺籃期(ようらんき)にあるなかで、兄・尊氏を支えながら武家政権の行政・法整備を推進した人物です。
豪胆な武力やカリスマ性こそ持たなかったかもしれませんが、公正さと誠実さを武器に、武家社会に秩序を根付かせようとした点は高く評価されます。
しかし、“ 観応の擾乱 ” に象徴される内部抗争が激化する中、直義は最終的に組織のパワーバランスを失い、悲劇的な退場を余儀なくされてしまいました。
このエピソードは、以下の要素が互いに影響しあい、“ 理想 ” や “ 正義 ” だけでは乗り切れない現実の厳しさを如実に示しています。
・リーダーの人格的な信頼(誠実さ・公正さ)
・組織を運営するシステム(法整備・権力配置)
・実権の行使というリアルなパワーバランス(カリスマや有力者との対立・協力関係)
現代でも、組織内の権力関係や法整備・ルールメイクの重要性は変わりません。
足利直義の奮闘と挫折は、リーダーシップの多面性を考えるうえで大きなヒントとなるでしょう。
次回以降も、歴史上のさまざまなリーダーの物語を通じて、現代に通じるリーダーシップの本質に迫っていきます。
どうぞお楽しみに!