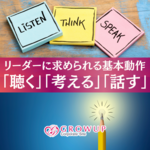Blog
労務管理に活かせる4つの組織論
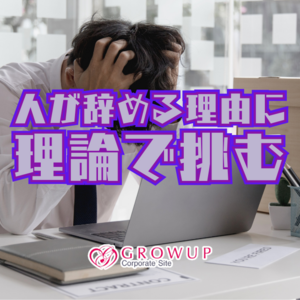
「人が辞める」「人が育たない」「人がついてこない」――
そんな職場の悩みを根本から見直したいとき、参考になるのが組織論や動機づけ理論です。
単にルールを決めたり、給与を上げたりするだけでは解決できないのが“人”の問題。
だからこそ、「なぜ人は働くのか?」「どうすれば納得して動くのか?」という問いに向き合う必要があります。
今回は、現代の労務管理にも役立つ4人の組織論者の思想を紹介し、それぞれの理論がどのように現場で活かせるかを解説します。
目次
チェスター・バーナード「協働意思」と「受容の条件」
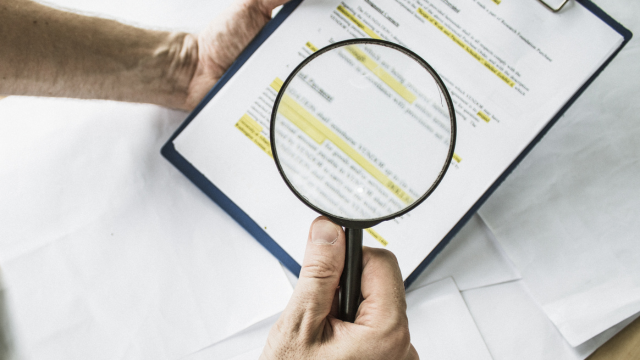
すでにご紹介したバーナードの理論は、「人は命令で動くのではなく、“納得”で動く」という点に本質があります。
「共通目的・協働意思・意思疎通」の3要素により、人間的な組織運営を重視する理論です。
現場での活用ポイント
・指示ではなく、理解と共感を得るコミュニケーション
・感情のつながりを育む職場環境づくり
・「なぜそれをするのか?」という目的の共有
ダグラス・マグレガーのX理論・Y理論

マグレガーは、管理者が部下に対して持つ前提として、2つの考え方を示しました。
| 理論 | 特徴 | 管理スタイル |
|---|---|---|
| X理論 | 人は本来怠けるものであり、監視と強制が必要とされる。 | トップダウン、命令管理型 |
| Y理論 | 人は本来仕事にやりがいを見出し、自主性を持って働く。 | 自律・参加型マネジメント |
現場での活用ポイント
・部下を「信じて任せる」ことで能力が引き出される
・エンゲージメントの高い組織は、Y理論型が多い
・あなたの管理スタイルはX?Y?と内省する材料にも
フレデリック・ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」

ハーズバーグは、満足と不満は別の要因によって起こると説きました。
| 要因 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 衛生要因(不満を防ぐ) | 整っていないと不満になるが、整っていても満足にはならない | 給与、労働環境、福利厚生 |
| 動機づけ要因(満足を生む) | あると人はやる気になる | 達成感、承認、成長の機会、責任感 |
現場での活用ポイント
・給与UPだけでやる気は出ない
・成果を認め、成長の機会を与えることがやる気を生む
・「満足」を生むには、内発的動機へのアプローチが必要
クリス・アージリスの「未熟→成熟モデル」

アージリスは、人間が組織の中で「未熟な存在から成熟した存在へと成長していく」ことが重要だと説きました。
| 発達段階 | 特徴 |
|---|---|
| 未熟 | 依存的、受け身、反応的 |
| 成熟 | 自律的、積極的、創造的 |
現場での活用ポイント
・指示待ち社員を育てるのではなく、「考えて動く人材」に育てる
・「裁量を与える」ことが、成長への第一歩
・教育・評価・任せ方の見直しが必要
まとめ|理論を知ることで、現場が変わる

| 理論家 | キーワード | 主な貢献 |
|---|---|---|
| バーナード | 協働意思・受容の条件 | 人間的な組織構築 |
| マグレガー | X理論・Y理論 | 管理者のスタンスを問い直す |
| ハーズバーグ | 衛生・動機づけ要因 | モチベーション設計 |
| アージリス | 成熟モデル | 成長支援と自律型人材育成 |
これらの理論は、どれも机上の空論ではなく、人を理解し、組織を強くするための実践知です。
「人が辞めない組織」「人が育つ職場」「人が協力するチーム」を作るには、まず人間理解から始めてみませんか?