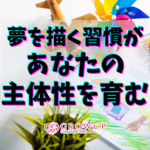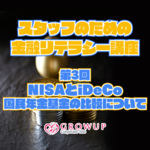Blog
意思決定の心理を紐解く(第2回)|推論のはしご〜思考が現実をつくるメカニズムを可視化する〜
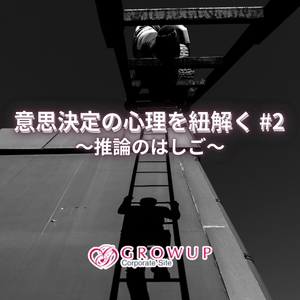
私たちは、目の前の現実をそのまま見ていると思っています。
しかし実際は、「選んで」「意味づけて」「解釈して」ようやく“世界”を構成してます。
この無意識のプロセスこそが、「推論のはしご(Ladder of Inference)」と呼ばれる思考の階段です。
推論のはしごとは?

この概念は、組織心理学者クリス・アージリスによって提唱されたモデルで、人がどのようにして事実から行動に至るかを示す図式のこと。
それが、以下のステップです。
・観察(現実・出来事)
・データの選択(自分が注目した情報)
・解釈(意味づけ・仮説)
・前提づけ(信念や価値観の補強)
・結論・信念形成
・行動(発言・選択・態度など)
例で理解してみる

たとえば、あなたが会議中に同僚があくびをしていたとします。
観察:「Aさんがあくびをした」
選択:「自分が発言していた時にあくびをした」
解釈:「私の話が退屈だったのかも」
前提:「Aさんは私の意見に関心がない」
信念:「私はこのチームで軽視されている」
行動:「もう発言しないでおこう」
—— でも、実際にはただ眠かっただけかもしれません。
この“はしご”の怖さ

推論のはしごは非常に速く、そして自動的に登ってしまいます。
しかも、自分の信念を強化する情報だけを選びがち(確証バイアス)なので、一度できた思い込みはなかなか修正されません。
これが、誤解・対立・偏見・自己否定といった問題の温床になります。
つまり、推論のはしごは私たちの「現実の感じ方」そのものを歪めている可能性があるのです。
はしごを“降りる”技術

重要なのは、この思考の階段を意識的に降りること。
そのための問いかけを紹介します。
・私が今見ている“事実”は、どこまでが客観的か?
・他にどんな解釈がありうるか?
・なぜその意味づけをしたのか?
・自分の信念がこの状況にどう影響しているか?
・それによって、どんな行動を選ぼうとしているか?
はしごを“編集”できるようになると…

このモデルに気づけるようになると、「思考=自分」ではなく、「思考は編集できるもの」という認識が生まれます。
感情に振り回されず、他者とも自分自身とも、丁寧で建設的な対話ができるようになります。
今日、あなたが無意識に登ってしまった“はしご”は何ですか?
一日ひとつでもいいので、「あのとき自分はどんな解釈をしたか」をメモしてみましょう。
📘 次回予告
意思決定の心理を紐解く(第3回)|メタ認知の技術〜自分の思考に気づく“もう一人の自分”を育てる〜
推論のはしごに気づく力、つまり“自分の思考を観察する力”が「メタ認知」です。
次回はそのメタ認知をどう鍛えるか、日常で使える実践的アプローチを紹介します。