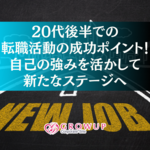Blog
AIエージェントは誰でも作成可能ですか??

最近、「AIエージェントって誰でも作れるようになったらしいよ」という声をよく耳にします。
確かに、ツールの進化により専門知識がなくてもAIを作ることは可能になりました。
しかし、“何を作るか”よりも大切なのは、AIエージェントによってどのような“知の構造”を生み出せるかです。
言い換えれば、「現場の知見や判断基準をどれだけAIに継承・循環させられるか」こそが、業務改善の成否を分けるポイントなのです。
本記事では、「誰でも作れる時代」だからこそ見落としがちな、AIエージェント導入の落とし穴と、成長するナレッジ基盤の構築法を4つの視点からお届けします。
目次
AIエージェントは誰でも作成可能ですか? → YES

はい、AIエージェントは誰でも作成可能な時代になりました。
ノーコードツールやテンプレート、対話式のガイドが充実しており、専門知識がなくても「それっぽいエージェント」は作れるようになっています。
たとえば、以下のようなツールが代表的です:
- ChatGPTのカスタムGPT(OpenAI)
- Dify、Flowise などのノーコードLLMツール
- n8n、Zapier などの自動化ツールとの連携
数時間あればチャットボット型のAIは完成します。
AIエージェントで誰でも業務改善できますか? → NO

残念ながら、AIエージェントを作れる=業務改善できるとは限りません。
よくある失敗例は以下の通りです:
- 目的が曖昧で「何のためのエージェントか」が不明確
- 現場の業務プロセスを理解せずに「とりあえず作ってみた」
- 質問精度や情報の信頼性が低く、使われないエージェントに
つまり、作ることより「使われ続けること」の方が難しいのです。
AIエージェントの本質と業務改善のいろはを抑えること

業務改善にAIエージェントを活かすには、以下の3点を押さえる必要があります。
① 問題設定:何を改善したいのか?
- 業務のどこにムダ・属人化・判断の負担があるか?
- AIが入ることで何が軽減されるか?
② ナレッジ設計:何を学ばせるか?
- FAQ、業務マニュアル、判断基準などの形式知を整備
- 暗黙知を言語化し、AIが「現場の思考」を模倣できるように
③ 運用設計:どう進化させるか?
- フィードバックの仕組みを用意し、AIを継続的にアップデート
- 「育てる文化」を社内に醸成する
この3点が揃ってはじめて、「AIエージェントによる業務改善」が実現します。
優秀なツールでも、使い方を誤ると単なる浪費

AIツールは使い方次第で“武器”にも“浪費”にもなります。
たとえば以下のようなケースは、注意が必要です。
| ツールの使い方 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|
| ナレッジ登録 | よくある質問や対応フローを整理してAIに学習 | コピペしたマニュアルを丸ごと読み込ませただけ |
| チャット設計 | 段階的に選択肢や分岐を設けて丁寧に誘導 | 「何でも聞いてください」だけの曖昧な設計 |
| フィードバック | 利用者から改善要望を収集して再学習 | つくって終わり、1年放置 |
AIは万能ではなく、「設計と運用がすべて」です。
最初に時間をかけて土台を作っておけば、あとで驚くほど効果を発揮します。
ここでいう設計はアプリの設計ではなく、オペレーション上にどう組み込むかということです。
AI×人のハイブリットなオペレーションを追求していきましょう。
AIエージェントは、単なる応答ツールではなく、「組織知を蓄積・共有・進化させるハブ」として設計すべきです。
▼たとえば以下のようなナレッジ循環構造が理想です:
- ① 現場の判断や対応ログがAIに蓄積され
- ② AIが標準化・整理された対応を再提示し
- ③ 使うたびにフィードバックが入り
- ④ さらに現場にフィードバックされる
この循環構造を意識することで、AIは “自動化ツール” から “知的共進化パートナー” へと進化していきます。
おわりに
AIエージェントは確かに誰でも作れます。
しかし、業務改善を実現するには、現場のナレッジをどう構造化し、循環・進化させるかという視点が欠かせません。
その意味で、日本発のナレッジマネジメント理論「SECIモデル」(野中郁次郎・一橋大学名誉教授)を一度学んでおくことを強くおすすめします。
▼SECIモデルとは:
暗黙知と形式知をらせん状に変換しながら、組織的な知識を創造していくプロセスモデル。
- S(Socialization/共同化)
- 現場の経験や感覚を共有
- E(Externalization/表出化)
- 言語化・マニュアル化
- C(Combination/連結化)
- 既存の知識と統合し構造化
- I(Internalization/内面化)
- 教育・実践を通じて再び暗黙知化
このSECIモデルにAIエージェントを組み込むことで、“知の進化エンジン”としてのAI”を設計できます。
単なる効率化ではなく、現場の学びとナレッジを資産に変える力として、AIを活用していきましょう。