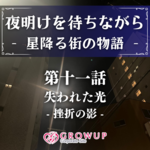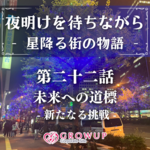Blog
電気を“買う”から“つくる”へ。V2H・蓄電池・補助金の最新事情

電気代の高騰や災害時の停電リスク。
私たちの生活を支える「電気」を、もっと安心して・もっと自由に使えたら…。
そんな暮らしを実現する鍵が、自宅で電気を“つくる・ためる・つかう”仕組みです。
近年注目されている V2H(Vehicle to Home) は、EV(電気自動車)を「走る蓄電池」として活用し、家庭の電源に変える技術。
さらにソーラーパネルや家庭用蓄電池と組み合わせれば、自宅そのものが“スマート発電所”になります。
しかも今は、国や自治体の補助金制度を使えば導入コストを大きく抑えることが可能です。
本記事では、V2Hの仕組みや有名メーカー、補助金の申請時期、さらに最大で250万円規模にもなる支援制度についてわかりやすく解説します。
目次
V2Hとはなに?ニチコンとオムロンについて

V2H(Vehicle to Home)とは、EV(電気自動車)やPHEVの大容量バッテリーを家庭用電源として利用できるシステムのこと。
停電時には「非常用電源」として家を守り、平常時には「安い時間に充電して高い時間に給電」という節電効果も期待できます。
注目のV2Hメーカー:ニチコンとオムロン
ニチコン
V2H市場をリードするメーカー。主力製品「EVパワー・ステーション」は導入実績が多く、補助金対象としても幅広く登録されています。安定感と信頼性に定評があり、「まずは安心のV2Hを」と考える方に選ばれやすいブランドです。
オムロン
特徴は ステップアップ設計。
- まずはV2H単体から導入し、将来的に蓄電池 → ソーラーパネルと拡張可能
- 最初からフルセット(V2H+蓄電池+太陽光)を導入することも可能
- ライフプランや予算に合わせて段階的にエネルギーシステムを育てられる
最新ニュースによると、新たに トリプル蓄電システム「KPTPシリーズ」 も追加発表され、さらに選択の幅が広がりました。
さらに、オムロンの「マルチV2Xシステム」 は、2025年度補正・2026年度(令和6年度補正・令和7年度)CEV補助金対象に登録済みです。新たなスケジュールは以下の通り:
- 申請期間:2025年7月25日~9月30日
- 交付決定時期:9月~11月下旬
- 実績報告期限:2026年1月30日
近年は 年々省スペース型のV2Hがリリースされ、都市部の限られた設置スペースでも容易に導入できるようになったことも大きな進化です。
マンションの駐車場横や狭小住宅の庭先など、従来は設置が難しかった環境でも対応できるケースが増えています。
ソーラーパネル+EV+V2H、さらに蓄電池を足すと・・・

V2H単体でも「停電に強い家」になりますが、ソーラーパネル+EV+V2Hを組み合わせると、昼間に太陽光で発電 → 余剰をEVに充電 → 夜はEVから家庭へ給電という循環型の暮らしが可能になります。
さらに、家庭用蓄電池を加えれば、昼夜を問わず電力を効率よく回せるようになり、以下が同時に実現します:
- 電気代のピークシフト(安い時間に充電し、高い時間に使用)
- 停電時のバックアップ強化
オムロンのトライブリッド蓄電システム
これは「V2H・太陽光・蓄電池」をバラバラに設置するのではなく、1台のパワーコンディショナーで統合管理できる仕組みです。
- 設置工事がシンプルになりコスト削減に寄与
- 将来的にEV導入や蓄電池追加を考えている家庭でも柔軟に対応
- 補助金の対象機器としても登録済みで安心
そして何より大切なのは、“自宅の電気を自分でマネジメントする”という思想です。
電気を「買う」だけの時代から:
- つくる(ソーラーパネル)
- ためる(蓄電池・EV)
- つかう(家庭)
- そなえる(停電時の非常用)
トライブリッドを選べば、こうした電力マネジメントをシンプルに実現でき、段階的な導入も最初からのフルセット導入も柔軟に対応可能です。
つまり、トライブリッドを選べば「段階的に導入」も「最初からフルセット導入」も自由自在。
家庭の電力システムをスマートにまとめたい方にとって、大きな選択肢となります。
補助金の申請時期はいつぐらい?何が必要!?
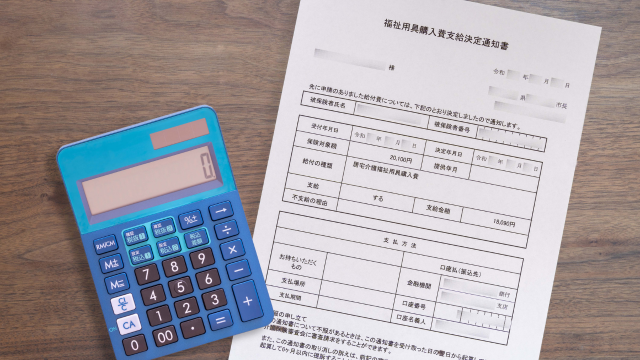
国の「CEV補助金(V2H充放電設備導入補助事業)」は、毎年度ごとに受付が行われます。
例年のスケジュールは、春(4月〜6月頃)に第1期、夏〜秋に第2期 が設けられる流れです。
補助金申請に必要なもの
- EVまたはPHEVの保有(あるいは購入予定の契約書)
- 登録されたV2H機器の導入見積り
- 住民票や車検証などの証明書類
- 設置後5年間の使用義務や譲渡禁止の遵守
⚠️ 人気が高く、予算が尽きれば早期終了するため、年度初めの申請が有利です。
そして見逃せないのが、この補助金が「自宅の電気を自分でマネジメントする思想」そのものを国が推奨しているという点です。
EVや蓄電池を「非常用バッテリー」としてだけでなく、日常の電力マネジメントに活用する
太陽光発電やV2Hを組み合わせて、エネルギーを家庭で循環させる
災害に強い家づくりを同時に進める
こうした考え方を広めるために、国は数十万円規模の補助金を用意しています。
つまり、補助金の申請とは単なる「お得な制度活用」ではなく、未来の暮らし方を国と一緒につくっていく取り組みでもあるのです。
さらに自治体によって差が大きいのも特徴です。
- 東京都:新築住宅へのソーラーパネル設置が義務化され、あわせてV2H・蓄電池への補助金も手厚く用意されています。太陽光+蓄電池+V2Hをまとめて導入すれば、国の補助金に上乗せされ、数十万円規模の追加支援を受けられるケースもあります。
- 大阪府・大阪市:義務化はなく、現状ではV2Hや太陽光発電への大規模補助は限定的。導入を考える場合は、国のCEV補助金をどう活かすかが中心になります。
👉 つまり、住んでいる地域によって「制度活用のしやすさ」に差があるため、国の補助金+自治体の上乗せを確認するのが賢い選択です。
EV+ソーラーパネル+V2H+蓄電池で補助金は最高額でいくらもらえるの?

| 項目 | 国の補助金 | 東京都(上乗せあり) | 大阪府・大阪市(上乗せなし) |
|---|---|---|---|
| V2H本体+工事費 | 最大65万円 | 最大65万円 | 最大65万円 |
| ソーラーパネル | ― | 50〜80万円前後(義務化と連動し補助) | 市町村によって数万円〜数十万円 ― |
| 蓄電池 | ― | 最大60〜70万円前後 | ― |
| EV購入 | 最大85万円 | 最大85万円 | 最大85万円 |
| 合計補助額 | 約150万円 | 最大250万円前後 | 約150万円+10~15万 |
東京都は「ソーラーパネル義務化」とあわせて蓄電池・V2Hへの支援も厚く、実際には 250万円前後 まで補助が積み上がるケースがあります。
特に「EV補助金(最大85万円)」+「V2H(65万円)」+「ソーラー&蓄電池への都の補助(100万円前後)」を合算するとその規模になります。
ソーラーパネルの設置+畜電池+V2Hで合計300万ほどEVを450万とすると750万のうち、東京では、1/3は補助金がいただけるということになります。
V2H設置状況(日本全国)
2024年時点での累積導入数:約5万台
経済産業省の資料によると、2024年時点で日本国内のV2Hシステムは累計約5万台に達していると推定されています。
今後の目標と展望
- 2030年までにV2Hシステムをさらに3万台設置する目標が発表
- 普及を後押しする施策が今後も継続される見込み
まとめ
EV+V2Hで変わる家庭と社会の電力活用
-
EVは「走る蓄電池」
V2Hと接続すれば、「家の一部」「街の電力インフラ」として活用可能。 -
電気料金とEV運用の最適化
夜間の安い電気で充電 → 昼間のピークに放電。AI+HEMSによる自動制御で効率的に電気代削減+系統負担軽減。 -
再エネとの組み合わせ
EV+V2Hで電気を蓄えて夜や外出時に利用可能。 -
社会全体への波及効果
各家庭に「バッテリー容量40〜60kWh」が普及 → 地域単位でネットワーク化すればVPP(仮想発電所)となり電力ピークシフトに貢献。
EVは「車」+「家の電池」+「地域の電源」としての潜在力を持つ。その実現には家庭レベルの電力マネジメント(AI+HEMS+V2H)が不可欠。2030年代には自宅での電気マネジメントが当たり前の時代になりそうです。