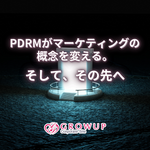Blog
「人」と「組織」の関係性について偶発的計画性と創発戦略
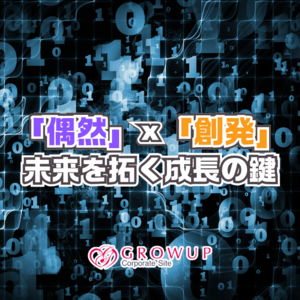
目次
ミンツバーグの創発戦略とは!

「創発戦略」は、計画的に策定された戦略が常に実行されるわけではなく、環境や状況の変化によって自然発生的に形成される戦略を回避します。
計画的戦略、実行過程で変更されることが多く、結果として「意図的でない結果(Unintended Consequences)」が生じます。
このプロセスで生まれる創発戦略は、組織が環境に適応し、柔軟に対応する力を発揮する手法です。
ミンツバーグの理論の重要性は、完璧な計画を追求するよりも、組織が環境と「対話」し、変化する状況に対処しながら進化する必要があることを示している点にあります。
このように不確実性が高い時代では、創発戦略は、変化に即応するための重要なフレームワークとされています。
クランボルツの計画的な偶然性とは?
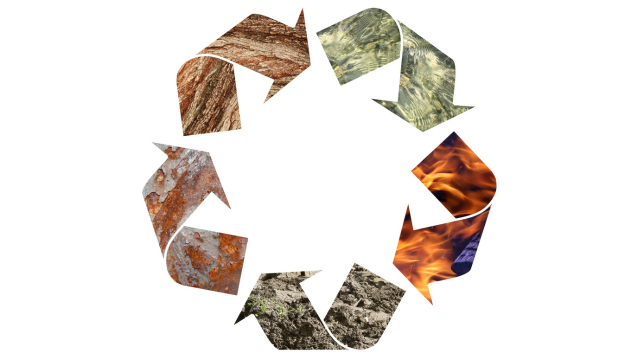
ジョン・クランボルツが提唱した「計画的な偶然性(Planned Happenstance)」は、個人が予期せぬ偶然の出来事をチャンスに変える力を持つことを目的としたキャリア理論です。
具体的には、以下のような要素が必要です。
好奇心:新しい経験を受け入れる
持続性:困難な状況でも続ける
柔軟性:計画を変更する柔軟性
楽観性:将来の可能性を信じる
冒険心:リスクを恐れず挑戦
この考え方は、個人がキャリア形成やライフプランにおいて不確実性を受け入れ、それを成功の源泉にする方法論を提供します。
「環境と相互作用」2つの概念を統合させること

人と組織の成長スピードが二乗変化していきます。
創発戦略と計画的な偶然性は、一見異なる領域で語られる理論ですが、そこには共通点があります。
それは「環境との相互作用」による成長の促進です。
創発戦略との両方が、予測不可能な状況をポジティブな結果に変えるために、環境に取り組み、またその影響を受けるプロセスを共有しています。
具体的には次のようなメカニズムが働きます。
偶然の偶然を起点とした戦略の創造
・個人が偶然のチャンスを活かすことで、組織にも新しい方向性が生まれる。
・組織が柔軟に対応することで、個人が新しいスキルや視点を身につける。
それぞれのフィードバックループ
個人と組織があらゆる影響を与えることで、成長の連鎖が起こる。
このように、相互作用による統合は、成長の「掛け算」が可能になります。
偶発的計画性と創発戦略の2階建てモデル「適応的共深化モデル」
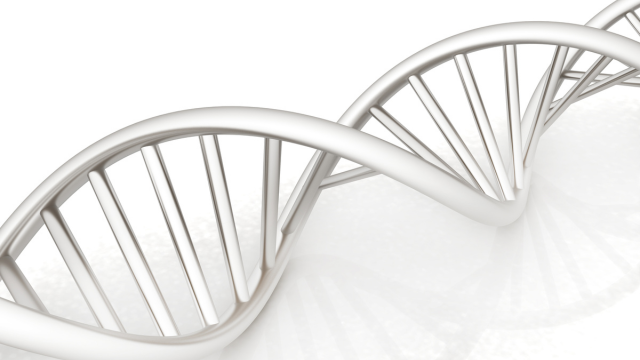
このブログで提案するのが、「偶発的計画性」と「創発戦略」を融合させた2階建てモデル「適応的共深化モデル(Adaptive Co-Enhancement Model)」です。
個人レベル – 計画的な偶然性
・個人の従業員が環境からの刺激に対して学習し、適応する
・個人の気づきや発見が生まれる場
・キャリア発達を通じた個人の成長
・好奇心やリスクテイキングなど、個人の特性が発揮される
組織レベル – 創発戦略
・個人の学びと発見が組織レベルで統合される
・ボトムアップの知見が組織の戦略として結実
・組織文化と認証を通じた学習の共有
・個人の適応能力が組織の適応力として昇華
この2階建てモデルの特記事項
相互作用の理解
・個人の成長が組織の成長を支えていく
・組織の変化が個人の成長機会を生み出す
生命体としての組織観
・個人の細胞(個人)の活性が組織全体の健康度を決定
・環境適応における個と全体の有機的な関係性
成長戦略への示唆
・個人の学習能力向上が組織の戦略的柔軟性を高める
・創発を超える組織文化と個人の自律性のバランス
このモデルは、人材育成戦略と経営戦略を統合的に検討する上で、有効なフレームワークになりそうです。