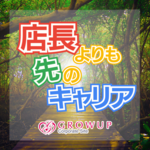Blog
米価の高止まり!?高騰かそれとも適正価格か!?
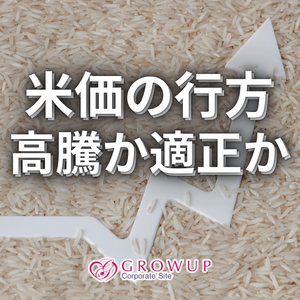
目次
米の消費量は年々減少、それに伴い作付け面積も減少傾向へ
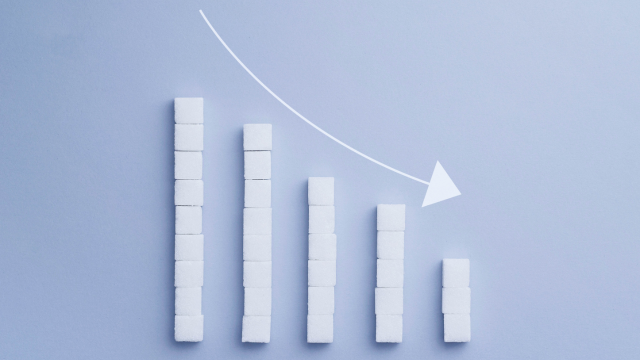
日本人の主食であるお米ですが、その消費量は年々減少しています。
年間消費量の変化
・1960年代:118kg(1人当たり)
・現在:50kg台
消費量減少の主な要因
・食生活の多様化(パン・麺類の消費増加)
・ライフスタイルの変化(外食・中食の普及)
・若年層の米離れ
この消費減少に伴い、米の生産面積も縮小しています。
作付面積の減少要因
・農家の高齢化 → 後継者不足が深刻化
・耕作放棄地の増加 → 農業衰退の懸念
・生産コストの上昇 → 農業の採算が合わなくなっている
しかし、消費量が減少している一方で、米価は高止まりしています。
では、なぜこのような現象が起こっているのでしょうか?
現在の米価の高騰は、複合的な要因によるもの

最近の米価上昇には、さまざまな要因が絡み合っています。
供給側の要因
生産量の減少 → 作付面積縮小・農家減少・不作
政府の備蓄米放出の減少 → 市場流通量の調整
需要側の要因
外食需要の回復 → コロナ明けの飲食業界の仕入れ増
インバウンドの影響 → 訪日外国人の和食需要拡大
市場の影響
円安・物流コスト増 → 海外輸出の増加&輸送コスト上昇
投機的な買い占め → 卸売業者の在庫確保・流通量制限
特に、コロナ禍の影響で落ち込んでいた外食産業の回復や、訪日外国人の増加により、業務用米の需要が急増しています。
また、円安の影響で海外輸出が増加し、日本国内の米供給にも影響を与えています。
はたして今までの米価は適正だったか?米農家の時給は100円

ここで一つの疑問が浮かびます。
「今までの米価は本当に適正だったのか?」
日本の農業は長年、「安い米」を前提に価格が抑えられてきました。
その結果、米農家の時給はわずか100円程度という厳しい現実があります。
米農家の収益の現状
・1年間の労働に対して数十万円の収益しか得られないケースもある
・機械・肥料のコスト上昇により、価格競争が激化
・価格が抑えられた結果、適正な収益を確保できない状況が続いてきた
しかし、最近の米価上昇は、農家にとっては適正な価格に近づく兆しと捉えられています。
消費者 vs 農家の視点の違い
・消費者にとっては「値上がり」
・農家にとっては「適正価格への是正」
農業の持続可能性を考えれば、適正な価格調整が必要かもしれません。
今後の農業政策は、大規模事業化・海外輸出・自動化・ドローン技術・遠隔化

持続可能な農業のためには、以下の施策が求められます。
農業の大規模化と企業参入
・効率的な生産体制の確立
・農業のビジネスモデル化
海外輸出の拡大
・日本米のブランド価値向上
・高価格帯市場への戦略的輸出
スマート農業の推進
・自動化・AI技術 → スマート農業による生産性向上
・ドローン・遠隔化 → 労働負担の軽減
輸出戦略の強化
・和食人気を活かした販路拡大
・政府の輸出支援政策の活用
特に、スマート農業の導入が重要視されています。
日本の米文化を世界へ発信する必要性

世界的な和食ブームの広がり
・寿司・おにぎり・和食の中心は米
・日本の高品質な米を世界に発信するチャンス
米関連ビジネスの海外展開事例
✅ おむすび権米衛(アメリカ・フランス)
✅ こめこめCLUB(タイ)
✅ ハナミズキ・カフェ(ニューヨーク)
✅ 佐賀冷凍食品(香港・シンガポール)
✅ 農事組合法人金塚(新潟・輸出開始)
日本のブランド米を海外生産する動きもあり、例えば、台湾での新潟コシヒカリの現地生産が進められています。
米は世界の主食の一つ
・世界人口の50%、約35億人が主食として米を食べている
・栄養価・保存性・流通インフラの発展により、さらなる可能性を秘めた作物
日本の食文化を守る取組は、生産者と消費者の温度差を解消すること

「お米が高い」 vs 「やっと適正価格」
消費者:「お米が高い…」
農家:「やっと適正な価格になった」
この温度差をどう解消するかが、今後の課題となります。
消費者と生産者の歩み寄りが必要
・持続可能な農業を支える仕組みを構築
・適正価格での購買を通じて、農家を支援する意識を醸成
まとめ
📌 米価の高騰は単なる「値上がり」ではなく、農業の未来を左右する問題
📌 適正価格での取引が、農業の持続可能性を支える
📌 消費者と生産者が歩み寄ることで、日本の米文化が守られる
今後も、日本の米と食文化を大切にしていきましょう!