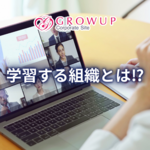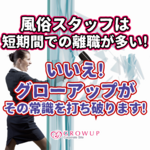Blog
【MBA × 現場思考⑪】市場ポジションと戦略的アプローチ──リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャーの視点
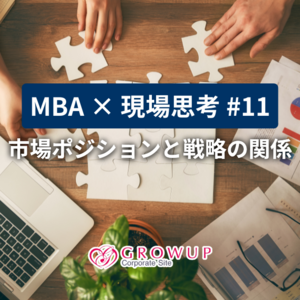
業界における市場のポジションと戦略的アプローチの考察
企業が市場で持続的な競争優位を築くためには、自社のポジションを正確に把握し、それに応じた戦略を策定・実行することが不可欠です。
市場における企業の立ち位置は、一般的に「リーダー」「チャレンジャー」「フォロワー」「ニッチャー」の4つに分類され、それぞれ異なる戦略的アプローチが求められます。
本稿では、これらの市場ポジションに基づく戦略の特徴を概観し、特に自動車業界におけるトヨタ自動車の「全方位戦略」を取り上げます。
目次
業界における市場のポジションはおよそ4つに分類される
マーケティングの大家、フィリップ・コトラーは、企業の市場における競争地位を以下の4つに分類しています。
これらの分類は、企業が自社の立ち位置を理解し、適切な戦略を策定するための指針となります。
リーダーの戦略とチャレンジャーの戦略の対比

リーダー企業は、市場全体の拡大を図りつつ、自社のシェアを維持・拡大する戦略を採ります。
具体的には、製品の多様化や価格戦略、流通チャネルの強化などが挙げられます。
一方、チャレンジャー企業は、リーダー企業との差別化を図りながら、市場シェアの拡大を目指します。
新製品の投入やマーケティング戦略の革新、価格競争などを通じて、リーダー企業に挑戦します。
- ❶ 市場規模拡大・・・市場が拡大した場合、もっとも恩恵を受けるためユーザ拡大のための投資を行う
- ❷ シェア拡大・・・体力に物を言わせて価格競争を仕掛ける
- ❸ シェア維持・・・独占禁止法を避けるため、通常は維持する戦略をとる
- ❶ リーダーとの直接対決・・・同じ領域で勝負する
- ❷ 背面攻撃・・・リーダーが強化していない領域で仕掛ける
- ❸ 後方攻撃・・・自社よりも小さなシェアの企業と勝負し奪う(ランチェスター戦略)
このように、リーダーとチャレンジャーは、それぞれの立場に応じた戦略を展開し、市場での競争を繰り広げています。
フォロワーの戦略変更のタイミングとニッチャーの市場分離
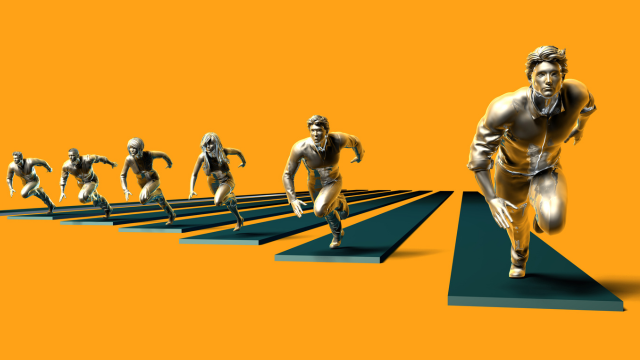
フォロワー企業は、リーダーやチャレンジャーの動向を注視し、リスクを最小限に抑えながら市場に追随します。
しかし、市場環境の変化や新たな機会の出現により、戦略の見直しや転換をする場合があります。
フォロワー企業がノウハウを貯め、シェアを徐々に拡大、チャレンジャ―やリーダーに変化する場合、例として白物家電業界でのハイセンス、モニター市場でのLGなどが挙げられるでしょう。
初めは日本市場に安価なモデルを展開し、そのハイエンドモデルなどを拡充させ、シェアを拡大に成功しています。
日本企業では、アイリスオーヤマが同じような戦略を描いています。
特定の家電の安価モデルいわゆるジェネリック家電のセグメントからスタートし、若年層や低機能モデルを求める層にヒットしています。
同社は「ユーザーイン」というコンセプトを掲げ、エンドユーザーの具体的なニーズに基づいた製品開発を行い、生活提案型の商品を提供しています。
このような戦略により、フォロワー企業がノウハウを蓄積し、シェアを徐々に拡大し、チャレンジャーやリーダーに変化する場合があります。
一方、ニッチャー企業は、特定の市場セグメントに特化し、高い専門性や独自性を武器に競争を回避します。
この特定分野の市場が拡大すると既存の市場とは別の市場と認識され、高い参入障壁が築かれます。
歯科医療用のデンタルミラーで国内シェア約90%。特定市場に特化した高い専門性で優位性を確立。
北海道に特化したコンビニチェーンとして地域密着型のサービスを提供。独自性を武器に市場で優位性を確保。
このような市場分離戦略により、大手企業が参入しにくい領域での優位性を確保しています。
トヨタの全方位戦略は果たして、集中と選択の原則から外れているのではないか?

トヨタ自動車は、電動化戦略において「全方位戦略」を採用しています。
これは、バッテリーEV(BEV)、ハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCEV)など、さまざまなパワートレイン技術を並行して開発・提供する方針です。
一見すると、リソースの分散や戦略の焦点が定まらないようにも見えますが、トヨタはこの戦略により、地域ごとのエネルギー事情やインフラ整備の状況、顧客ニーズの多様性に柔軟に対応しています。
例えば、電力インフラが未整備な地域ではHEVやFCEVが有効であり、都市部ではBEVの需要が高まっています。
トヨタはこれらの多様なニーズに応えることで、グローバル市場での競争力を維持しています。
このように、トヨタの全方位戦略は、単なる「集中と選択」の原則からの逸脱ではなく、顧客中心主義と市場適応性を重視した戦略的な選択は表向きの理由です。
しかし最大の理由は、【ゴールポストの位置を変えられること】に対する対策です。
トヨタのようなグルーバル企業は、世界各国で自国に有利な内容に法律が変更されます。
ヨーロッパの排ガス規制、トランプ大統領による関税政策などカントリーリスクが他の業種の何倍も多いのです。
各国で一定数のシェアを維持するためには、その国のユーザのニーズとマッチしなければ、法改正時に大きな損失を被ってしまいます。
集中と選択をしたくとも、全方位戦略をせずにはリスクコントロールできないということです。