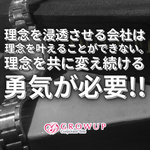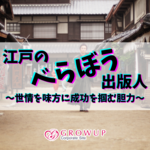Blog
【MBA × 現場思考⑦】「価格は誰のものか?」──競争戦略とプライシング再考
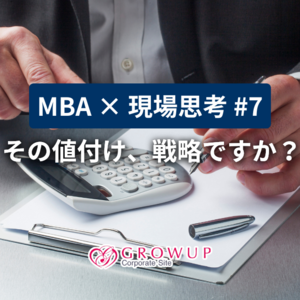
ポーターの競争戦略フレームワークと価格戦略について
私たちは現場で日々「価格をどう設定するか」「競合とどう差別化するか」という問いと向き合っています。
MBAで学ぶ戦略理論は、こうした実務の意思決定に“型”や“視点”を与えてくれますが、一方で「この理論は今の時代にも通用するのか?」という懐疑もまた生まれます。
本稿では、競争戦略の基本とされるポーターの三類型をあらためて確認しながら、それが価格戦略にどう影響するのか、そして現代の「パーソナライズド・プライシング」や「一物一価の是非」まで、現場視点で問い直してみたいと思います。
目次
ポーターの競争戦略のフレームワークとは?

マイケル・ポーターが提唱した競争戦略の三類型は、今日でも多くの企業分析や経営戦略論の基本として使われています。
ポーターの「基本戦略三類型」とは
このフレームは業界内のポジションを明確化するのに有効で、特に自社が「何で勝つのか?」を考える際の出発点になります。
価格戦略の種類について
価格は「利益の源泉」でありながら、「市場との接点」でもある重要な戦略要素です。
以下に代表的な価格戦略を紹介します。
代表的な価格戦略
価格戦略は単なる「値付け」ではなく、顧客への提供価値とのバランスをどう設計するか、という戦略的意思決定です。
ポーターのフレームによる分析は、いつまで有効か?

ポーターのフレームは今なお有効ですが、限界も見えてきています。
-
業界の境界が曖昧に
(例:Amazonは小売業か?IT企業か?) -
消費者の選択行動が「感情」や「共感」で左右される
(≒ 情緒価値の重視。スペックではなく“意味”で選ばれる) -
パーソナライズ化・個別対応のニーズが急増
(一括りに分析できない時代へ)
つまり、「業界内の位置取り」に意味があった時代から、「個人単位の選好データに基づく戦略」へと移りつつあります。
たとえば、PDRM(Personal Data Relationship Management)やCDE(Collaborative Data Enhancement)のように、個別のデータ起点での戦略立案が次世代の軸になり得ます。
はたして現在に一物一価が正解なのか?

「一物一価」の原則は近代経済学の基本でしたが、それは供給が希少で、流通も限定的だった時代の話です。
現代のように情報が開かれ、顧客ごとのニーズや文脈が複雑に絡み合う社会においては、「誰に、いつ、いくらで売るか?」がますます重要になっています。
一律割引の落とし穴|共感なき顧客に割引してしまうと…
多くの企業が実践してきた「新規顧客への一律割引」や「誰でも使えるクーポン」は、実はブランド価値を毀損するリスクを内包しています。
とくに気をつけるべきは、共感性の低いユーザーに対して安易に値引きしてしまうことです。
その理由は?
興味関心が薄いユーザーに値引きで無理に購入させてしまうと、
➡︎ その割引価格が「参照価格(アンカープライス)」となり、次回以降の正規価格を高く感じさせてしまう。
価格でしか動かない層を獲得してしまうと、
➡︎ 価格を戻した瞬間に離脱し、リピートされない。しかもブランドの“値引きありき”の印象が残る。
つまり、本来であれば価値に共感してもらうべき段階の顧客に、先に価格で訴求してしまうと、商品の本質価値が伝わらなくなるのです。
現代ではむしろ:
・個々人に異なる価格で売るほうが合理的 (=パーソナライズド・プライシング)
・時間帯や在庫によって価格を柔軟に変えるほうが効率的 (=ダイナミック・プライシング)
・ブランドへの共感度やロイヤルティによって価格を差別化できる (=エモーショナル・プライシング)
これらを可能にするのが、データとテクノロジーです。
正しいアプローチ|セグメント別・関係性ベースの価格戦略
これからの価格戦略は、「誰にでも割引する」のではなく、“誰にだけ割引するか”を見極める視点が重要になります。
たとえば:
・購入履歴やエンゲージメントデータから、ロイヤル層・離反リスク層・新規層をセグメント化
・離反リスク層や復活ユーザーにはピンポイントで割引を実施
・一方で、ブランドに共感し、自発的に商品に価値を感じている層には値引きではなく、限定情報や先行体験などの非価格特典を提供
このように、割引を“販促”ではなく“処方”として扱うことが、ブランドの健全性を保ちながらLTV(顧客生涯価値)を最大化するカギとなります。
価格の再定義へ|「一物一価」から「一人一価」へ
価格はもはや「固定された値札」ではなく、「文脈に応じた可変の価値表現」へと変わりつつあります。
共感しているか
なぜ今この商品が必要か
その人にとっての価値はどれくらいか
こうした背景をもとに価格を設計することが、パーソナライズド・プライシングの本質であり、PDRM(Personal Data Relationship Management)の未来的な価値戦略でもあります。
まとめ

ポーターの競争戦略は、依然として「基本の型」として有効です。
しかし、環境が激変する現代においては「一物一価」や「業界内の優位性」だけでは戦えません。
これからは、価格戦略を個人ベースで捉え、共感や文脈、タイミングをもとに調整する視点が重要です。
価格戦略の重要ポイント:
- 共感:誰が、なぜそれを作ったのか? 自分の価値観と合うか?
- 文脈:いつ、どんな状況でその商品・サービスが必要なのか?
- タイミング:今すぐ欲しいのか?後でもいいのか?それが価格受容性を変える。
これらは「個別性」を前提とした価格戦略であり、「一物一価」の前提を崩す合理的な根拠になります。
つまり価格は「市場」ではなく、「個人」と「関係性」によって決まる時代へと進んでいるのです。