Blog
【MBA × 現場思考⑥】「選ぶ経営」への転換──ポートフォリオ戦略と事業の見極め方

ポートフォリオマネジメントと市場ライフサイクル
複数の事業を展開する企業にとって、「どの事業に注力すべきか?」「どの事業は見直すべきか?」という問いは日々つきまといます。
その答えを導くための手法が、ポートフォリオマネジメントです。
この記事では、戦略的に事業の選択と集中を行うための考え方と、その背景にあるフレームワークを解説します。
目次
ポートフォリオマネジメントとは!?
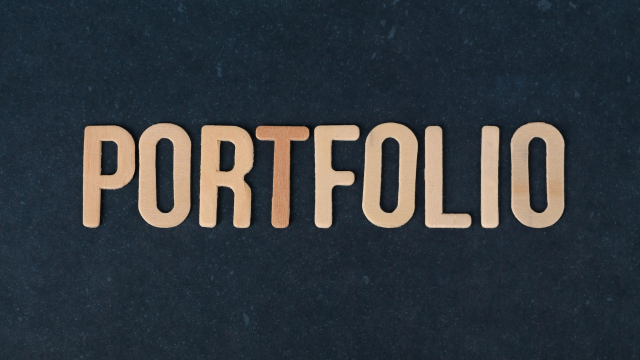
ポートフォリオマネジメントとは、複数の事業・製品を「資産」と捉え、全体最適の視点で評価・管理する戦略的手法です。
株式投資でリスクとリターンのバランスを取るように、経営資源(ヒト・モノ・カネ)を最も効果的に配分することを目的としています。
事業ごとの“現在の位置”と“将来性”を把握し、どの事業に資源を集中すべきか?どの事業を維持・撤退すべきか?を判断するための思考枠組みです。
BCGのPPMとGEのビジネス・スクリーン
BCGマトリクス(PPM:プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)
市場成長率×市場シェアの2軸で分類
花形(Star)
市場成長率・市場シェアともに高い。積極的な投資で市場リーダーを維持しながら、将来のキャッシュカウに育てるポジション。
金のなる木(Cash Cow)
市場成長率は低いが、シェアは高い。安定した収益源として、他事業への資金供給源となる。過剰投資は避けつつ利益最大化を図る。
問題児(Question Mark)
市場成長率は高いが、シェアは低い。将来的に花形となる可能性を秘める一方で、投資判断を誤れば失敗リスクも高い。選択と集中が鍵。
負け犬(Dog)
市場成長率・シェアともに低い。撤退・縮小の対象になりやすいが、ブランド価値やシナジーがある場合は戦略的保有も検討。
【注意点】
- 単純すぎる分類に依存すると、事業の本質を見誤るリスクがある
- 定量評価に偏りやすく、ブランドやノウハウといった非数値的価値を見落としがち
GEのビジネス・スクリーン
業界の魅力度 × 自社の競争力で9象限に分類。
より多面的で柔軟な評価が可能。
【注意点】
- 評価指標が多く、主観が入りやすい
- 評価に手間と分析力が必要
- 内部データを指標に多用しているため、客観性に欠けるリスクがある
両者に共通して重要なのは、「数字の裏にある意味」を読み解くリテラシーです。
事業ポートフォリオで確認すべきは、シナジーと投資すべき事業の見極め
戦略的なポートフォリオ設計では、以下の2点を重視するべきです。
ブランド強化、
顧客基盤の相互活用 など
事業にいかに早く資源を
移せるかが重要
単体で収益を出している事業でも、全体として足を引っ張ることもあります。
だからこそ、「個別最適」ではなく「全体最適」の視点が必要です。
加えて重要なのは、「将来的に狙うべき事業ポートフォリオを創造しながら会議せよ」という考え方です。
未来の市場構造や顧客ニーズを先取りし、現状の延長線上ではない戦略的視点での議論が求められます。
事業ポートフォリオを組む理由は株式投資と同じ
事業ポートフォリオは、いわば企業版の資産運用です。
将来の成長ドライバーを創出
他事業への資金供給源とする
資源再配置を図る
これらをバランスよく保有しながら、「未来の成長曲線」を描くことが経営の醍醐味です。
市場のライフサイクル(導入期→成長期→成熟期→衰退期)に応じた資源再配分が不可欠です。
また、株式投資における格言である「同じかごに卵を盛るな(Don’t put all your eggs in one basket)」のように、特定事業への依存を避け、多様なポートフォリオによってリスクを分散させる思考も非常に重要です。
アンゾフの事業拡大マトリクスとその他の事業展開思考方法
事業の成長戦略を方向づける代表的なフレームワークに「アンゾフの拡大マトリクス」があります。
| 既存市場 | 新市場 | |
|---|---|---|
| 既存製品 |
市場浸透
既存顧客への販売強化やシェア拡大を狙う |
市場開拓
新たな地域顧客層へのアプローチ |
| 新製品 |
新製品開発
既存市場向けに新しい商品・サービスを投入 |
多角化
新市場へ新製品で参入。最も高リスク・高リターン |
多角化この4象限から、リスクの低い「市場浸透」、リターンの高いが不確実性も大きい「多角化」まで、自社の資源と成長目標に照らして最適な戦略を選びます。
- ブランド・販売チャネルの活用による効率性
- 既存のノウハウやリソースを活かした展開の速さ
- 顧客基盤の転用によるクロスセルの可能性
出発点が「既存の強み」
アンゾフは、企業がすでに保有している市場や製品を基点に、リスクを段階的に取りながら成長戦略を描くことを推奨しています。
これは「再現性のある成功パターン」の延長線上に、新たな機会を見出すという発想です。
リスクの段階的コントロール
比較的短期間で成果が出やすい施策
慎重な市場分析と準備が不可欠
この考え方は、組織にとっての「実行可能性」と「資源の活用効率」を重視した現実的なフレームです。
戦略的想像力の限界と補完
逆に言えば、「既存」から自由にならない限り、破壊的イノベーションは起こしにくいという側面もあります。
そのため、アンゾフに基づく議論だけではなく、「ゼロベース思考」や「ジョブ理論(JTBD)」などのアプローチと組み合わせて使うと、より柔軟で革新的な戦略立案が可能です。
ゼロベース思考(Zero-Based Thinking)とは?
ゼロベース思考とは、「今までの前提をすべてリセットし、ゼロの状態から最適な解を考える思考法」です。
ビジネスでは、慣習や既存資源にとらわれず、真に価値のある行動や仕組みを再定義するために使われます。
ジョブ理論(Jobs To Be Done:JTBD)とは?
ジョブ理論は、「顧客は商品を“買う”のではなく、“自分の課題を解決するために雇う”」という発想に基づく、顧客ニーズの深掘りフレームです。
つまり、「この商品が果たしている“ジョブ(用事・目的)”は何か?」を明確にする理論です。
まとめ|事業は「持つ」ではなく「選ぶ」時代へ

すべての事業に均等に投資する時代は終わりました。
PPMやGEマトリクスを活用することで、自社の全体像を“見える化”できます。
シナジーと将来性のある事業に、リソースを集中させることが重要です。
投資判断の考え方は、株式投資と多くの点で共通しています。
成長戦略の方向性は、アンゾフマトリクスを使って明確にしましょう。
持続的な成長を実現するためには、どの事業に注力するかという“筋の良い選択”こそが、経営の要になります。




