Blog
【MBA × 現場思考⑤】「戦う場所」と「勝ち方」──ドメイン設計とコアコンピタンス育成の実践
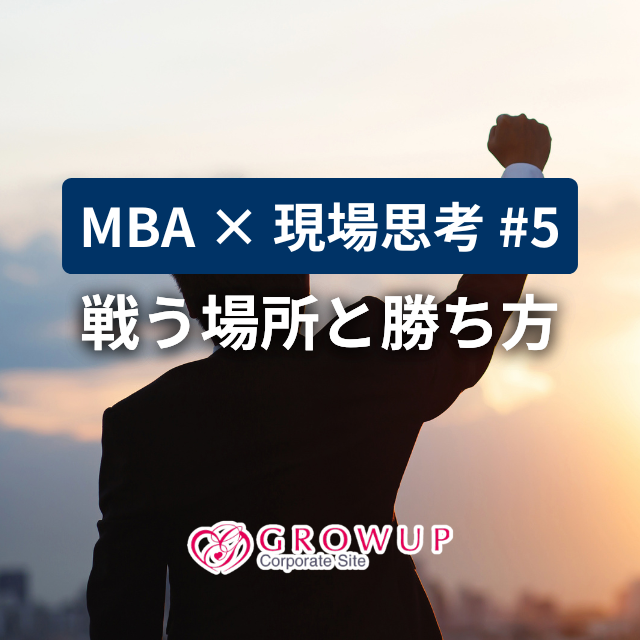
ドメインの決定方法とコアコンピタンスを育て、戦略を強化する仕組み
戦略を策定する上で、「どこで戦うか(ドメイン)」と「何で勝つか(コアコンピタンス)」の決定は極めて重要です。
この回では、全社戦略におけるドメイン設定とコアコンピタンスの育成を通じて、競争優位の源泉をどう設計していくかについて解説します。
目次
全社戦略では、事業領域・中核的な力(コアコンピタンス)・資源配分の3つに注目

全社戦略(Corporate Strategy)とは、企業グループ全体の方向性を定める最上位の戦略です。
特に以下の3点に注目が必要です:
- 事業ドメインの設定:どの市場・業界で戦うのか?
- コアコンピタンスの明確化:自社が持つ中核的な競争力は何か?
- 資源配分の最適化:どの事業にどの程度のヒト・モノ・カネを投下するか?
コアコンピタンスとは?
コアコンピタンスとは、「自社の競争優位の源泉となる中核的能力や仕組み」を指し、単なる技術やノウハウにとどまらず、次の3つの条件を満たすことが求められます。
戦略的な資産としての要件
- 顧客に独自の価値を提供できること
- 他社には容易に模倣されないこと
- 複数の事業に応用可能であること
これら3つの条件が一貫性と整合性をもって備わっていなければ、どれほど立派な戦略であっても、実行段階で迷走するリスクが高まります。
ドメインは“戦う場所”ではなく、“志す未来”──ビジョンと連動させよ

ドメインとは、「企業が事業活動を行う領域・フィールド」を意味します。
単なる「市場」や「業界」ではなく、企業の存在意義(ミッション)や将来像(ビジョン)と連動して設定されるべきものです。
「ドメイン=戦場」と捉えると、短期的な儲け話に走りがちです。
実際には、ドメインは企業のビジョンと連動した「成長する土壌」でなければなりません。
「儲かりそうだからやる」ではなく、
「この領域でなら自社の強みが活かせる、育つ」と判断できるかがポイントです。
したがって、ドメイン設定とは、コアコンピタンスが発揮・進化できる「育成環境」の選択ともいえるのです。
中核的な価値は現状の分析ではなく、将来的に優位性を作れる力で決める

今ある強みだけを見て、「これがうちの核だ」と決めつけるのは危険です。
むしろ注目すべきは、
- 今後、どのような競争環境になるか?
- その中で自社はどのような価値を創出できるか?
つまり、未来視点での強み(将来の競争優位)を見極め、それを今から育てていくという発想が重要です。
また、コアコンピタンスは「分析」で終わるのではなく、それを強化し続けるための施策=戦略へとつなげる必要があります。
戦略とは、「強みを伸ばすための仕組み設計」であり、育て続けるプロセスでもあるのです。
まずはVRIO分析で5つの条件を見極めよ
将来的な優位性を見極めるために有効なのが、VRIO分析です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Value (価値) |
顧客にとって意味のある価値を生んでいるか? |
| Rarity (希少性) |
他社には真似できない、または希少な資源か? |
| Imitability (模倣困難性) |
他社が模倣するのに時間・コストがかかるか? |
| Organization (組織) |
それを活かせる組織体制が整っているか? |
| Sustainability (持続可能性) |
この優位性はどれだけ維持できるか? |
さらに、以下の2つの視点も付け加えると、より実践的です。
- 移転可能性:他企業への模倣や移転が困難であるか?
- 代替可能性:他の製品・技術などで代替されにくいか?
この7つの条件を見極めることで、より信頼性のあるコアコンピタンス候補を抽出できます。
経営資源が不足している場合はアライアンスで補完する

自社だけですべての資源を持つ必要はありません。
特に中小企業では、外部との連携(アライアンス)でリソースを補完し、競争優位を作る戦略が有効です。
「オープンイノベーション」
「異業種連携」
「地域連携・大学・行政との共同開発」
などを通じて、“コミュニティとしてのコアコンピタンス”を築いていくことも可能です。
さらに、自社がコントロール可能な経営資源を社外に拡張するという「外部拡張思考」も重要です。
これは、信頼性のあるパートナーやプラットフォームと協業し、自社の影響範囲を戦略的に広げていくことを意味します。
特にPDRMのような「共通プラットフォーム」をベースにすれば、価値創造の核が社外にも広がり、より模倣困難なビジネスモデルが構築できます。
まとめ|ドメインとコアコンピタンスの設計は、未来への布石である
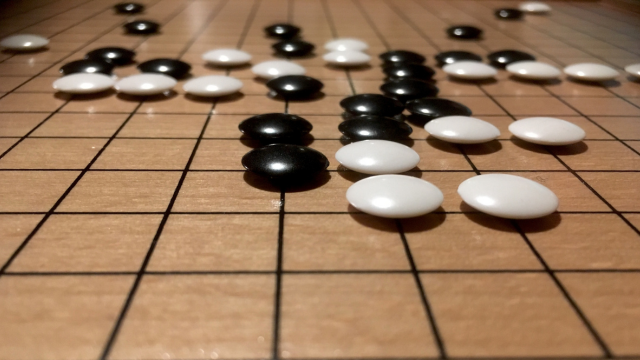
ドメインは「今」ではなく、「未来」に自社の力が育つ場所を指します。
コアコンピタンスは、将来に意味を持つ力を育てる視点で見つけることが大切です。
VRIO分析を活用し、移転可能性や代替可能性、耐久性といった視点も加えながら、自社の核を見極めましょう。
不足している経営資源はアライアンスを活用して補い、開かれた強みを形成していくことも重要です。
さらに、自社がコントロールできる資源の範囲を広げる「外部拡張思考」も戦略の一部として欠かせません。
これらを踏まえ、ビジョンから逆算して「戦う場所」と「勝ち方」を戦略的に設計することこそ、経営戦略の真髄と言えます。




