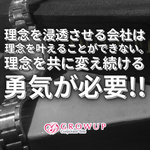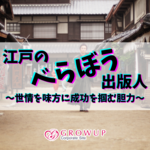Blog
【MBA × 現場思考④】戦略は組織を変えうるか──策定プロセスと“現場視点”の再設計
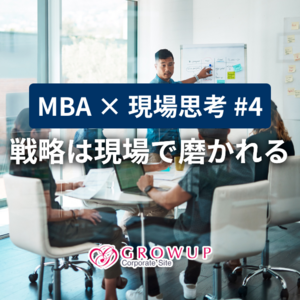
戦略は組織に従うべきか?それとも、組織が戦略に従うべきか?
経営戦略を語る際、必ずといっていいほど浮上するこの問いは、単なる「順番」の問題ではなく、経営の本質を突く重要なテーマです。
戦略を先に描き、組織の形をそれに合わせていくのか。
あるいは、現場の実態を踏まえて、組織に根ざした戦略をつくるのか。
本記事では、この問いを軸にしながら、戦略策定の基本プロセスと、戦略と組織の“相互関係”に焦点を当てて解説します。
理論だけでは終わらない、現場で使える戦略思考を手に入れるためのヒントをお届けします。
目次
戦略とは「意思決定の連続」である──基本プロセスと現場実践の流れ

戦略とは、「意思決定の連続」です。
目の前の選択を“理想に向かう方向”に導く羅針盤であり、偶然に頼らず成果を積み上げるための「筋道の設計図」ともいえます。
【戦略プロセスの基本ステップ】
- ① 現状把握(環境・内部)
- ↓
- ② 問題の特定とゴール設定
- ↓
- ③ 解決策の立案(戦略オプション)
- ↓
- ④ 優先順位の決定と実行設計
- ↓
- ⑤ 実行・検証・見直し
このプロセスは一度きりではなく、PDCAのようにループして繰り返すことが重要です。
戦略の上位概念には、理念・ビジョン・ドメインがありますのでこの戦略を実行すればその方向性に近づくのかと考えることが重要です。
環境分析フレームワークの使い方──PEST・SWOT・3C・5フォースをどう現場に活かすか

戦略の出発点は、“世界をどう見るか”です。
そのために、環境分析のフレームワークを活用します。
【環境分析フレームワークまとめ】
政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)
Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats
Customer(顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)
新規参入の脅威・競争業者の敵対関係・代替品の脅威・買い手の交渉力・売り手の交渉力
これらのフレームワークは、情報の整理だけでなく、仮説構築・視点拡張のツールとして活用できます。
ビジネスにおいて、情報は全て集まりません、限られた情報の中でパーツを組み合わせ推論・仮説を形成することが不可欠です。
そうでなければ、戦略は成り立ちません。
また、現状の分析だけでは片手落ちです。
顧客がどう反応するのか?また競争他者がどのような打ち手を示すのか?
事業環境は常に変化していきます。
戦略の可視化ツール「リーンモデルキャンバス」とは──1枚で描く現場視点の戦略設計

伝統的な重厚長大な戦略書ではなく、最近では「1枚の戦略設計図」が支持されています。
中でも有効なのが、リーンモデルキャンバス(Lean Model Canvas)です。
ビジネスモデルキャンバスをアップデートしたもので、環境変化に対応できる書式になっています。
これは、スタートアップや新規事業において、最小限のリソースで最大のインパクトを出すための「思考の整理表」です。
【リーンモデルキャンバスの主要6要素】
- ① 顧客セグメント:誰に価値を届けるのか?
- ② 顧客の課題:解決すべきニーズやペインは何か?
- ③ 提供価値:どのような価値を提供するのか?
- ④ ソリューション:価値を実現する手段・方法は?
- ⑤ 収益モデル:どうやって利益を生むか?
- ⑥ 指標と指標追跡:何をもって成果とし、どう検証するか?
これにより、「思いつき」ではなく、論理的かつ顧客中心の戦略を設計でき、変化にも柔軟に対応できます。
また、環境の変化に応じて、各セグメントを実態に合わせて見直すことで、現実にフィットした戦略へのアップデートが可能になります。
良い戦略に必要な2つの条件──合理性×創造性は“特許”にも通じる

戦略に求められるのは、単なるロジックではありません。
合理性・創造性に求められる力
・合理性・論理性(分析力)
目的から逆算し、現実的に到達可能な筋道があるかを検証します。
・創造性・革新性(発想力)
他社にはない独自の突破口を提示できるかが問われます。
戦略策定の3ステップ
- 事実を客観的に観察し、論理的に組み立てて分析する
- 推論と事実を組み合わせ、問題の本質構造に迫る
- 真の課題に対応し、効果的に解決できる方策を設計する
これはまさに、「特許」に求められる“新規性と進歩性”に似ています。
“誰もやっていない”“でも実行可能”というバランスが問われるのです。
戦略は組織を変革するためにある──「従属」ではなく「相互作用」の関係へ

戦略は、現状の延長ではなく、“変革の起点”であるべきです。
つまり:
- 組織のリソースや構造に合わせるだけでは、変化は生まれません。
- 一方で、現場を無視した戦略は絵に描いた餅にすぎません。
このジレンマを超えるには、戦略と組織が“双方向に影響を与える関係”であることが重要です。
戦略の策定や実施に関わる人々を動かすには、信念や夢、リスクへの挑戦、既存の組織風土の打破、革新的なものの見方、感情に働きかける力が必要となります。
PDRMは、この組織の意思決定の癖を解明し、支援する仕組みも模索しています。
組織は戦略に従い、戦略は組織によって鍛えられる
この相互作用を設計し、日々の行動レベルに落とし込むのが、現場リーダーに求められる力なのです。
まとめ|戦略は「誰かが決めるもの」から「組織全体で創るもの」へ
- 戦略とは、現場を導く意思決定の道筋です。
- 分析フレームは、視点を得るための重要な道具です。
- 創造性と合理性の両立が不可欠です。
- 戦略は、組織を変える存在であるべきです。
だからこそ、戦略は「現場で語れる言葉」で語られるべきなのです。