Blog
【MBA × 現場思考③】理念と戦略を“つなぐ”──経営の言葉を現場の力に変える

経営理念と戦略レベル──現場にどうつなげるか?
現場の努力は、本当に戦略とつながっているでしょうか?
「現場が頑張っているのに、なぜ成果につながらないのか」と感じたことはありませんか?
また、「この改善は戦略と関係があるのだろうか」と疑問に思うこともあるでしょう。
こうした違和感は、戦略と現場の間に“言葉の橋”が欠けているからかもしれません。
経営理念やドメイン定義、階層的な戦略構造をしっかり理解し、現場とつなげることが大切です。
本記事では、理念から戦略、そして現場へとつなげるポイントを5つの視点から解説します。
目次
経営理念の定義とビジョンとの違い(そして“進化する理念”)
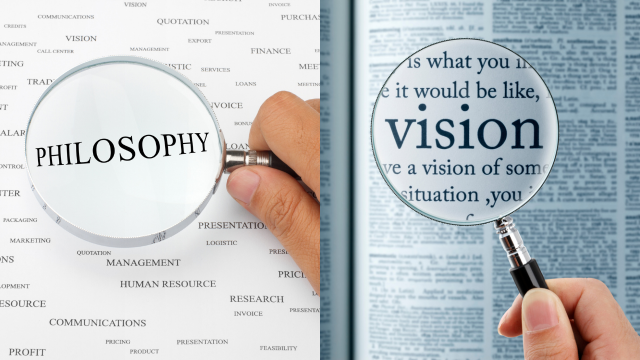
経営理念(Philosophy/Mission)とは、その企業が存在する理由や信じている価値観を示すものです。
一方、ビジョン(Vision)は、将来どうなりたいかという“目的地”です。
かつては「理念は一度定めたら永遠に守るもの」とされていましたが、今の時代、理念もアップデートされるべきという考え方が主流になりつつあります。
なぜ理念は進化するのか?
- 社会や顧客の価値観が変化しているため
- 多様性、サステナビリティ、ウェルビーイングなど
求められる社会的役割が広がっているため
🔑 重要なのは、“軸はぶらさず、表現を磨く”こと
例:パナソニックの「社会貢献」という軸は変わらずとも、
その方法は「ものづくり」から「環境貢献・ESG・共創」へと拡張されている。
戦略は3階建て構造|全社・事業・機能戦略の違い

意思決定はどこで生まれるか?
戦略を立てるには、どのレベルの話をしているかを明確にすることが大切です。
| 戦略レベル | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 全社戦略(Corporate) | 企業全体の方向性・事業ポートフォリオ | 「ITと教育の両軸で展開」 |
| 事業戦略(Business) | 各事業での競争戦略 | 「教育事業は高単価・深耕型」 |
| 機能戦略(Functional) | マーケ、開発、人事など各部門の戦術 | 「LP改善と営業スクリプト刷新」 |
「自分は今、どのレベルの戦略を考えているのか?」を意識すると、議論や改善策がブレなくなります。
付け加えると、事業戦略は大手企業だけのものではありません。
経営資源の少ない中小企業だからこそ、戦略や方策が不可欠なのです。
経営資源を獲得または組織内で創造し、新たな事業戦略に組み込む構造的な仕組みが必要なのです
事業ドメインと企業ドメインの違い(中小企業では同一のことが多い)
| ドメイン種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業ドメイン | 事業ごとの市場定義、顧客、価値 | 商品・部門単位で設計 |
| 企業ドメイン | 企業としての市場定義・存在意義 | 全社的な成長領域や思想を含む |
中小企業では1つのドメインしかない場合が多く、両者が実質同一になっていることがほとんどです。
そのため、「企業としての存在意義=主力事業の価値提供」という構図が成り立ちます。
これには、弊害があり、新規の事業を開発するときにドメインを分離しなければならないということになります。
そうしなければ、どうしても視野が狭くなってしまうからです。
不確実性の時代において、単一の事業領域しか目が向いていないと成長の機会を見失い事にもなりかねません。
サービス業であろうが、飲食業であろうとも価値を創造し、顧客を満足させるといった基本的な概念は変わりません。
新たな事業展開をしるときには基本的な概念の中でどこで強みを発揮できるのか?
自社らしさ、自社事業との相補・相乗効果。経営資源の同時利用などを考慮しなければならいということです。
ドメイン3つの軸(アンゾフの事業定義フレーム)
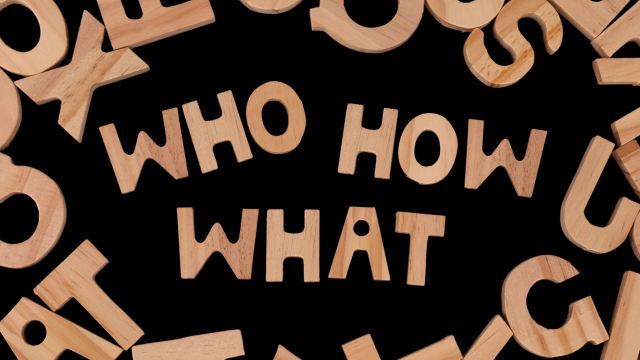
アンゾフのフレームは、事業ドメインを「Who/What/How」で捉えるものです。
| 軸 | 定義 | 例(弁当事業) |
|---|---|---|
| Who(誰に) | ターゲット顧客 | 都市部の単身世帯 |
| What(何を) | 提供する価値 | 健康で手軽な食事 |
| How(どうやって) | 実現手段 | 自社調理と店舗網・配送体制 |
この3軸が曖昧だと、事業戦略もぶれてしまいます。
逆に、3軸がはっきりしていれば、現場の判断が早くなります。
事業ポートフォリオとシナジーについて
企業が複数の事業を抱えている場合、どこに注力し、どこを撤退するかの判断が必要です。
これが「事業ポートフォリオ戦略」です。
代表的な分析例:BCGマトリクス
- 花形:成長市場でシェアも高い
- 金のなる木:成長は鈍化しているが稼げる
- 問題児:成長はしているがシェアが低い
- 負け犬:撤退検討領域
市場でどのポジションにいるのか?
その市場は商品ライフサイクルの中でどのような状態にあるか?
企業全体の中でその事業はどの役割にあるか?
つまり、どの経営資源を獲得できるかは重要ことです。
短期的な視点だけだと、キャッシュに目が生きがちですが、軽資源とは(人・モノ・カネ・ノウハウ・データ)などです。
戦略的に獲得するためにはそのとき一時の分析だけでなく、将来に渡って時間的な経過を考慮する必要があります。
※PDRMの概念では、Personal Data Relationship Management(PDRM)は、個人と企業の関係を“データ”を通じて戦略的に強化するアプローチとされています。
戦略的に獲得すべきことがデータとヒトです。キャッシュはスケール後になります。
加えて、重要なのが、事業同士に“シナジー(相乗効果)”があるかどうか。
| シナジーの種類 | 例 |
|---|---|
| 営業シナジー | 同じ営業チームで複数商材を提案 |
| 技術シナジー | R&D成果を他事業に転用 |
| ブランドシナジー | 一貫した世界観で複数サービスを展開 |
シナジーのない事業は、リソースの分散や軸のブレにつながるため、「選択と集中」の判断材料になります。
まとめ|理念・戦略・現場が“つながる”と組織は強くなる

理念は変えてはならないものではなく、軸を保ちながら時代に合わせて“進化”させるもの。
戦略は「どのレベルの話か」を見極めることで、現場とつながる。
ドメインやシナジーの考え方を用いれば、組織の“焦点”が明確になる。
経営は“理屈”と“現場”の橋渡し。
その橋を架けるのは、MBA的思考を持った“現場のあなた”かもしれません。




