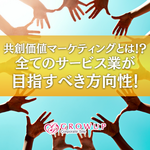Blog
構造化する“人”の力(第3回)理念を動力に変える、“構造エンジニアリング”の技術
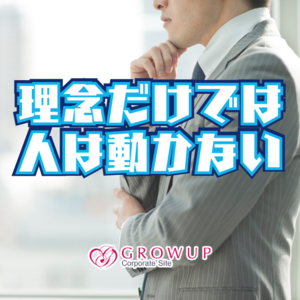
目次
理念があるのに、なぜ組織は動かないのか?

「うちは理念があるのに、社員が共感していない」
「ビジョンを掲げても、現場には浸透していない」
そう悩む経営者やマネージャーは少なくありません。
ですが、それは理念やビジョンの質の問題ではなく、構造に落とし込まれていないことが原因です。
どれだけ立派な言葉を掲げても、それが日々の意思決定、行動、評価、習慣に結びついていなければ、理念は“立てかけられた看板”にすぎないのです。
理念は“構造化”されて、初めて機能する

ビジョンやパーパスを「経営の中心」に据えるには、次の3つの段階が必要です。
理念を機能させる3ステップ
-
① 言語化する(共有可能にする)
→ 誰が聞いても理解できる、共通のことばとして定義する。 -
② 構造化する(仕組みに落とす)
→ 人事制度、採用基準、育成計画、会議の設計、評価基準などに埋め込む。 -
③ 可視化する(ふるまいに現れる)
→ 上司の言動、日々の選択、意思決定プロセスとして見える状態にする。
ここで“②”の構造化が抜け落ちると、ビジョンは抽象的なスローガンとなり、現場の実感を失っていきます。
人が“理念通りに動く”組織には、仕掛けがある

理念が“行動の構造”として浸透している組織の例
- 会議の冒頭でビジョンに沿った意思決定を確認する
- 評価項目に「パーパスに沿った挑戦」が含まれている
- 1on1で“理念と自己の接点”を言語化する習慣がある
- 制度設計が「目先の成果」よりも「長期的な貢献」に報いている
こうした仕掛けがある組織では、理念は“ポスター”ではなく、人を動かす“空気”として機能するようになります。
理念は、仕組みによって体現され、反復によって文化となるのです。
経営者に必要なのは“理念のエンジニアリング”

経営者が果たすべき最も重要な役割は、理念を構造として設計する“思考のエンジニア”であることです。
理念を構造に落とすために、経営者が答えるべき問い
- この理念を、どう評価制度に落とすか?
- この価値観を、どの場面で問うか?
- このビジョンを、行動レベルの習慣にどう変換するか?
この問いに、自分の言葉で答えられる経営者こそが、理念を語る資格を持っているのだと思います。
理念は、ただ掲げるものではなく、日々の構造やふるまいによってこそ、語られるべきものなのではないでしょうか。
「人が動く言葉」ではなく、「人が動く構造」を設計せよ

人は、理念に感動することはあっても、実際に動くのは仕組みによってです。
理念は出発点にすぎません。
仕組みに変換されてはじめて、力を持ちはじめるのだと思います。
経営とは、理念を“人が動く仕組み”として設計していく営みなのではないでしょうか。
次回予告
次回はさらに行動面に踏み込み、“人が自然と動きたくなる組織”に共通する構造について解説します。
第4回|ナッジ経営:人が自然と動きたくなる場
心理・行動経済学の知見も交えながら、「人が動く組織の空気のつくり方」に迫ります。