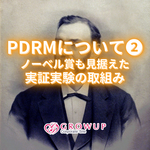Blog
構造化する“人”の力(第1回) 人的資本経営は「仕組みづくり」から始まる

経営とは、単に利益を最大化するための仕組みではありません。
人が集まり、自ら動き、そして「ここにいる意味」を感じられる“場”を設計することが、経営の本質だと考えます。
この連載では、人的資本を「能力の集合体」としてだけでなく、感情や文脈、共鳴といった要素を含んだ“構造化された力”として捉えていきます。
「なぜ、ある会社には人が自然と惹かれ、別の組織からは離れていってしまうのか?」
その問いに対する答えは、「構造」にあります。
真に人を活かす人的資本経営とは、“人そのもの”に注目するのではなく、“人が自然と力を発揮したくなる構造”をつくることから始まるのです。
経営とは何でしょうか?

この問いに対して、皆さんはどのように答えるでしょうか?
「売上を上げること」
「利益を最大化すること」
「社員をマネジメントすること」
いずれも間違いではありません。
ですが、私は次のように定義したいと思います。
経営とは、“人が集まり続ける構造”をつくることです。
ここでいう「集まる」とは、単に人数が多い状態を指すのではありません。
・「この場所でなら、自分の力を発揮できる」と人が信じられる状態。
・「ここで何かを成し遂げたい」と自ら動きたくなるような状態。
そうした“磁場”のような構造を意図的につくり出すことこそが、経営の本質だと考えています。
人的資本は「存在」ではなく「構造」の中で力を発揮する

近年、「人的資本経営」という言葉が注目を集めています。
しかし、それを単なる「人材の管理」や「スキルの一覧表」として捉えるのでは、本質を見誤ってしまいます。
人的資本とは、人が持つ知識や経験、情熱が“構造的に活かされる”ことによって、初めて力を発揮するものです。
どれほど優れた人材がいても、その力を活かせない場にいる限り、それは資本とは言えません。
一方で、たとえ凡人であっても、「自分の役割を感じられる構造」に身を置くことで、想像以上の成果を上げることができます。
つまり、経営者に求められるのは──
人が力を発揮したくなる“場の構造”を設計する視点です。
なぜ人は集まるのか?

人が組織に集まる理由は、スキルシートや待遇条件といった表面的なものだけではありません。
人は、“意味”に惹かれ、“共感”によって動かされるのです。
たとえば、ビジョン、パーパス(存在意義)、ストーリー、制度設計、信頼関係、日々の習慣──
こうした要素が重なり合うことで、人は「この組織に所属したい」「ここで働きたい」と感じるようになります。
つまり、経営とは、人が意味を見出し、共鳴できる“場”を意図的にデザインすることに他なりません。
次回予告

では、具体的に「人が集まる構造」はどのように設計すればよいのでしょうか?
そのヒントは、次回のテーマにあります。
第2回|人は“何”に惹かれて集まるのか?
次回は、人間の行動や感情、選択の背景にある“惹きつける力”、いわば組織の磁力の正体について掘り下げていきます。