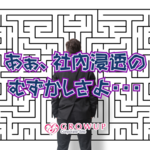Blog
人的資本時代の“組織構造とビジネスモデル”の関係性~「人を活かす設計」が競争優位を生む時代
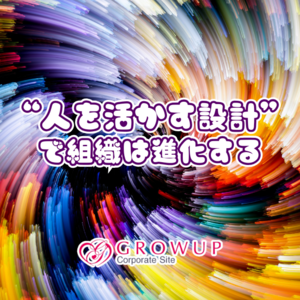
目次
人的資本が“経営資源”から“経営戦略”になった

これまで「人」は、資源やコストとして扱われることが多くありました。
しかし現在は、「人」こそが企業の持続的競争力の中核であり、経営そのものを形作る“戦略的資本”と見なされています。
そしてこの人的資本時代において、単なる組織改革ではなく、ビジネスモデルと連動した組織構造の設計が、企業の未来を左右するようになってきました。
なぜ“ビジネスモデルと組織構造”の連動が重要なのか?

旧来型の落とし穴
・経営戦略はトップだけが考え、現場は“実行部隊”
・組織図は固定、役職や部門が主語の意思決定
・評価は“効率性”や“従順さ”が基準
こうした構造では、柔軟で創造的な価値創造は難しくなります。
とくに生成AIやテクノロジーによって変化のサイクルが短くなった今、組織構造も「戦略に連動して動く柔らかい構造」でなければ、持続的な競争力は維持できません。
では、どのように組織を再設計すべきか?

以下のような視点で、ビジネスモデルと一体化した組織設計が求められます。
【視点1】「機能」より「価値創造単位」で組織を設計する
従来の組織構造|機能別の“縦割り”
・営業部
・開発部
・人事部
→ 部門ごとの役割分担が中心で、顧客体験や価値の流れは断片化されがち。
これからの組織構造|価値の流れを起点とした“横断型”
・プロダクト・サービス単位でチームを組成
・機能を横断する「自律型チーム」が、1つの価値に責任を持つ
例:Spotifyの“スクワッドモデル”
・プロダクトごとに編成された少人数チーム(スクワッド)
・エンジニア、デザイナー、マーケターなどが横断的に所属
・顧客体験の改善に直結する設計で、組織がビジネスモデルと連動
【視点2】権限分散と“戦略的余白”の設計
従来の意思決定構造|上意下達&報告ライン重視
・指示・命令は上層部から
・現場は“実行”に徹する
・判断スピードが遅く、変化対応に弱い
これからの構造|目的ベースの“柔軟な意思決定”
・組織全体が「共通目的」を持ちつつ、現場には“最適化する余白”を残す
・上層部は「方向性と原則」を示すだけ
・各チームが状況に応じて判断し、行動できる構造へ
例:リクルートの「Will-Can-Must」フレーム
Will:社員がやりたいこと
Can:自分ができること・得意分野
Must:組織や事業にとって必要なこと
この3軸の重なりから個人の役割を定義し、「やりたいこと」が事業の方向に組み込まれる設計が、人材の自律性と事業の推進力を両立させています。
「すべてを決める」のではなく、“決めないこと”を戦略的に残すことが、柔軟で強い組織の土台となります。
【視点3】人的資本データの活用で“構造の仮説検証”を行う
可視化が、構造改善の第一歩
・エンゲージメントスコア
・スキルマップ(業務対応力・強みの分布)
・LTV(従業員の生涯価値)
こうしたデータを活用し、組織構造が「人の創造性や貢献度」にどう影響しているかを定量的に分析します。
“構造の仮説”を検証し、必要に応じてピボットを
・一度つくった組織構造を“固定化”しない
・データから気づきを得て、柔軟に構造を見直す
・変化の兆しに合わせて、早期に設計をチューニング
人的資本を“感覚”ではなく“数値と構造”で捉えることで、組織は進化のPDCAを回せるようになる。
経営の柔軟性は、データをもとにした“構造の実験”から生まれます。
【視点4】“働き方”は「組織戦略」そのものである
柔軟な働き方=人材戦略の中核
・リモート勤務
・ハイブリッドワーク
・副業・パラレルキャリアの容認
これらは単なる制度ではなく、“優秀な人材が集まるかどうか”を左右する組織戦略の一部です。
“自律型人材”に選ばれる組織とは?
・働く場所ではなく、「どう価値を生むか」にフォーカスできる環境
・情報共有・評価制度・ナレッジ管理が明確で、自己管理がしやすい構造
例:GitLabの“完全リモート前提型組織”
・全情報を社内外にオープン化(透明性の担保)
・業務プロセスをドキュメント化し、いつでも誰でも参照可能
・時間や場所に縛られず、「価値創出」に集中できる働き方を実現
こうした設計により、世界中から優秀な人材が集まり、組織としての競争優位が継続しています。
働き方の選択肢は、“働く人の質と多様性”に直結する。
制度設計=組織設計であり、働き方そのものが企業価値の源泉となる時代です。
結論|「人をどう活かすか」は「ビジネスをどう設計するか」と表裏一体

人的資本経営=“人を大切にすること”では終わらない。
それは、「人の力が最大化されるように、ビジネスそのものを設計し直すこと」です。
問うべき本質は──
・組織の構造や仕組みは、人の創造性を引き出せているか?
・人の力が発揮されるような“設計”になっているか?
・変化の激しい市場に応じて、組織そのものを“再発明”できる柔軟性を持っているか?
人材活用ではなく、「人を活かす前提の構造設計」こそが、真の人的資本経営。
組織の進化は、制度や文化ではなく、「ビジネスモデルと構造」から始まります。