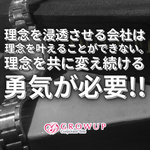Blog
経営者は社員の幸福に責任を持て【幸福経営の好循環モデル】

「うちの社員、最近なんだか覇気がないんです。」
ある中小企業の社長から、そんな相談を受けたことがあります。
その会社は黒字経営を続けており、福利厚生も他社と比べて悪くない。
給与も年々上げている。
なのに、社員の定着率は低く、若手の離職が続いていました。
よくよく話を聞いてみると、社員が「自分が何のために働いているのか分からない」「成長の実感が持てない」と感じていたことが原因でした。
会社としては一生懸命、待遇を改善していたのですが、社員にとって本当に必要だったのは“居場所”や“やりがい”、つまり「働く意味」だったのです。
この話は、決して特殊なケースではありません。
今、日本の多くの職場で同じようなことが起こっています。
1990年代以降、日本経済は「失われた30年」と呼ばれる長い低迷期を経験しました。
バブル崩壊の後、企業の多くは生き残りを最優先に掲げ、リストラや給与カットを実施しながら、内部留保を着実に積み上げていきました。
目次
失われた30年間で企業は内部留保にいそしみ会社を存続させた
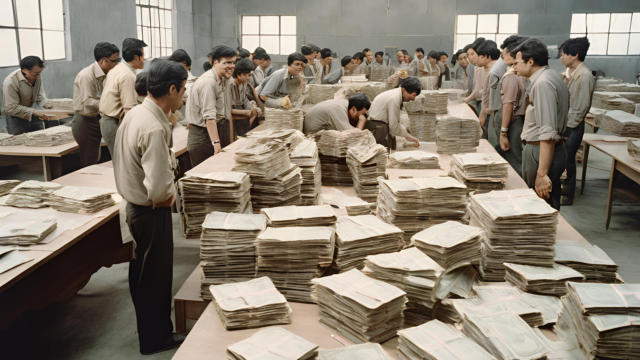
それはある意味で正しい判断だったのかもしれません。
倒産すれば社員を守ることはできませんし、景気の不安定さを乗り越えるにはキャッシュが必要だったからです。
ただ、その過程で多くの企業が「人材をどう活かすか」「社員の幸せとは何か」という本質的な問いに向き合う余裕を失ってしまったようにも感じます。
では、今の時代における“よい会社”とは何でしょうか?
給与や福利厚生といった金銭的報酬はもちろん重要ですが、それだけでは人は長く幸せには働けません。
むしろ今、多くの人が求めているのは「自己成長の実感」や「働きがい」「仲間との信頼関係」といった、形のない報酬です。
金銭という対価の他に成長の場という見えない対価が必要

自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できること、自分の成長を会社が応援してくれていると感じられること。
こうした“成長の場”こそが、社員のエンゲージメント(仕事への主体的な関わり)を高める鍵になります。
そして結果として、それが企業の成長にもつながっていくのです。
また、私たちはいまだに「一つの会社で何十年も働き続けることが正しい」といった昭和的価値観に縛られがちです。
しかし現代は副業や転職、起業といったキャリアの選択肢が大きく広がり、働き方は多様化しています。
「会社に人生を捧げる」のではなく、「会社は人生を豊かにする場である」ことが求められているのです。
何十年も勤め上げなければならないという呪縛から逃れよう

社員が会社に「しがみつく」のではなく、「ここで働くことに意味がある」と感じてもらえる関係性こそ、これからの経営には不可欠です。
そのためには、経営者が“社員の人生の一部を預かっている”という覚悟を持つことが大切です。
経営というと、売上や利益、シェア拡大といった数字が重視されがちですが、本当に見るべきは「この会社でどれだけの人が幸せになれたか」ではないでしょうか?
会社の業績を伸ばすということは、幸福になった人の数

「業績を上げる」と聞くと、多くの経営者は売上や利益の数字を思い浮かべるでしょう。
もちろん、それらは企業が存続し、社会に価値を提供し続けるために欠かせない指標です。
しかし、数字の背景にある「人」の存在を忘れてはいけません。
売上も利益も、すべては“人が動いた結果”として生まれるものです。
では、その「人」がどんな状態で働いているか。
これこそが、業績を左右する最も重要な要素です。
社員が心から納得し、誇りを持って仕事に取り組めているか。
会社という場所が、ただの労働の場ではなく、“人生の充実を感じられる場”になっているか。
そこに目を向けることが、これからの経営には求められます。
幸福な社員は、自ら考え、動き、工夫し、仲間と協力しながら成果を出します。
一方、義務感だけで働く社員は、指示を待ち、言われたことだけをこなすだけで終わります。
見た目には同じように仕事をしているように見えても、その生産性や創造性には圧倒的な差が生まれます。
また、社員の幸福はお客様にも伝播します。
笑顔のないスタッフが接客するお店と、いきいきと働くスタッフがいるお店。
どちらにまた行きたくなるかは明白です。
つまり、「社員の幸福 → 良いサービス → 顧客満足 → 業績向上」というシンプルかつ強力な循環が成立するのです。
さらに言えば、社員の幸福を追求する企業は、結果的に優秀な人材を引きつけ、離職率も下がります。
「この会社で働くことが、自分の人生にとって意味がある」と思える環境こそが、人材戦略上の最大の武器になるのです。
業績とは、数字の積み上げではなく、“幸福になった人の数”の積み上げなのだ――。
この視点に立てば、経営者としての意思決定も変わってきます。
「どれだけの利益が出たか」だけでなく、「どれだけの人を幸せにできたか」を判断軸に持つこと。
それこそが、これからの時代の“強くて、やさしい経営”の姿だと、私は信じています。