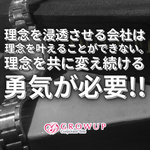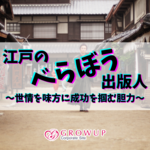Blog
ガソリンの暫定税率廃止とガソリン補助金について

日々の生活に直結するガソリン価格。私たちが給油するたびに支払っている金額の中には、実は多くの税金が含まれています。しかもその税制は「暫定」と名付けられながら半世紀以上続いており、補助金と絡み合って国民の負担や財政を大きく左右しています。
今回の法改正でガソリンの暫定税率が廃止される一方で、軽油や灯油は対象外です。
自治体や家庭への影響、さらにEVの普及による将来の税収構造まで、複雑な課題が浮かび上がっています。
この記事では、ガソリン税制度の仕組みと問題点、暫定税率廃止の影響、そして今後の税制のあり方について考えてみます。
目次
ガソリン税制度の仕組みと二重課税問題

日本のガソリンには、揮発油税と地方揮発油税を合わせて 1リットルあたり53.8円 が課税されています。
さらにその合計額に対して 消費税10% が課されるため、いわゆる「税に税をかける」二重課税が生じています。
この仕組みはかねてから「適法なのか?」という議論を呼んできました。
法律上は「課税対象をガソリン価格全体」とする解釈で成り立っていますが、国民感覚としてはやや不公平さを覚えるのも自然です。
暫定税率を廃止すれば、国全体で 年間約1.5兆円の税収減 が見込まれます。

今回の法改正の概要
ガソリンの暫定税率(揮発油税+地方揮発油税に含まれる “暫定分” 約25.1円/ℓ) は、 2025年11月1日から廃止される予定です。 これにより、ガソリン価格が1リットルあたり 25.1円引き下げ られる見込みです。
一方で、軽油引取税(軽油にかかる暫定税率)や灯油などの燃料への暫定税率は、 今回の改正では対象外とされています。これらについては引き続き暫定税率が維持され、 補助金措置も継続される方向です。
また政府は2022年から「燃料油価格定額引下げ措置」を導入し、 ガソリン1リットルあたり最大 10円程度 を補助しています。
この措置の費用は年間 1兆円規模 にのぼるとされ、今回の法改正の実質的な減収は 5000億円 ということになります。さらに、家計圧迫軽減補助金も今回の法改正で 停止される可能性があります。
とりわけ灯油を多く使う北海道や東北の家庭では、補助停止によって逆に 家計が直撃 するという矛盾も生まれてしまうでしょう。
「暫定税率」とは本当に暫定なのか

「暫定」とは一時的な意味ですが、ガソリン税の暫定税率は1970年代の石油危機をきっかけに導入され、実に半世紀近く続いています。
地方自治体にとっては道路整備や地域インフラの大事な財源であり、廃止となれば財政難が深刻化するため、「暫定」が常態化してしまったのです。
各自治体からは「廃止すれば地域の公共事業に影響が出る」という不安の声が絶えません。
なぜ制度化してしまうのか
- 財源依存:道路整備や地方交付税などに直結しており、廃止すると自治体財源が一気に不足する。
- 政治的リスク:一度でも減税してしまうと、その財源を穴埋めする新税が必要となり、政治的に負担が大きい。
- 官僚機構の論理:財源を「一度手に入れたら手放さない」という予算獲得インセンティブが強く働く。
暫定が制度化するのは、官僚組織が「財源確保」を最優先に動く体質の表れであり、政治もまた「減税リスク」を避けるために追認してきた結果です。
政治家が一度下げた消費税は戻しにくいと話をしますが、一度上げてしまった税も下げにくいのが実情なのです。
一度得た税収は、それを組織的に使用する構造が生まれます。いわば、税金を効果効率的に使用するエコシステムです。
計画を立てる → 予算をつける → 発注する / 受注する → 工事を行う → 便益を図ってくれる政治家へ投票する ── という循環になります。
一度このシステムが出来上がると、なかなか壊しにくくなります。
EV普及で訪れる“税収崖”

さらに構造的な問題として、EV(電気自動車)の普及があります。EVはガソリンを使わないため、当然ガソリン税収は減少します。
もしEVが本格的に普及すれば、道路整備や社会資本を支える財源が一気に縮小し、現在の制度は立ち行かなくなります。
EVに対する政策的優遇の矛盾
EVには購入補助金(数十万円規模)が支給され、重量税・自動車税なども優遇されています。一方で、ガソリン車にはガソリン税・暫定税率・消費税などの多重課税が重くのしかかっています。
この構造は「環境にやさしいからEVを優遇」という名目ですが、実際には発電源が化石燃料中心の国では本末転倒になりかねません。
日本の現状では電力の約7割以上を化石燃料(LNG・石炭・石油)に依存しています。つまり「ガソリン車 → EV」へシフトしても、発電段階で排出されるCO₂が大きいため、実質的な環境負荷削減効果は限定的です。
本当に普及が必要なものは「EV」ではなく…
- 再生可能エネルギーの発電比率拡大:太陽光・風力・地熱・水力などを増やし、化石燃料依存を減らす。
- 蓄電システムの強化:自然変動電源(太陽光・風力)の出力を安定化させるため、大規模蓄電池やV2H(車から家・電力系統への電力供給)が不可欠。
- 送電網のスマート化:需給調整の仕組みを整えることで、効率的に再エネを利用できる。
こうした「インフラ」が整わないうちにEVだけを優遇しても、環境面では効果が薄いばかりか、財政負担ばかりが先行するリスクがあります。
ガソリンはエネルギーです。EVなどの電動化により今後ますます使用量は減っていきます。その減り続けるエネルギーに税収を頼るのは難しくなっていくでしょう。
道路の保全などのインフラ整備は、自家用車を保有している世帯や企業だけが負担するものではありません。交通網はすべての国民が受益しているからです。
受益者の負担を考慮すれば、自家用車保有者や使用者、自転車や徒歩利用者、さらには使用していない人々も納得できる税制度が必要となります。
つまり、すべての道路の有料化です。走行距離に応じた負担(車・バイク・自転車などの軽車両も含め、すべてにスマートメーターの設置義務)。
この場合は、特定財源に戻すべきです。税負担者が適切に税の活用を評価できなくなるからです。
まとめ
ガソリンの税制度をめぐる議論は、単なる「価格の高い・安い」ではなく、国家財政や地方自治体の財源、さらに将来の社会インフラに直結しています。
- ガソリンには 税に税をかける構造(二重課税問題) があり、不公平感を招いている。
- 暫定税率は半世紀近く続き、もはや暫定ではなく制度化。廃止には地方財源の不安が伴う。
- 補助金での価格調整は一時的な対策にすぎず、年間1兆円規模の財政負担を生んでいる。
- EV普及が進めば、ガソリン税収は激減し、現行制度は立ち行かなくなる。
- 本当に必要なのは「EV優遇」よりも 発電・蓄電・使う習慣の再構築。
道路や交通網はすべての国民が恩恵を受ける社会基盤です。だからこそ、「誰がどのように負担し、どう使われるのか」が透明で納得感のある制度設計が求められます。
ガソリン税の問題は、そのまま 未来のエネルギー政策と税制の在り方 を問うものでもあるのです。