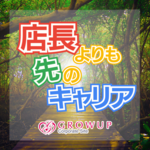Blog
教育投資で個人消費を刺激!リスキリング支援を全振りする未来
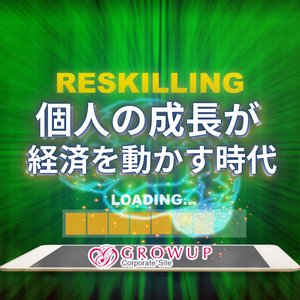
目次
リスキリング助成金、会社から個人へ直接給付してはどうか?

現在では、急速なデジタル化と産業構造の変化により、労働市場で求められるスキルが大きく変化していいます。
現行のリスキリングに関する助成金は、企業が従業員を育成する目線が強く、制度を利用した企業に助成金が支払われます。
現在の企業リスキリング支援では、労働市場の流動性向上や個人による主体的なキャリア開発を十分に推進できていません。
また、中小企業従業員や非正規雇用者、フリーランスなど十分な支援を受けられていない問題があります。
現行制度から変更した場合の解決すべき課題
・個人の主体的なキャリア開発の支援
・サポートの公平性確保
・不正受給の防止
・サポートの実効性の確保
現行制度との決定的な違い

サポート対象の拡大
現在:正規中心の約2,000万人
新認定:完全承諾者の6,700万人 → 支援対象が3.35倍に
個人へ直接給付することで対象者が一気に拡大します。
雇用のミスマッチはこの人財不足、担い手不足と言われた今でも解消はされていません。
女性、高齢者、ニートや転職困難者のために、直接給付の方が望ましいことは明白です。
効果の違い
現在:社内での配置転換が中心
新制度:産業人材移動が活性化 → 経済全体の生産性向上に直結
企業目線だけではなく個人目線やキャリアカウンセラーからの視点で社会の全体最適を考えるべきです。
雇用の流動性が増すと、労働市場での最適化を目指すことができます。
コストパフォーマンス
・助成要件を資格取得費の100%合格時、不合格時は学習時間で計算
・効果測定を収入増加、売上増加で計算
・成功事例をビックデータで開示
現行の制度では、企業側がリスキリング内容を決定しますので、個人が主体的に決定するわけではありません。
あくまでも業務の一環となります。
パフォーマンス的にも意思決定権は個人あることが望ましいと言えます。
フェルミ推定による経済効果試算

まず、基本となる数値を設定します。
制度対象人口:約6,700万人
リスキリングによる平均収入増加額:50万円
認定利用者の収入増加成功率:60%(キャリアカウンセリング効果を加味)
直接的な経済効果
1年目の直接的な経済効果
利用者数:50万人
成功者数:30万人(成功率60%)
収益増加額:1,500億円(30万人×50万円)
消費増加額:900億円(年収増加額の60%が消費に)消費性向は60%貯蓄性向40%
税収増加額:300億円(所得税・消費税)
3年間の累積効果
総利用者数:200万人(3年以内)
成功者累計:120万人
収益増加額:6,000億円
消費増加額:3,600億円
税収増加:1,200億円
波及効果の検証
労働市場への影響、産業構造への影響

現在の日本画抱える課題として、終身雇用、年功序列の日本の労働慣習のデメリットが多く出ており社会構造の変化に対応しきれていません。
労働市場の流動化、インフレ以上の賃上げ(実質賃金の増加)、成長産業への人財転換などです。
労働市場への影響、労働市場の流動化へ
転職市場の活性化
現在の転職率:約8.5%
認証後の移行見込み率:10%(+1.5ポイント)
年間の追加転職者数:約100万人
給与水準への影響、賃上げ効果
・リスキリング成功者の給与上昇が市場価格を押し上げる。
3年後の平均給与上昇効果:約2%(13万円/年)
産業構造への影響 雇用のミスマッチ解消へ
デジタル人材の増加数:年間10万人
新規事業創出:1,000社 / 年
起業数の増加:5,000社 / 年(制度利用者の1%が起業と仮定)
結論|日本経済への影響

年後の蓄積積効果を試算すると?
GDP押し上げ効果:約2兆円(0.4%)
新規雇用者数:30万人
平均給与上昇率:3%※インフレ率と同等かまた超える
労働生産性向上:5%~10%
令和時代は資産形成の時代です。
金融性資産だけではなく、スキルや能力、キャリアといった無形資産も個人で形成することが不可欠です。
どのような働き方を通じてどのようなキャリアを歩んでいくのか?
それは会社が考えることではなく、一人一人の個人が考えなければならないことなのです。
特筆すべきは、この制度が単に結果移転ではなく、個人の主体的な選択による「創造的破壊」がポイントです。
これにより、日本の産業構造の転換が加速し、国際競争力の向上につながっていくと考えられます。
結論として、提案の個人向けリスキリング支援制度は、現行の企業制度と比較して、より広範な対象者、高い成功率、大きな経済緩衝効果が期待できる、限りなく効果的な政策だと評価できます。