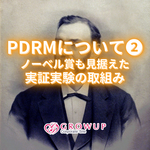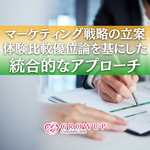Blog
他業種のビジネスモデル分析|第1回:SASAYAグループの成長戦略を探る

目次
兎我野町界隈に増殖している飲食店の謎をさぐる
大阪・兎我野町を歩いていると、ある共通点を持つ飲食店が点在していることに気づきます。
古民家を改装したお洒落な外観、駐車場はなく、店内はいつも満席…。
これらの店は偶然似ているのでしょうか?それとも、背後に何らかの戦略があるのでしょうか?
今回は、この「謎の増殖」の背景にあるビジネスモデルに迫ります。
坂上家グループ “焼き鳥・ホルモン・うなぎ・そば”などを多品目店展開

これらの店舗を運営しているのは「坂上家」という会社です。
一般的なチェーン店とは違い、同じ看板で画一的な店舗を増やすのではなく、焼き鳥、ホルモン、うなぎ、そばなど、様々な業態の店舗を展開しています。
驚くべきは、どの店も関東で人気の飲食店のコンセプトをオマージュしたメニュー構成である点です。
東京などで話題のメニューやコンセプトを大阪で再現しつつ、古民家という独自の空間価値を加えるという絶妙な差別化戦略です。
坂上家など10社以上をホールディングするSASAYAグループ

実は坂上家は、株式会社SASAYAホールディングスというグループ企業の一社にすぎません。
SASAYAホールディングスは、坂上家を含む10社以上の事業会社を束ねる企業集団です(※公式サイトでは現在16社が紹介されています)。
興味深いのは、これらの事業会社がエリアごとに分かれており、各社の名前がFCオーナーの名前を冠している点です。
創業から17年で50~60店舗を展開し、従業員数は825人というスケールに成長しています。
不動産取得及び飲食店向け改装のリースと食材購入及びロイヤリティなどの複線収入?
SASAYAグループの最大の特徴は、そのビジネスモデルにあります。
一般的な飲食チェーンとは全く異なるアプローチを取っています。
・ホールディングスが好立地の物件(多くは路面の古民家)を取得
・物件を飲食店向けに改装
・FCオーナーに物件をリース
・食材供給やブランド使用料などのロイヤリティも徴収
これにより、不動産収入と飲食事業収入という二重の収益構造を確立しています。
特筆すべきは、コロナ禍で多くの飲食店が苦戦する中、SASAYAグループはむしろ出店を加速させた点です。
廃業した飲食店から好立地物件と人材を確保する絶好の機会と捉えたのです。
従来のチェーン店とは違い、労働者が集まる出口戦略

最も革新的なのは、人材に対するアプローチです。
従来の飲食業界では、キャリアパスが不明確で将来展望が持ちにくいという課題がありました。
SASAYAグループでは、FCオーナーとして事業会社の代表になるという明確な「出口戦略」を示しています。
これにより、単なる雇用ではなく「将来の経営者」としての成長機会を提供し、優秀な人材が自然と集まる仕組みを構築しています。
FCオーナーにとっては、物件取得コストや開業リスクを抑えながら経営者としてのキャリアを築ける魅力的な選択肢となっています。
SASAYAグループの事例は、飲食業の枠を超えて多くのビジネスに示唆を与えてくれます。
不動産活用と人材育成を組み合わせた独自のパートナーシップモデルは、様々な業界で応用可能な考え方かもしれません。
風俗店の経営についても出口戦略は重要です。
ちょっとした視点の変化からでも十分に参考にできるビジネスモデルです。
※本記事は、公式HPや店舗の展開状況などから筆者の視点で読み解いた分析となります。確定情報ではない点をご了承ください。
ビジネスモデルの分析手法の一例としてお考え下さい。
次回は別の業種の革新的ビジネスモデルを取り上げる予定です。
お楽しみに!