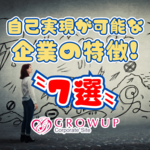Blog
共感マーケティング入門|ペルソナ設計からブランディング戦略まで徹底解説
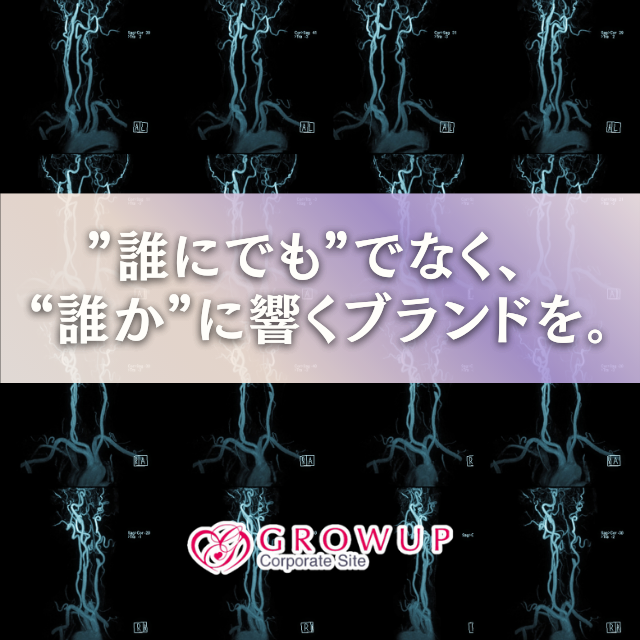
誰しもに好かれるブランドは存在しません。
しいて言えば大谷選手ぐらいでしょうか。
もっとも彼も敵チームのファンから悪意のあるヤジをもらうこともあります。
貴方が商品開発する場合に顧客を絞り込まず、誰にでも受け入れられるようなマーケティングをしていたら、危機感をもったほうがいいでしょう。
おそらくそのマーケティングでも誰にも共感されない商品になることでしょう。
今回のブログでは何故ペルソナの設定が必要なのか、わかりやすく解説していきます。
目次
ブランド(このブログでは、商品・サービス)がファンにしたい象徴的な人物像【ペルソナ】を設定する

ペルソナとは、商品やサービスのターゲットとなる「理想的な顧客像」を具体的な人物として設定したものです。
単に「20代女性」「30代サラリーマン」といったざっくりとした設定ではなく、年齢・性別・職業・ライフスタイル・価値観・行動パターンなどを細かく決めます。
よりリアルな顧客像を設定し共感するポイントを仮説していきます。
| ペルソナ設定例:佐藤 美咲(29歳・東京都在住) | |
|---|---|
| 職業 | IT企業のマーケティング職 |
| 年収 | 約500万円 |
| 趣味 | カフェ巡り、ヨガ、旅行 |
| 価値観 | ナチュラル志向で、肌に優しいコスメを求めている |
| 購入行動 | SNSや口コミ・レビューサイトの影響を受けやすい |
・デモグラフィック:属性、家族構成・職業・年収・可処分所得など
・サイコグラフィック:趣味・嗜好・余暇の過ごし方(時間の優先項目)
・ジオグラフィック:居住地・就労地・アクティブエリア
・行動特性:購買行動における習慣や癖
・何から影響を受けているか?(意思決定権):家族・パートナー、友人・知人
・育成歴(学生期・社会人期):どのような人格形成をしてきたのか?どんな経験・体験をしてきたのか?
あくまでも象徴的な人物設定ですので、市場の収益性が担保されるボリュームゾーンを狙っていくことが必要です。
エッジを効かせすぎると、市場は独占できるかもしれませんが、ビジネスとして成り立たないためです。
ペルソナを設定するメリット4つ(顧客視点・共感POINT・マーケティングの効果性分析・関係者間の共通認識)

ペルソナを設定すると顧客視点でも物事を決めることができます。
人物像を具体的にすることで、その人のライフスタイルに商品・サービスがどのシーンで利用され、どのような場面で再認されるか、想像できるようになり、浸透をはかることができます。
「何に反応してくれるか」
「購買行動後の体験の変化によって、どんな感情を抱くか」
ファンづくりの要諦は、狙ったターゲットと共感する仕掛けを作りだすことです。
共感するポイントについて
ターゲットとするペルソナが今、どのような困りごとがあるかということを推論することから始めます。
既存のサービス・商品との差別化を図るためには競合分析、特に既存の商品サービスとの明確な違いを打ち出すことです。
代替する、問題解決のための異なったアプローチをする、競合他社との価格的な差別化をすることなどが挙げられます。
また商品・サービスの体験時の感情変化を明確に狙い定めることでブランド価値を高めることができます。
マーケティングの効果性分析について
ブランドを認知してもらい、興味・関心をもってファン化していく一連の流れには、顧客の行動及び感情の変化が伴います。
コンセプトダイヤグラムやカスタマージャーニーなどで設定しておくと、実際の口コミやレビューとの差異分析が可能となります。
マーケティング施策があっているのか?その効果性を図ることができるのです。
関係者間での共通認識
ブランドとして何を発信していくのかを共通認識しておかなければ、一貫性が保たれません。
ブランドマーケティングには、インターナルブランディングとエクスターナルブラディングがあります。社外に発信していくためには、まずは社内浸透が不可欠なのです。
そのためには、社内浸透していく仕掛けや共通認識が必要です。
ペルソナの作り方(セグメンテーション・ターゲッティング・属性などの深堀)
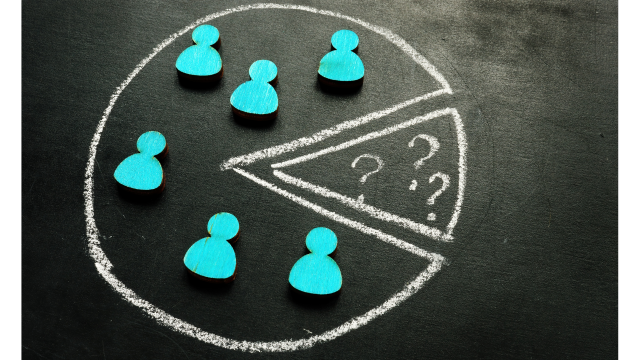
まずは狙う市場を分析します。
性別・年代・地域などで人口ボリュームを把握し、市場規模を調べます。
その市場をセグメンテーションしてきましょう。
セグメンテーションとは、市場全体に共通の特徴やニーズを持つグループに分類する
・地理的セグメンテーション(地域・気候・所得など)
・心理的セグメンテーション(ライフスタイルや価値観)
・行動的セグメンテーション(購買行動や使用状況)
・属性的セグメンテーション(年齢・性別・職業・学歴など)
セグメンテーションを行うことで、以下の特典があります
・適切な最適に最適なメッセージを届けられる
・ 競争を競争を避け、独自の市場を開拓できる
・ マーケティング予算を効率的に使える
セグメンテーションできれば、どの市場を狙うのかターゲティングです。
ターゲットのボリュームを仮説するにはフェルミ推定が有効でしょう。
詳細なデータが手元にない場合や、ざっくりとした市場規模を短時間で知りたいときに役立ちます。
フェルミ推定を使うことで、論理的な仮説を積み上げて、目標層の推定のボリューム感を推測できます。
フェルミ推定とは
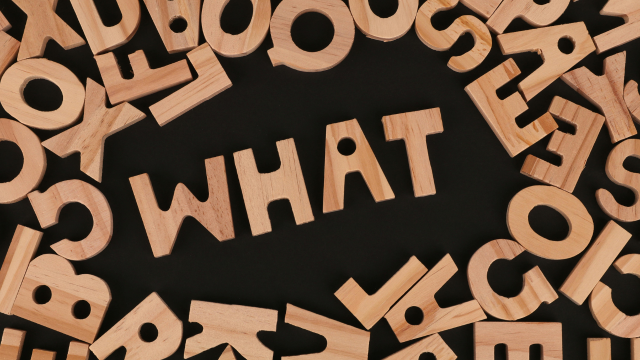
「与えられたデータが限られている状況で、論理的な分解と近似を行い、おおよその数値を見積もる手法」です。
市場規模が見込めない状況下では、ブルーオーシャン戦略をとることが可能ですが、そもそもその池には魚がいません。
顧客を創造・育成することが必要となっていきます。
市場規模が大きなセグメントでは、競合もひしめき合っていますので、価格競争に陥ってしまうことにもなりかねません。
そこで大切なことがポジショニングなのです。
競合との有利なポジションを探して、橋頭堡を築くのか?ニッチ市場を狙い育てていくのか?競合のシェアの補完を狙うのか?それぞれの戦略によってポジションを取りに行くのです。
ポジショニングに狙いがないと惰性的に決まります。
また競合にも動きが出ますのでポジションは常に流動的だと考えておきましょう。
補足ですが、ポジションを作り出す、動かす力はケイパビリティ(継戦能力)と言われております。
こちらは組織論になりますので、他のブログをご参考くださいね。
消費者の購買行動は感情に左右される。その感情に刺激を与える仕掛けが必要
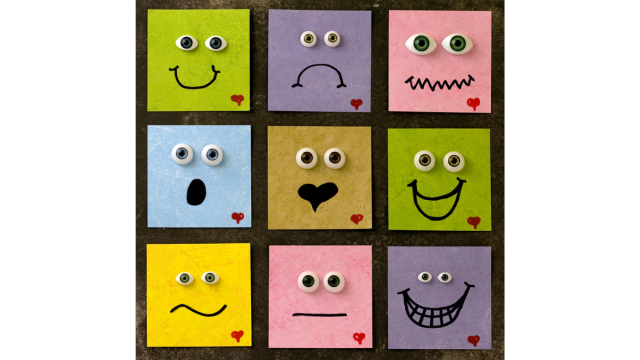
消費者の購買行動は、欲求・願望から始ります。
その行動に影響を与えることがインフルエンスです。
このブログではエフェクター(影響者)をします。
エフェクターには、人・広告・メディア・SNSが存在します。
人:家族・友人・知人など
広告:TVCM、SNS広告、
メディア:TV、雑誌、新聞、ニュースなど
SNS:インフルエンサーや芸能人、動画など
様々なエフェクターが、個人の購買行動に影響を与えているのです。
最も効果的な方法は、複数のエフェクターを組み合わせて一貫したメッセージを届けることです。
・インフルエンサーがSNSで商品を紹介(SNSの影響)
・雑誌やニュースで「今話題の○○」として特集される(プレスリリース)
・TVCMやYouTube広告でブランドのストーリーを伝える(ナラティブアプローチ)
・実際に使ったユーザーがレビュー投稿し、友人の間で広がる(人の影響)
このようにエフェクターを連携させることで、消費者の感情を刺激し、購買行動へとつなげることができます。
購買行動に導く感情変化を捉えることができれば、再購買(リピート)する仕掛けも作っておくことも同じようにできます。
リピートの仕掛けとして
・購買行動の承認(自己承認バイアス)「自分の行動は正しかったんだ」
・購買後のフォローアップ
・購買頻度の短縮させる仕掛け(30日以内)
・レビューや口コミなどコミュニティ貢献度によるインセンティブ設定
などです。
グループが追求する新しいメディアの可能性=ユーザ体験メディア
運営者の発信の体験動画と異なり、ユーザの体験を動画化した体験動画は、情報の非対称性を解消させることだけでなく、新たなメディアになる可能性を含まれています。
生成AIの活用で、個人ごとパーソナライズされた体験動画の生成が、新たな顧客に共感を生み出す仕掛けとなり、新しい時代のメディアになっていくでしょう。