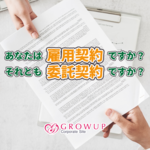Blog
バーナード理論の深掘り|「組織は生きている」ことを理解する
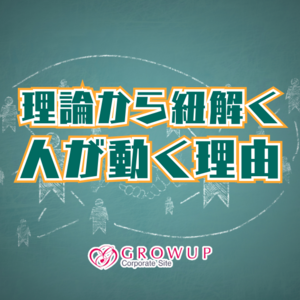
組織を「機械のように動かすもの」と捉えるか、それとも「人と人の関係によって成り立つ“生き物”」と考えるか。
この問いに対し、明確に後者を選んだのが、経営思想家チェスター・バーナードです。
バーナードは「命令・服従・組織の目的」といった言葉を使いつつも、その本質は“人間関係の調和”と“自律的な協働”にありました。
今回は、バーナード理論の中でもとくに重要な3つのテーマを深掘りし、「人が自発的に動く組織づくり」への実践的ヒントを探っていきます。
組織の3要素と「協働システム」

バーナードは、組織を「協働のシステム」として定義しました。
彼によれば、組織が成り立つには次の3要素が必要です。
| 組織の3要素 | 説明 |
|---|---|
| 共通目的 | すべての構成員が納得できる「目指すべきゴール」 |
| 協働意思 | 一人ひとりが「この組織で一緒にやっていこう」と思う気持ち |
|
意思疎通 (コミュニケーション) |
メンバー間の信頼と情報の循環がスムーズであること |
この3つの要素が整ったとき、組織は単なる「人の集まり」から、“力を発揮するチーム”へと進化します。
とくに「協働意思」は、給与や制度では買えない“関係性の価値”であり、労務管理上の要となります。
権限ではなく「受容される命令」が組織を動かす

バーナードの名著『経営者の役割』で有名な概念が「命令受容の4条件」です。
彼は、上からの命令が成立するには、受け手が納得して初めて効力を持つと説きました。
📌 命令受容の4条件
- 命令の内容が理解できること
- 命令が組織目的と一致していること
- 個人の価値観と矛盾しないこと
- 実行が可能な状況であること
つまり、どれだけ肩書や権限があっても、これらが欠ければ「命令」は無効。
この考え方は、“納得と共感のない指示は意味を持たない”という現代のマネジメントの本質にも通じます。
公式組織と非公式組織|“雑談”が組織を支える

バーナードはまた、組織には「公式組織」と「非公式組織」の両方が存在することを指摘しました。
| 種類 | 説明 | 現場での例 |
|---|---|---|
| 公式組織 | 意図的に構築された仕組み(役職・命令系統など) | 組織図、規則、マニュアル |
| 非公式組織 | 自然発生的にできる人間関係や文化 | 仲の良いチーム、ランチ仲間、雑談 |
バーナードは、非公式組織こそが、公式組織の潤滑油になると考えました。
上司に言えない本音、相談できる人間関係、ちょっとした笑い――
こうした非公式なつながりが、人の不安を和らげ、モチベーションを下支えしているのです。
まとめ|バーナード理論は今こそ活きる

| 理論要素 | 現場での活かし方 |
|---|---|
| 組織の3要素 | 「目的の共有」「信頼関係」「対話の機会」をつくる |
| 命令受容の4条件 | 指示前に「納得・共感・実行可能性」をチェック |
| 非公式組織の重視 | 雑談・相談・信頼の空気を“意図して”育てる |
バーナードは「マネジメント=人間理解」だと考えていました。
ルールや管理よりも、人の内面と向き合うことこそ、組織を強くする鍵だという彼の思想は、働き方が多様化した今だからこそ、改めて見直す価値があるのではないでしょうか。