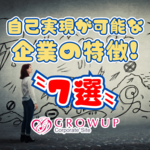Blog
BANI時代の経営に必要なのは“直感力”?感覚・経験・どんぶり勘定のススメ
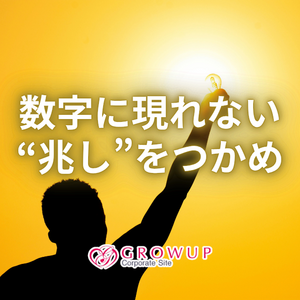
最近、会議で「なんか感覚的にはうまくいきそうな気がするんだよなぁ」という発言に、若手スタッフが少し困惑していたのが印象的でした。
でも、それって実は、これからの経営に必要な“感覚”かもしれないのです。
目次
経営環境は、VUCA時代からBANI時代へ

かつて私たちは、VUCA(ブーカ)時代と呼ばれる「不安定・不確実・複雑・曖昧」な時代にどう立ち向かうかを考えていました。
しかし今、世界はさらに一歩先へ進み、BANI(バーニー)時代に突入したと言われています。
BANIという概念は、2020年のCOVID-19パンデミック中に、未来学者で作家のジャメイス・カスシオ(Jamais Cascio)氏が提唱しました。
BANIの4要素:
- Brittle(もろい)
- Anxious(不安な)
- Nonlinear(非線形)
- Incomprehensible(理解不能)
BANIは、VUCAの限界(軍事・経済発の概念で、変化の「スピード」や「心理的影響」への対応が弱い)を補完・更新する次世代フレームとして登場しました。
変化は加速度を増し、「過去の延長線上に未来はない」とすら感じられるようになりました。
VUCAとBANIの比較
| 要素 | VUCA時代 | BANI時代 |
|---|---|---|
| 不確実性 | 高いが予測可能 | 不安と予測不能が混在 |
| 複雑さ | ロジックで整理できる | ロジックが通用しない場面も増加 |
| 対応方法 | 計画と分析 | 感覚と柔軟性 |
つまり、BANI時代は「わからなさ」と共存する力が問われるのです。
データから導き出す経営は、時代の変化のスピードに追い付かない

もちろん、数字やデータは大切です。
でも、データを収集・分析し、意思決定に活かすまでのプロセスには「時間差」があります。
その間に、環境は一変しているかもしれません。
これまでの“正解パターン”に当てはめようとするほど、変化に置いていかれる。
そんなジレンマが、現場では起こっています。
数字は結果であり、過去の行動や外部環境の変化からきている
経営会議の場で「数字を見てから考えよう」という言葉をよく耳にしますが、それは本来、「過去を振り返る行為」でしかありません。
たとえば売上データ一つ取っても、その背後には必ず因果があります。
- 何を、いつ、誰に、どんな価格・手法で売ったのか
- 天候や曜日、他社の動向、社会情勢など外的要因
- SNSでバズった・広告が不発だったなどの偶然性
これらが複雑に絡み合って「数字」という結果になっているのです。
言い換えれば、数字だけを見ても“なぜそうなったか”はわからない。
しかも、数字は「変化の後」にしか現れません。
変化の「兆し」→ 行動 → 結果 → 数字
この時間差の中で、現場はすでに次の変化に向かって進んでいます。
そのため、「数字を見てから動く」のでは、一歩遅れた判断になりがちです。
たとえば…
- 🟠 2週間後に来店数が急落した
- ↳ 実はその3週間前にInstagramの発信頻度が落ちていた
- ↳ さらに4週間前に投稿内容が“自己満足寄り”になっていた…
このように、数字はあくまで“最後に現れるシグナル”に過ぎません。
それよりも、数字に至るプロセスの変化や違和感にいち早く気づく感性こそが重要なのです。
その数値の変化も経験と捉え、直感とどんぶり勘定が新たな仮説を導き出す

では、その数字の変化をどう捉えるか?
ここで重要なのが、「数値も一つの“経験”として扱う」という視点です。
経営とは、実験の連続です。
仮説を立てて、施策を打ち、結果を見て、また仮説を更新していく。
数字の上下も、「これは次にどう活かせるか?」という“問いの種”になるのです。
このとき役に立つのが、“どんぶり勘定”という名の大胆な仮説力です。
「どんぶり勘定」は悪なのか?
日本では「どんぶり勘定=ずさん・非合理」という印象がありますが、本来は「細部にとらわれず、大局で捉える仮設思考」とも言えます。
たとえば:
- 💡「ざっくり見て、このまま放置したら売上10%落ちるな」
- 💡「たぶん今月の顧客単価は上がる。客層の変化を感じるから」
これらはデータが出る前に動ける仮説です。
精密なシミュレーションでは出せない、“肌感覚からくる洞察”なのです。
本来「どんぶり勘定」とはずさんな管理を指す言葉ですが、BANI時代の仮説駆動経営においては、数字にとらわれすぎず、大胆に仮説を立てる“思考の柔軟さ”とも捉えられます。
つまり、「どんぶり勘定=大胆な仮説力」という逆説的な再定義が、今こそ必要なのです。
カンと経験が「仮説生成装置」になる
経営者や現場マネージャーが「なんか変だぞ」「この流れ、前にもあった」というとき、それは過去の膨大な経験知から無意識に導かれた“仮説の芽”です。
数字には現れない「違和感」の例:
- 数字に現れない小さな違和感
- お客様のちょっとした表情の変化
- 店舗の空気感、スタッフの姿勢のズレ
これらを「無視せず言語化する力」が、これからの経営に求められます。
そして、あえてざっくりと仮説を立て、走りながらチューニングしていく。
完璧な分析ではなく、変化に喰らいつく思考と行動の速さ。
これこそが、BANI時代における“どんぶり勘定経営”の強みなのです。
失敗から学び、直感を鍛える方法

「カンを頼りにしていいのか?」と不安になる方もいるかもしれません。
確かに、根拠のない直感に賭けるだけでは、ただの博打になってしまいます。
ですが――
直感とは、“過去の経験と失敗の統合知”によって磨かれるものです。
失敗は“感覚の精度”を高める材料
たとえば、こんな経験はないでしょうか?
直感が当たった、よくある現場の例:
- 「なんかこのお客様、クレームになりそうな気がする…」と思ったら的中した
- 「このキャンペーン、たぶんうまくいかない」と思ったらやはり反応が悪かった
- 「なんとなく今日の売上は高そう」と感じたら当たっていた
これらは偶然ではなく、過去に蓄積された失敗・成功パターンの記憶から生まれる直感です。
しかも、失敗は成功以上に深く感情に刻まれるため、直感に影響を与える力が大きい。
大切なのは、「失敗した」という事実ではなく、そこから学びを得ること。
以下のような問いを繰り返し、自分の感覚と行動を見直すことが重要です:
- なぜそうなったのか?
- どの時点で兆候があったか?
- 次に似た状況が起きたら、どう判断するか?
それが、直感を“再現可能な思考”に近づけていく訓練となります。
カンは鍛えられる。「違和感に名前をつける」習慣を
直感を鍛える最も実践的な方法は、「違和感に名前をつける」ことです。
直感と観察のセットで「なぜ?」が見えてくる:
- 🔹 「いつもと空気感が違うな」 → 「笑顔が少ない」「声が小さい」
- 🔹 「この商品が今日は売れなさそう」 → 「陳列位置が悪い」「お客様の足が止まらない」
このように、抽象的な違和感を具体的な言葉に変換するクセをつけることで、カンは“言語化された知識”に昇華され、再利用可能な武器になります。
直感は天性ではなく、磨かれるスキルなのです。
【まとめ】「感覚」はこれからの経営資源になる
VUCAを超えたBANIの時代、計画も予測も、通用しないことが当たり前になってきました。
だからこそ、人間の“感覚”に再び光が当たっているのだと思います。
データは大事。だけど、それだけじゃ遅い。
すべての体験が、学びと“カン”になる:
- 数字の変化も、経験として咀嚼しよう。
- 直感やどんぶり勘定も、仮説として活用できる。
- 失敗こそが、カンを鍛える最大の材料。
そして何より――
「感覚」を言語化し、周囲と共有できる力が、組織全体の直感力を高めていきます。
もしかしたら次に会社を救うのは、誰かの「なんか、変じゃない?」というひと言かもしれません。