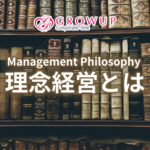Blog
AIに奪われない仕事とは?12年前の予測と今を比べて見えてきた“人間にしかできないこと”
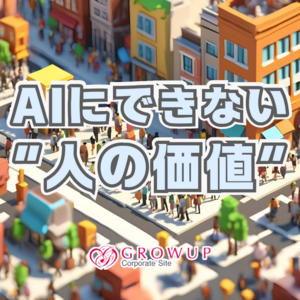
「AIに仕事が奪われる」と言われ始めて約10年。
当時の予測はどれほど現実になったのでしょうか?
この記事では、2013年の“AI代替予測”と現在を比較しながら、本当にAIにできること/できないことを見直します。
最後には、「AI時代に残る仕事とは何か?」という本質的な問いにも迫ります。
目次
国内で事務職は180万人余剰になる!?

AIやRPA(業務自動化)の進化により、事務系の業務が急速に自動化されつつあります。
経済産業省の報告では、2025年までに日本国内で約180万人分の事務職が余剰になる可能性があるとされています。
書類作成、データ入力、スケジュール管理といった「繰り返し型の業務」は、AIにとって得意分野。
確かに、私たちの周りでも無人受付やチャットボットの導入が進んでいます。
AIの代替確率とは?

「AIに奪われる仕事」という言葉が話題になったのは2013年。
英オックスフォード大学が発表した論文がきっかけでした。
この論文では、702種の職業を対象に「AIによって代替される確率」を算出し、大きな注目を集めました。
例えば、会計士:94.5%、銀行窓口業務:97.6% など、高い数値が並びました。
以来、AIの進化とともに「どの仕事が残るのか」が多くの人の関心事となっています。
2013年と2025年の代替確率の比較はこんなに違う。
実は、12年前の予測と現在の状況を比べてみると「思ったよりAIに置き換わっていない」仕事も多くあります。
| 職業名 | 2013年予測 | 2025年現在の状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般事務職 | 96% | 高い自動化進行中 | RPA・チャットボット導入進む |
| 銀行窓口業務 | 97.6% | 多くが無人化 | ATM・アプリ化で業務縮小 |
| 会計士・経理 | 94.5% | 一部自動化進行中 | クラウド会計・税務AIなど活用 |
| 医師(診断補助) | 23% | 補助として活用中 | 画像診断AIや問診AIが登場 |
| 教師 | 1% | 代替進行中 | オンライン教育補助は進むが本質は人間性 |
| カウンセラー | 0.3% | 代替進行中 | 壁打ちや自問に向く |
| 弁護士 | 3.5% | 補助ツール活用中 | リーガルテック進展も「判断」は人間 |
| 研究職 | 15% | AIが仮説生成などで補助 | AIと共同研究が進む傾向 |
| コンテンツクリエイター | 8% | 一部代替進行中 | 画像・文章生成AIの活用増加 |
| 芸術家・表現者 | 1%未満 | 代替困難 | 人間固有の「感性」が求められる分野 |
たとえば、教師やカウンセラー、介護士など「人と人との関係性」が中心の仕事は、2025年時点でも依然として代替困難とされています。
AIは情報の処理は得意でも、「共感」や「空気を読む」といった人間ならではのスキルは苦手だからです。
また、弁護士や研究者といった専門職も、「AIがサポートはするが、完全に置き換わるのはまだ先」と見られています。
AIは過去の分析から法律や仮説思考までこなす。

とはいえ、AIの進化は目覚ましく、今や契約書の作成補助、裁判例の検索、仮説の生成、さらには研究論文の執筆補助までこなすようになっています。
ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AIは、質問に対して「それっぽい答え」を出すだけでなく、複雑な法律・医療・工学知識を含んだ回答すらできるようになってきています。
もはや「AIにはできない」と思っていた領域すら、次々と手の内に入れてきているのです。
AIにとってかわられないのは、人生観のみ

では、AIに絶対に代替されない仕事とは何でしょうか?
答えは意外とシンプルかもしれません。
それは「その人にしか語れない人生観や価値観を、他者に影響を与える形で伝える仕事」。
つまり、“師匠”のような存在です。
たとえば、同じ教育者でも、カリキュラム通りに授業を行う「先生」は、AIや動画教材に代替されつつあります。
一方で、生徒の可能性を引き出し、時に厳しく、時に寄り添いながら人生を導く「師匠」は、AIでは決して代替できません。
そこには属人性(その人にしかできない要素)が強く関わっているからです。
このように、知識を伝える役割はAIでも可能ですが、人を“育てる”“変える”関係性を築く仕事は、人間にしかできないのです。
まとめ
AIに代替されない仕事は、もはやスキルの話ではありません。
「人と人の間にしか生まれない体験」を提供できるかどうか。それが最後に残る価値です。
人を介したサービス業は、表面上のやり取りだけでなく、「空気感」「人間性」「関係性」に支えられています。
だからこそ、どれだけAIが賢くなっても──
“あの人に会いたい”という気持ちだけは、AIにはつくれません。
たとえば、日本の性風俗業は、人間的なつながりの極みともいえるサービスです。
そこには身体性だけでなく、疑似的な感情の共有や、癒し・安心感といった非常に人間らしい価値が詰まっています。
どれだけAIやロボットが進化しても、「人に触れられている」「人に受け入れられている」という体感だけは、機械ではつくれない。
AI時代に残るのは、“人と人との間にあるもの”──それは、風俗という業界が教えてくれる、ひとつのリアルな答えかもしれません。
テクノロジーが進化すればするほど、「人と人とが直接ふれあう瞬間」には、逆説的にプレミアムな価値が宿るようになります。
AIが効率や利便性を極める時代において、非効率で温もりのある“人間的な体験”は、むしろ唯一無二の資源になるのです。